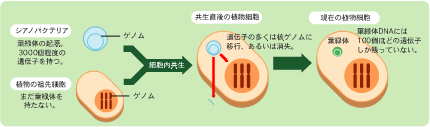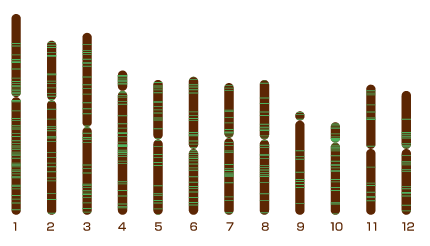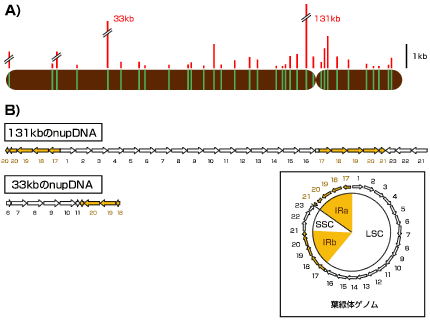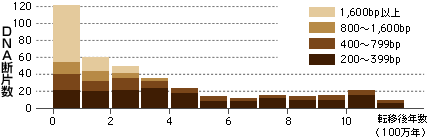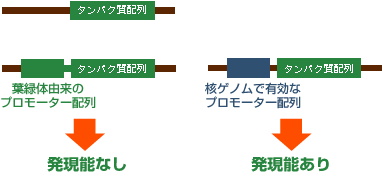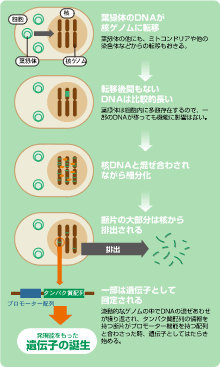ところで700箇所にも及ぶnupDNAは、葉緑体から核にいつ転移したのだろう。実は、葉緑体のDNAは、同じように細胞内共生の結果誕生したミトコンドリアのDNAに比べて、生物種間での配列の違いが非常に少ない。つまり、葉緑体ゲノムの進化速度は遅く、配列の変化が起こりにくいのである。ところが核に転移した葉緑体DNAは、核ゲノムの進化速度の影響を受けるので、nupDNAは核で過ごした時間の分だけ配列を変化させているのだ。そこで現在の葉緑体にあるDNAとnupDNAとの配列を比べると、個々のnupDNAがいつ頃葉緑体から核へ転移したのかを推定できる。
その結果、核ゲノムに散在するnupDNA集団はその大部分が100万年以内に転移した若い断片で構成されており、転移後の年数が長くなると存在量が急速に減ることが明らかになった(図4)。人間社会に例えるなら、出生率が高く、平均寿命が短い年齢ピラミッドを形成しているのである。また、若いnupDNAは一般にサイズが大きく、年齢の進行と共に急速に断片化が進み、転移して数百万年を経た高齢のnupDNAは小さな破片ばかりであることも明らかになった(図4)。
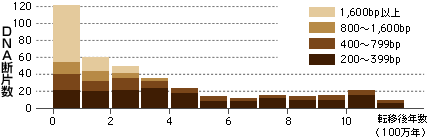 |
図4 nupDNAの長さと転移後年数の関係
nupDNAは大部分が100万年以内に転移しており、それ以上古いものは著しく少ない。転移するDNAは1,600bp以上の長い断片が多いが、年数と共に急速に断片化が進み、短くなっている。 |
このようなnupDNA集団の特徴から、葉緑体ゲノムと核ゲノムの密接な関係が見えてきた。葉緑体DNAはかなり頻繁に核ゲノムに取りこまれる性質があり、そこで染色体DNAと混ぜ合わされながら次第に細片化され、やがて核から排出されて消えていく…このようなダイナミックな出来事が、過去から現在に至るまで、イネの細胞の中で連綿と続いてきたのだろう。このDNA転移の頻度は、一つの遺伝系統だけを考えると数万年に一度程度のものだが、例えば1ヘクタールの水田といった規模で考えると、毎年、新たなDNA転移をもった種もみが数千生まれている計算になる。
私たちは、このような葉緑体から核へのDNAの流れを、一定の流速を持った定常的な流れ、という意味を込めて、「DNAフラックス」とよんでいる。植物の核と葉緑体のゲノムは、これまで互いに独立した存在であることが強調されてきた。しかし、少し長い時間の流れや集団の広がりのなかで捉えると、両者はむしろ、連続したDNAの流れでつながった流動的な実体であると見ることができる。 |
|
|
|