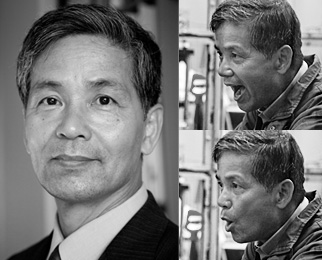楽天家の末っ子
東京深川の教員寮で、小学校教師の両親と男の子3人がちゃぶ台を囲んで食事をしている。それが子ども時代の記憶です。昭和25年に愛媛の松山で産まれましたが、1年ほどで、両親が青雲の志をもって上京したんです。時は朝鮮特需で経済が右肩上がりの時代です。僕は末っ子で兄たちとは8つと6つ離れていましたから遊び相手にはならず、兄たちが飼っていた伝書鳩の世話を手伝う役目でした。小学校4年生の時、千葉県の船橋に家を建てて引っ越しました。父が3人の子どもの勉強部屋兼書斎を作り、そこにブリタニカの百科事典や世界美術、日本の歴史、世界の歴史などの全集を並べたのです。そこが僕のお気に入りの場所になりました。小学校はそのまま深川で1時間以上かけて通学しており、近所に友達がいなかったんです。しかも両親が働いて鍵っ子でしたから自ずと書物が友達になりました。百科事典を眺めたり、全集を片っ端から手に取ってみたり。兄たちが2メートル四方の大きな鳥小屋を作ってインコやブンチョウ、ジュウシマツなどの小鳥からキジやチャボまでいろいろな鳥を飼っていたので、ここでも鳥の面倒をみていました。ハムスターやリス、ヘビも飼いましたね。歳の離れた兄たちとの共通の話題はもっぱら動物のことでした。周囲は自然だらけですから、夏には虫取りをし、あぜ道でカエルやザリガニを捕まえました。まあ普通の男の子です。
中学校は都内の両国中学に進みました。実は、中学1年の終わる春に母を亡くしています。当時は反抗期で病床の母を思いやることができなかったのが今も心残りです。すでに大学を出て建設会社に勤めていた長兄が母親代わりに食事や弁当を作ってくれました。末っ子が不憫だったのか、トランペットやフルートも買ってくれて、楽器も楽しみましたね。高校は両国高校、旧府立三中です。公立の小学校、中学校、高校を出て、国立大学に行く。当時は国立大学の月謝が千円ですから、それ以上の親孝行はないわけです。特に東京大学に行きたいと思ったことはないけれど、下町のできる子たちがみんなそうするように両国高校に行って東大に行くものだと思っていました。高校生になっても学校が好きで、どの教科も大好きだったんです。こんなの珍しいかな。当時は受験に9科目必要でしたけど、なんでもおもしろく苦になりませんでした。こうやっていつまでも勉強を続けられたらいいなと、それが夢でした。イメージしたのは高校の世界史に出てくるギリシャの哲人です。白い服を着てなんかこうぞろぞろと歩きながら森羅万象を語る。よし、これになろうとね。数学も物理も面白いけど、数学者や物理学者になりたい訳ではない。きっと哲学だろうと思いました。受験勉強が忙しくて実は哲学書なんて読んだこともないのに大学の志望は哲学にしたのです。同級生は医者だ弁護士だと言っていたけれど、そんな気持ち理解できませんでしたね。1960年代は経済成長期ですから就職のことは心配していなかったのです。父も兄達も戦争の苦労を知っているので、末っ子には好きにさせてくれたのだと思います。

2歳半松山にて。末っ子でかわいがられた。

小学校入学前。江東区立明治小学校に通った。

高校の修学旅行で京都へ。
学部は「山岳部」
東大を受験するつもりだったのに、その年は例の安田講堂事件の影響で東大の入試が中止、京都大学を受けました。京大に入らなければ霊長類の研究をすることはなかっただろうから、これも神様の采配です。ところが入学式に行ってみると総長がいるべき演壇は、ヘルメットをかぶった学生で占拠されている。全学ストで授業は全部中止です。そこで岩倉の農家に下宿していた下宿生で勉強会することになったのですが、そのテキストが「共産党宣言」。驚きましたね。みんな気分は革命家だったんでしょう。普通に勉強していた高校生がさあ大学に入ったはいいが、学問的方向づけはないまま、いきなり学生運動に直面させられました。僕たちは国に保証された特権的なエリートで、一方にベトナムで戦争をしている若者がいる。それをどう思うかと問われました。いやが上にも社会の問題を意識せざる得ない状況です。良心的な子ほど深く受け止めて悩んだと思います。その中で僕は山岳部に出会ったんです。高校時代も山岳部でしたから、授業がないなら山に登ろうと。京大の山岳部は中途半端ではない。毎月毎月山行合宿があり、1年120日山へ行きます。残りのうちの120日はそのための訓練です。毎日夕方大文字山を走って登る。他にやることがないから、日々次の山行に向けて体を鍛えていました。そうやって1年を過ごして2回生になるころには授業が再開したのですが、哲学というのが自分が想像していたものと全然違うことに驚きました。デカルトがこういったとかプラトンがこういったということを習うのですが、僕は彼らが言っている中身、この世界がどうなっているかを知りたかった。その上、哲学科に行くには、教養部の間にドイツ語とフランス語とギリシャ語とラテン語をマスターするように言われたんです。僕は言語学者になりたいのではないと思いましたが、実際それができる人が同級生にいる。これはショックでした。大学の学問は受験勉強とは違うということにようやく気づいた、パラダイムシフトです。僕が学問としてやりたいと思ってきたことは、学問でもなんでもなかったんです。呆然としますよね。学問についてガツンと一撃ですから。それで心のよりどころは山岳部です。同じように呆然としている子が集まってきていたんです。自然の中にどっぷり身を置きながら、ある種の緊張感をもって山へ登り無事帰ってくるという、達成感。そちらの方が、自分が生きているということが実感できたんです。
今の研究につながることは全て山岳部で学んだと思います。京大山岳部には初登頂の精神というのが脈々と受け継がれてるんです。未踏の山、未踏の沢、未踏の尾根を調べ、文献や地図や航空写真を集めて研究し、目標を定めます。山岳部が掲げている標語はパイオニアワーク。まだ誰も行っていないところに行くことが重要でした。結局一年留年して5年生まで毎月毎月山に行っていました。5年生の時にヒマラヤの世界で3番目に高い山カンチェンジュンガ、その西峰であるヤルン・カン(8505m)に行くチャンスが巡ってきたんです。山岳部の生活はヒマラヤへの道だと思っていましたから嬉しかったですよ。70歳の西堀栄三郎さん西堀栄三郎
【にしぼり・えいざぶろう】
(1903年−1989年)科学者、技術者、探検家。京大山岳会、日本山岳会。京大教員から民間企業に移り、再び京大に戻り、第一次南極越冬隊の隊長を務めた。を隊長に、最年少の僕まで15人の部隊です。八千メートル級の登頂は京大学士山岳会(山岳部のOB会)の悲願でしたから、今西錦司さん今西錦司
【いまにし・きんじ】
(1902年−1992年)生態学者、動物社会学者、霊長類学者。競争ではなく棲み分けによる進化論を提唱した。京大山岳会、日本山岳会で登山家としても知られる。、桑原武夫さん桑原武夫
【くわばら・たけお】
(1904年−1988年)フランス文学者、評論家。学際的共同研究の先導者として知られる。今西錦司と京都大学の同期であり登山家としても活躍した。、西堀栄三郎さんという大先輩がいて、その下に梅棹忠夫さん梅棹忠夫
【うめさお・ただお】
(1920年−2010年)生態学者、民俗学者。今西錦司に師事し、登山家、探検家としても知られる。国立民族学博物館の設立に尽力し、初代館長に就任。、KJ法の川喜田二郎さん、照葉樹林文化論の中尾佐助さんなど、錚々たる人たちがいらして、計画を実現していくのです。15人の隊員だと20人くらいのシェルパが必要で、60日間登るとなると2100人日となります。さらにこの2100人日分の食料や装備類を五千五百メートルの高さのベースキャンプ(登山基地)まで持ち上げなくてはならないので、約四百人のポーターが必要です。一番若い僕が食料を全部準備する食料係を任されました。寄付を集めるところから始まって、食料を集めます。梱包して10トンの荷物にまとめて、船に乗せて、通関の手続き、これを全部一人でやるんです。もちろん先例をお手本にするのですが、本当に鍛えられました。何年も前にヤルンカンという山を見つけ、偵察をして、交渉して、許可を得てと、出発までには沢山の人の願いと汗と涙があるのですから、寝る暇もなく準備に明け暮れました。途方もない仕事でしたけれど、自分が登りたくて行く訳ですから、苦しくはありませんでした。準備ができて、日本を出たら半分成功したようなものです。船から荷を降ろして、通関業務をして、トラックでダランバザールという山麓の町まで運び、四百人のポーターを手配して、五千五百メートルの基地まで上げるのです。それをしなければ山登りはできません。その日のために来る日も来る日も大文字山に登り、雪山を登り、岩壁を登ってきたのですから、みんなただ必死にやるだけです。そして日本初の八千五百メートル峰の初登頂に成功しましたが、残念ながら登頂隊員が一人亡くなりました。僕は七千四百メートルのキャンプにいたのですが、最年少の隊員としてもっと自分が力を発揮できたらという思いがあり、成功を喜ぶことはできませんでした。

京大生時代。時代祭に参加して扮装をした。


1973年京大学士山岳会、ヤルンカン登頂隊に最年少の隊員として参加。隊長は西堀栄三郎、7400mまで登った
人間は世界をどう見ているのか
年に百二十日山行で、百二十日訓練で、山に明け暮れる学生生活でしたが、あとの百二十日しっかり勉強すれば結構いい成績がとれました。三年生になって哲学科に進みましたが、世界を知りたいという興味に近いのは先人の訓詁学ではなく、実験心理学だと知りました。ベル研究所のベラ・ユレシュベラ・ユレシュ
(1928年−2003年)ハンガリー出身の実験心理学者。学位取得後渡米し、新設されたベル研究所に入所。1959年にランダムドットステレオグラムを発表した。がランダムドットステレオグラムを発表したところでした。これは一見白黒のランダムなパターンが、両眼の像を融合させると奥行きのある形を見せるというものです。世界がどう見えるのか、という認知の問題が科学的に実証できることを知りました。ちょうど京大心理学の柿崎祐一先生が、両眼分離刺激といって、左右の目に別々な画像を見せたときどういう現象がおきるかという実験をなさっていました。そこで、三、四年生の時は山に登りながら視覚の認知心理学をやっていたのです。ハプロスコープという装置を使って、両眼の情報が加算されていることを卒論にしました。視野闘争両眼視野闘争左右の眼でそれぞれ異なるものを見ていると、片方の眼で見ているものだけが見えるようになり、見える側がランダムな時間間隔で入れ替わる現象。という現象は日常では起こらないことを自分自身で体験できるところがおもしろかったのですが、そのような実験は百年も前から行われていて、論文も沢山でている分野でした。パイオニアワークではないわけです。そして世界を見ているのは目ではなく、脳が解釈しているのだから脳の研究をしたいと思い始めました。そこで大学院では脳の研究をすることにしたのです。脳の研究は人間ではできないからネズミを用いましたが、ユクスキュルヤーコプ・フォン・ユクスキュル
(1869年−1944年)ドイツの動物学者、哲学者。生きものの環境は、その生きものの知覚によって認識された世界である「環世界」であると考えた。著作に「生物から見た世界」「生命の劇場」がある。の「生物から見た世界」を読んで動物が見ている世界に興味があったので、ネズミの脳がどう世界を見ているか調べようと思いました。スペリーロジャー・ウォルコット・スペリー
(1913年−1994年)米国の神経心理学者。分離脳の研究によりデイヴィッド・ヒューベル、トルステン・ ウィーセルとともに、1981年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。とガザニガマイケル・S・ガザニガ
(1939年−)米国の神経心理学者。スペリーに師事し、分離脳の研究を続け、大脳の左右半球の連絡と機能分化の理解に貢献した。が分断脳、左右の脳半球の機能の違いを見つけた頃だったので、両眼の研究から両半球の研究へと移ったのです。自分が大学に入った時に持っていた本当のモチベーション、この世界はどうなっているのか、どう振る舞うべきなのか、という哲学が掲げている二つの質問に答えたい。つまり、この瞬間を見て理解しているのは人間の目ですし、五感を通してこの世界を理解しているわけですから、人間はこの世界をどう見ているのかという科学的研究がこの質問への答えを出すはずだと思いました。今につながる問いをもうこの頃持ったんです。ここが自分の学問の場だと。だから見るとか分かるとかとはなにか、それが分かるというメタレベルでの人間の心の研究を目指して、人間の両眼視の研究や、ネズミの両半球間の記憶の転移の研究をしようと思いました。修士課程に入り、動物の学習行動の研究を始めた頃ちょうど、ネズミを用いて脳内自己刺激の研究をなさっていた平野俊二先生が、京大に移って来られたので、これ幸いと最初の弟子になってマンツーマンで指導を受けました。脳の実験なんて初めてでしたが、平野先生は脳波を計る電極の作成、それを用いた測定、脳の組織切片を作っての染色と、全てを自分でなさるので、これを全て教わりました。師を超えたいと思ったら、先生より早く研究室に行って遅く帰るしかないわけですよ。休日もなしにラットの両半球間の記憶の転移における海馬の役割を調べました。二年半、研究スタイル、勉強の方法、論文の書き方とすべて平野先生の後姿を見て学んだんです。

ネズミの脳の研究を始めた修士1年の時。研究室にて。

見返り阿弥陀に会いに紅葉の名所永観堂へ。
霊長類研究へ
博士課程一年生の秋に京都大学霊長類研究所の心理学研究部門の助手の公募がありました。ネズミの脳には人間の脳のような皺がなく、左右の半球に違いは見られません。だからそこからは、人間の脳のことはわからない。これが僕にわかったことでした。そこで大学時代の人間の視覚の研究と大学院で身につけた学習行動を大脳生理学の実験手法で解析する方法を合わせ、サルの心理学に挑戦しようと思ったのです。サルが、この世界をどんな風に見ているのか、それを行動や学習を通して検証したいと応募書類に書きました。それを室伏靖子先生がおもしろいと思って採用してくれたのです。当時の助手は学位を取る前の学生が応募するのが普通でしたから、論文数を競うものではありませんでした。でも僕は学部の卒論を学会誌『心理学研究』に投稿し受理されていたのでそれが評価されたのだろうと思います。これは山岳部のおかげです。京大の山岳部は単に頂上を目指すだけではなく、学術調査をすることになっていましたから、先輩が気象や森林や地質やそれぞれの研究をして論文を書くのを見ていました。それで誰に教わらなくても、研究をしたら論文をまとめるものだということが身についていたのです。助手に任期制がない時代ですので、二十六歳になったばかりで終身保証のポストに就けてとても恵まれていたと思いますが、その分プレッシャーも大きかったですね。大学院生の真ん中の年なので学生の中に年上の人がいて、その人達は霊長類のことをよく知っているわけです。僕はサルの学名ひとつ知らないわけですから肩身が狭かったです。最初の二年くらいは暗中模索で、資料委員として標本を作る仕事をしたり冬の志賀高原での野生ニホンザルの調査に同行させてもらったりしていました。ちょうどその時、室伏先生がチンパンジーでの言語学習の研究を始めると決心されたんです。日本はニホンザルの研究では先進的でしたが、類人猿では欧米に十年遅れをとっていました。僕は助手ですから「松沢さん、あなた一緒にやってね」となったわけです。どうやったらいいか全く知らないところからのスタートでしたが、山岳部での初登頂の精神でやりました。今西さんたちからは自由な研究の姿勢は学びましたが、霊長類学については影響を受けていません。チンパンジーの言語習得の研究としては、ガードナー夫妻ガードナー夫妻(アレン・ガードナー、ベアトリス・ ガードナー)米国ネバダ大学の心理学者(当時)。チンパンジーに手話を教える研究の先駆けで、1969年サイエンスに「チンパンジーに手話を教える」という論文を発表した。が手話をワシューに教えた研究、プレマック夫妻プレマック夫妻(デイビット・プレマック、アン・プレマック米国ペンシルバニア大学(当時)の心理学者。1967年にサラというチンパンジーに色の付いたプラスチックの板(彩色片)を使って言語を教える実験を行い、チンパンジーが文章を作ることを証明した。がプラスチックチップでサラに言葉を教えた研究があったのでそれらの論文を読み解くことから始めました。ちょうどランボーランボー夫妻夫のデュエイン・ランボー(当時、米国ヤーキス霊長類研究所)は、チンパンジーの「ラナ」に図形文字を教え、チンパンジーがコンピュータを使って書き言葉を習得し、文章を作成できることを示した。夫人のスー・サベージ・ランボーは、後年、1980年代になって、ボノボの「カンジ」の言語能力とくに発話の理解の研究をおこなった。がコンピュータを使って図形文字を教える研究を発表したところだったのでこれを発展させようと思いました。大学院生と話しながら自分たちのシステムをゼロから作り上げていくのがとても楽しかった。そこへウィルソンの「Sociobiology(社会生物学)」の最後の二章、つまり霊長類とヒトの章の翻訳担当の話が来ました。そこでは個体というものは遺伝子の運び手にすぎないので、個体レベルの研究は縮小すると予測されていたんです。その時、それならこれこそ自分がやるべきものだと直感しましたね。登山の場合、山はそこに存在するものですけれど、学問の山は自分で見つける、自分で作るということです。この世界がどうなっているのかということを研究対象にしたいと思い続けてきて、チンパンジーの研究がそれだとは思ってもみなかったわけですが、チンパンジーはこの世界をどんなふうに見るのかという問いが成り立つことは確信しはじめていました。


助手に採用された頃。霊長類研究所の窓辺にて。
アイプロジェクトのはじまり
チンパンジーが来るまでの1年間、ニホンザルの赤ん坊を自分で育てる研究をしました。サルがわかったと思い始めていたところに、1977年の秋、チンパンジーのアイがやってきました。その衝撃は大きかった。なんじゃこりゃ、これはサルじゃないぞというものが目の前に現れましたから。最初から目をじっと見てコミュニケーションができたのです。1978年4月15日にチンパンジーに言葉を教える研究、アイプロジェクトが始まりました。アイが初めてコンピュータの画面に触れて言葉の学習を始めたのです。室伏先生の「大型類人猿の人工言語習得とその脳内機構」という研究プロジェクトの一員として、実験を計画してきましたが、言語によるコミュニケーションが可能なことはある程度わかっていたので、もっと科学的な方法でチンパンジーの認識の研究をしようと考えました。言語をメディアとして、チンパンジーが見ている世界を知ろうとしたのです。それまでの研究では、彼らが言語を覚えたり使ったりする行動を言語的に説明していましたが、僕は人間とチンパンジーで同じ装置を使い、同じ測定方法を使って、人間とチンパンジーの知覚や認知の比較研究をすることにしました。比較認知科学というのは、僕がこのアイプロジェクトで初めて使った言葉です。手話研究はすでに行われているので、そうではない方法を考えるべきなのですから。お手本があるわけではないので、日々を積み重ねていく中で、毎日新しいチンパンジーの側面が少しずつわかってきました。まず手がけたのは、色の認識です。チンパンジーがヒトと同じ赤、緑、青の三原色をとらえていることは、生理的なレベルではわかっていましたが、どう見えているのかはチンパンジーに聞いてみるしかないわけでしょ。使ったのは図形文字で、色に相当する文字と色の組み合わせを教えました。赤い色紙を見せて、赤という文字を選べば正解です。こうしてアイは、十一色の色とそれを表す図形文字を選べるようになりました。同じことを大学院生にもやってもらいます。二百種類以上の色を見せて、何色に見えるかを聞く実験では、青緑のような境界の色でヒトもチンパンジーも同じように迷います。その結果を比べるとチンパンジーとヒトと色の認識が、ほぼ同じことがわかりました。これは日本人が日本語で表す色の見え方ですが、バーリンブレント・バーリン米国ジョージア大学の文化人類学者。
世界の言語の色を表す言葉と実際の色の関係を研究し、文化人類学的視点から色彩基本語の進化に関する説を打ち立てた。とケイポール・ケイ米国カリフォルニア大学の言語学者。が文化人類学の研究で、言語によって多少の違いはあるものの赤なら赤、緑なら緑の範囲は人類共通であることを見つけています。ですから、僕の研究の結果、ヒトとチンパンジーが見ている色の世界は同じと言えたのです。この研究の中で、面白いことに気づきました。アイは、赤色を見せて赤という文字を選ぶことができるのに、赤という文字を見せて赤色を選ぶことがすぐにはできなかったんです。今では訓練を積んでいるので、色も図形文字もさらには漢字も等価であると認識していますが、チンパンジーや他の動物では赤を示す文字を教えても、その文字が赤と等価であるということがすぐにはわからない。ヒトは教えなくても赤という文字を覚えれば、それが赤と結びつきます。つまりこれが人間の言語に特有のことなのです。チンパンジーの研究をすることで人間の特徴が浮かびあがってきました。色の次に教えたのは数です。アイは図形文字の学習を終えた時、五歳になっていました。4個の積み木を見せて、数字の4を選べば正解というように教えて、具体的なものをいろいろ見せてその数を1から6まで正確に選ぶことができるようになったんです。1985年にこの結果をネイチャーに発表し、アイは数を数えるチンパンジーとして一躍有名になりました。それまで誰もチンパンジーが数字を使って数の概念を表せると思っていなかったから、これはインパクトがありました。論文のタイトルは、Use of numbers by a chimpanzee.つまり、アイという一人のチンパンジーができたことでチンパンジーには数がわかると言ったのです。アイを通じてチンパンジーの普遍的な知性を引き出していることを証明するという研究がここで実を結びました。

色の勉強をするアイ。(2012年1月撮影)

ご褒美のリンゴを用意する。正解すると1片与える。(2012年1月撮影)


1984年日本山岳会のカンチェンジュンガ縦走では主峰隊チームリーダーを務め8350mまで登った。この後ヒマラヤ登山では、2回登頂を果たした。
アフリカで野生チンパンジーに会う
論文が出て間もなく、サバティカルサバティカル主に欧米の大学・研究所で取り入れられている半年から1年程度の有給休暇。でアメリカのペンシルバニア大学のデイビット・プレマックさんのところに留学しました。チンパンジーのサラに言語を教え、「心の理論」の研究をされた先生です。プレマックさんと議論をするうちに、研究のオリジナリティを強く意識するようになりました。一人のチンパンジーがコンピュータの前に向かっていることからわかる知性を追求するという研究は、オリジナルなものでしたが、この知性は本来チンパンジーの社会の中で発揮されるものだと気づきました。それでアメリカ東部からすぐのアフリカ西海岸に行って野生のチンパンジーを見ることにしたんです。すでに霊長類研究所の先輩の杉山幸丸さんがギニアのボッソウ村に開拓したフィールドがあったので、そこを訪ねたのですが、着いて早々杉山さんがマラリアに罹って帰国することになって、一人でアフリカに取り残されました。山岳部でフィールドワークを叩き込まれていましたので、どんなところでも大丈夫という自信はあったのですが、初めてのアフリカですからさすがに少し心細かったですよ。これをきっかけに、フィールドと実験室両方を見るようになりました。野生のチンパンジーの研究ならジェーン・グドールさんに敵わないけれど、グドールさんはコンピュータの前に座ったチンパンジーは見ません。実験室の研究ならプレマックさんの方が優れていると思うけれど、彼はアフリカには行きません。しかしこの両方を見れば、新しい誰もやっていない研究ができると考えたんです。僕の研究はそれなしでは世界が回らないという種類の研究ではないけれど、ほかの誰もやっていないという点でとても重要なものだという自負があります。
毎年十二月から一月の乾期にアフリカに行って、ボッソウの野生チンパンジーの調査をしていますが、ここでは道具の使用に目をつけました。ヒトの特徴は道具を使うことだと言われますが、ここのチンパンジーは台となる石の上に置いたアブラヤシの種をもう一つの石をハンマーに使って割りその中の核を食べます。なんでもないと思われるかもしれませんが、台、ハンマー、種と3つを操る訳ですからこれは石器とも呼べる高度な道具利用です。最初は彼らが石器を使っている場所を探して観察をしていましたが、その場を捉えるのは難しい。そこで、さまざまな予備調査後に、1988年に野外実験を始めました。石器を使うお膳立てをした場所を用意し、見通しのいい離れた所にフェンスを作ってビデオカメラを設定し、観察するのです。「野外実験」と称しています。それが上手くいって道具を使う様子がビデオで撮れたので、以来ずっとその様子を記録し、研究しています。例えば、チンパンジーに利き手があるということは、同じ場所で、同じ個体や同じ親子を何度も観察してようやくわかってきますよね。子どもがいつどうやって道具利用を学習するかも同じです。そこでわかったのがチンパンジーは「教えない教育・見習う学習」だということ。子どもはじっと見ていて大人の真似をするけれども、大人は手を取って教えたり、できたからといって褒めたりはしません。子どもはただ大人のすることを真似しているうちにだんだんできるようになる。個人差はありますが、アブラヤシの種割りはだいたい三、四歳でできるようになり、その頃に学ばないともう学習できない。チンパンジーの場合は、女性が年頃になると生まれた群れを離れて、別な群れに入ってそこで子どもを産みますが、生まれた群れが道具を使わない群れだと、入った群れが道具を使う文化を持っていてももう覚えられないんです。でも、その子どもは母親ができなくても、他の大人を見てちゃんと使えるようになる。「教えない教育・見習う学習」のいいところです。こういうこともたくさんの例を検証することで、正しく解釈できます。たまたま観察したのではなく、観察を繰り返すうちに行動を予測できるようになるので、実験を組み立て、確認することで対象が理解できる。一般的には実験室で実験、野外で観察という方法をとりますが、僕はフィールドでも実験をし、実験室でも観察するんです。この組み合わせで、統合的な理解ができると思っているんです。
Scientist Library:
季刊 生命誌 31号
「サルの森にて 自然の秘密を探り出す」
杉山幸丸

ギニアボッソウで野外観察をはじめた。研究所には各国の研究者がいる。

イタリアで開催された会議で、海外の霊長類研究者とともに。(本人:左端)

チンパンジーと暮らすボッソウ村のマノン人ガイドたち。

2011年ギニアのボッソウで道具を使う野生のチンパンジーたちと。
チンパンジーの本来の知性を探して
アメリカから帰ってきて取り組んだのが、どうやって実験室のチンパンジーをより本来の姿に近い形で研究する環境をつくるかです。アイはまだ日本がワシントン条約ワシントン条約絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
絶滅のおそれのある動植物の取引規制することで保護を図る。日本は1980年に締結国となった。を批准する前に一歳の子どもで親から離されて輸入されました。でもそれは本来のチンパンジーの暮らしからかけ離れているんです。チンパンジーの子どもは五歳くらいまでお母さんに抱かれて育てられます。僕も自分の子どもが赤ん坊のときに、育児放棄したチンパンジーの子を一緒に育てましたが、やってみてすぐに気がつくのはフェアじゃないということ。うちの娘には親がいるけど、うちのチンパンジーにはいるべき親がいないのです。欧米では子どものチンパンジーを連れてきて研究するのは一般的ですが、親から無理矢理引き離し、チンパンジー本来の環境ではない暮らしにおいて、むりやり人間の環境に適応しようとしている様子を見るわけです。彼らはそれでも柔軟な知性を持っていますから期待通りかそれ以上の能力を示しますよ。でも僕が見たいのはそれではない。そういう柔軟な知性が彼らの本来の暮らしの中で、どう活かされているのか。柔軟な知性と呼ばれるものの中身なんです。そこで日本ならではの方法をと考えました。それが2000年から始めたアイとアユム親子達3組の親子プロジェクトです。協力とか思いやりとかいうことは人間でもとても大切ですよね。他者に手をさしのべる、思いやる、他者の心を測る。その中で親が子を慈しみ、子が親に信頼を寄せる。そうやって人間は育っていくわけでしょう。たった一人のチンパンジーを取り出してきて、人間の世界でコンピュータに向かっているのを見たところで、親子関係や協力関係のような関係や心の発達はわかりません。そういう当たり前のことに改めて一人の研究者として気づいたんです。一人のチンパンジーが育っていくためには、お父さんが必要、お母さんが必要、仲間が必要、そして仲間と一緒に住む森が必要なんです。そのモデルはアフリカの彼らが住む森にあります。それでアフリカに行き、彼らが森でどう暮らしているかを観察して、それを実験する環境に活かすことにしました。なぜなら野生の姿それだけ見ていても、引き出さないと見えてこない彼らの色の知覚、数の概念、記憶の世界があるので、コンピュータの場面もやはり重要だからです。それで両方を見るというオリジナルな研究スタイルができあがりました。それに加えて人工飼育の場をなるべく本来の姿に近い形にし、親子の研究を始めたのです。親子が日常に暮らしているところに参加して研究するのですが、研究者は母親とはすでに親しいので、母親を助手にする形にしました。「参与観察」法と呼んでいます。普段は仲間と普通にくらしており、「アイ、こっちにおいで」と言うと、アイが自分の自由意志でトコトコトコ歩いて勉強部屋までやってくる。勉強を終えると「じゃあね」といって帰っていく。息子のアユムと呼ぶとアユムがやってくる。ポポと言えばポポがくるというわけです。研究者とチンパンジーとが同じ場所で暮らしていく中で、相互の信頼関係が生まれているところで、できるだけまっとうなチンパンジーとしての生活を保証しつつ、我々は我々が知りたいと思っているチンパンジーの心の働きを調べます。そうでないと人間とチンパンジーを比較することはできないでしょう。
アイの子どもアユムは、2歳からコンピュータの前で問題を解くことを覚えました。お母さんがやっているとだいたい子ども達も同じようにコンピュータの前に座って勉強をはじめます。アユムは4歳の時には、同じ歳の子供たちやすでに学習のすんでいるアイ以外のお母さんたちと一緒に数字の学習をしました。チンパンジーの4歳は人間でいうと6歳くらいにあたりますから小学生になる頃です。アユムは数字を小さい順に選べるようになったので、これを利用して記憶能力を調べました。コンピュータ画面に出たいくつかの数字のうち、一番小さい数字を選ぶとそれ以外の数字が白い四角に置き換わります。記憶を頼りに置き換わる前の数字の小さい順に四角に触れたら正解というテストです。アユムは今では1から9までの9つの数字をたった0.5秒見ただけで正しく答えます。人間ではとてもできないし、アイよりも優秀です。これこそ実験研究の白眉ですよね。手話の研究では、人間の使う言葉の能力の一部分がチンパンジーにもあるという二分法の見方しかできませんでした。チンパンジーの記憶研究のすばらしさは、あきらかに人間の大人でもできないことをチンパンジーのそれも子どもができるということを証明したことです。身体能力ではなくて、認知的な課題の瞬時記憶において、チンパンジーの方が人間より優れている。それを万人が認めざるえない形で提供したのです。人間と動物という二分法が間違っていて、人間は動物の一つでしかないのですから、人間に得意な分野がある一方で、チンパンジーの方が得意な分野がある。ゲノム的な人間観が現れているのです。ゲノムは目に見えないけれど、心の研究は実際に見て経験できるところが面白いのです。

中山賞授賞式。伊谷純一郎先生、西田利貞先生、日高敏隆先生など錚々たる顔ぶれが揃った。(本人:前列右から4人目)

アフリカの森により近い環境をつくる試みは現在も続けている。

アイとアユムがコンピュータにむかってそれぞれ自分の課題に取り組む。(2012年1月撮影)

京都大学霊長類研究所で指導する大学院生たちと、アメリカ霊長類学会に参加したホテルで。
見えてきた人間の心
チンパンジーには一瞬でこの世界を読み解くすばらしい記憶力があります。それが分かると我々人間には、そうした記憶力はないけれど、ぱっと見たものの向こう側にあるもの、あるいはぱっと見た景色の中に入ってこないものに思いをはせることができるということに気づきます。チンパンジーは画材を与えるとご褒美がなくても思い思いに絵を描きます。殴り書きのようではあるけれど、タッチや色使いに個性が見られます。でも決して具体的なものは描かないことが分かりました。ただ描かれたものをなぞりはするので、チンパンジーの顔を予め描いておいた紙を与えてみたんです。当時大学院生の齋藤亜矢さんが考えた検査です。輪郭だけとか、片目がない、両目がないなど変化をつけると、チンパンジーはみんなその通りをなぞります。人間の場合、2歳児くらいまではチンパンジーと大差ないのですが、3歳児になるとほぼ全員が描かれていない目を書き足します。「おめめがない」ことに気がついて。これってすごいですよね。人間は時間と空間を超えて目の前にないことを考えられるんです。人間とは何かという問いに、チンパンジーを通じて向き合い、人間には想像するちからがある、という答えを見つけました。個別の研究の答えだけを求めるのでなく、チンパンジーの社会を丸ごと作り上げることを目指してやってきた背景があるからこそ得られた答だと考えています。明らかに今の生命科学、生物科学の還元主義とは逆の方向です。全体主義と言ったらよいかな。若い頃に最初に哲学を志し、世界がどんな風に見えているかと考えたとき、世界がどうであれ見ているのは「私」なのだと思いました。世界の森羅万象は自分の目を通して見えるのであり、全部自分の中に畳み込まれていると考えたのです。つまり世界の理解を個に還元できると思った。そこで最初は一人のチンパンジーの見ている世界から普遍的なチンパンジーの知性が引き出せると考えてアイプロジェクトを始めました。一般的には、人間の心は脳にあると考えて、脳は神経細胞に還元できて、更には遺伝子や神経伝達物質に還元していますね。それで理解できると思っている。でも心は社会の中で働くものだし、文化という背景があって働くのです。心が働く環境が、どのようなものか、それが行動を決めているのであって、脳が決めているわけではないでしょう。だから社会の中でどう心が働くかを見るのが正しいはずだ、という強い自信を持っていまは研究を進めています。

2010年9月、ジェーン・グドール博士と旅の友のミスターHと一緒に。

グドール博士(左)、マルチネス博士と。背景は伊谷純一郎先生のフィールドノートの展示。

チンパンジーと人間の子どもの違い。人間には無いものを想像するちからがある。
未来にむけて
チンパンジーで研究をさせてもらっているからには、日本で飼育されているチンパンジーの福祉と、野生のチンパンジーの保全を考えないわけにはいきません。霊長類研究所でも豊かな環境づくりを進めてきましたが、国内にいる335人のチンパンジーがすべて幸せになるように努力しています。明日からアフリカに調査に行きますが、ボッソウも深刻です。ボッソウの野生チンパンジーの群れには最近外から女性が入ってきていないので、少子高齢化が進んでいます。そこでその東にあるニンバ山にいるチンパンジーとの交流を期待して、サバンナに木を植えてボッソウとニンバ山の間に森をつくる「緑の回廊」プロジェクトを1997年から進めています。三百メートルの幅で四キロにわたる緑地帯を作ろうという計画なのですが、植えても定着するのは四分の1ですし、野火で焼けてしまうこともあるんです。さらにニンバ山は世界自然遺産のはずですが、鉄鉱石の塊なので先進国の巨大資本がよってたかって鉄の露天掘りを始めようとしています。それをどうやって止めるのか、本当に頭を痛めています。僕がやるべきことは、チンパンジーの研究者として認められる研究を続けること、アフリカに出かけては木を植えてくることだと思っています。研究者はカメレオンの目をもつことが必要だと思っているんですよ。それぞれ違う方向をみること、それも近くを凝視する目と広く周辺を見回す目を持つことです。別の言い方をすると、百メートルも速いけどマラソンも得意という人である必要があります。それには健康でいることと、毎日続けること。僕が目指すのは、やはり山岳部で学んだ初登頂の精神、パイオニアワークです。それを実現するにはなんでもできて、完全にできることが大事です。徹底した完全主義でとても現実にはあり得ないけれど、こういう矛盾したものこそ目指すべきだと思っています。チンパンジーと同じ「教えない教育、見習う学習」を目指しています。だから口では言わないけれど、若い研究者にそれを目指してほしいと思っています。すばらしいものを実際に見て自分で自分を直していくこと、そのためには自己管理と自分を客観的に理解することが必要です。僕は十七歳の夏に一念発起して毎日自己点検ノートをつけているんですよ。「お父さん変だよ」と娘に言われますが、人間を知るにはまず自分から、ではないでしょうか。

アイとはもう34年のつきあいになる。

「想像するちから」で毎日出版文化賞を受賞。授賞式で研究所のメンバーと一緒に。(本人:後列左から5番目)

研究所で還暦のお祝い。赤いちゃんちゃんこが本人。

高校生から続けている自己点検ノート。1行が1日の生活を表す。