詳細
日時
2025/9/6(土) 14:00-16:00
場所
JT生命誌研究館およびYouTubeライブ配信
出演者
近藤 滋(国立遺伝学研究所 所長)
永田 和宏(JT生命誌研究館 館長)
主催
JT生命誌研究館
参加方法
参加無料・予約不要
【現地参加】直接会場へお越しください。
【オンライン】本ページよりライブ配信を行います。
内容
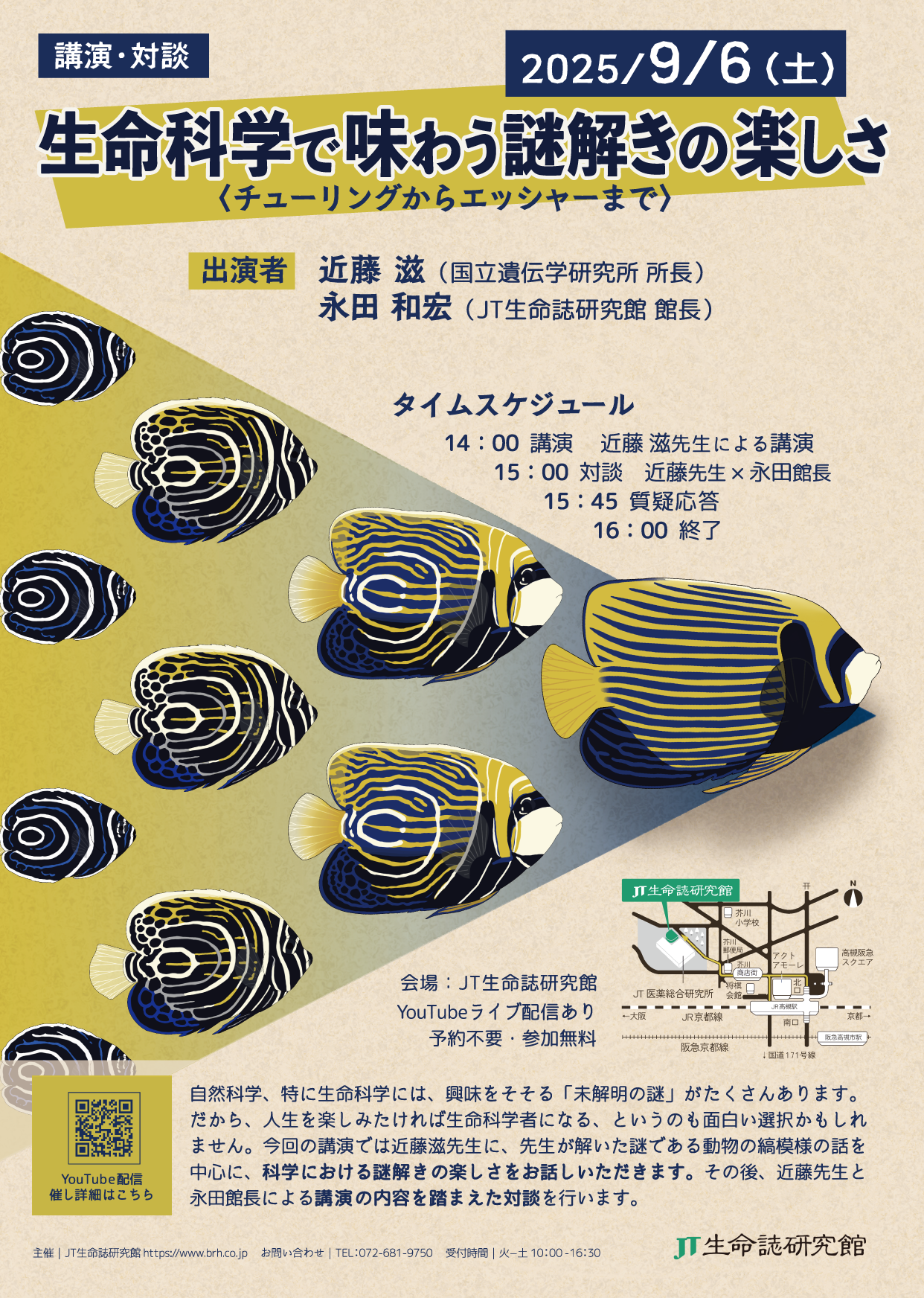
今回の生命誌の催しでは、発生学・
講演趣旨
知的な遊びには謎解きのプロセスが含まれます。プログラム
| 14:00 | 講演 近藤滋先生による講演 |
| 15:00 | 対談 近藤先生×永田館長 |
| 15:45 | 質疑応答 |
| 16:00 | 終了 |
開催記録
講演の記録映像配信中!
こちらの講演の後に行われた永田館長と近藤先生の対談は
季刊「生命誌」123号(12月発行)の記事として公開予定です。
館内の催しについて
研究のお話を聞いたり、実験を体験したり、生きものを観察したり、研究員と直接語り合ったり、子供から大人までどなたにも驚きと発見が待っています。参加無料です。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)