検索結果を表示しています。(824 件の記事が該当しました)
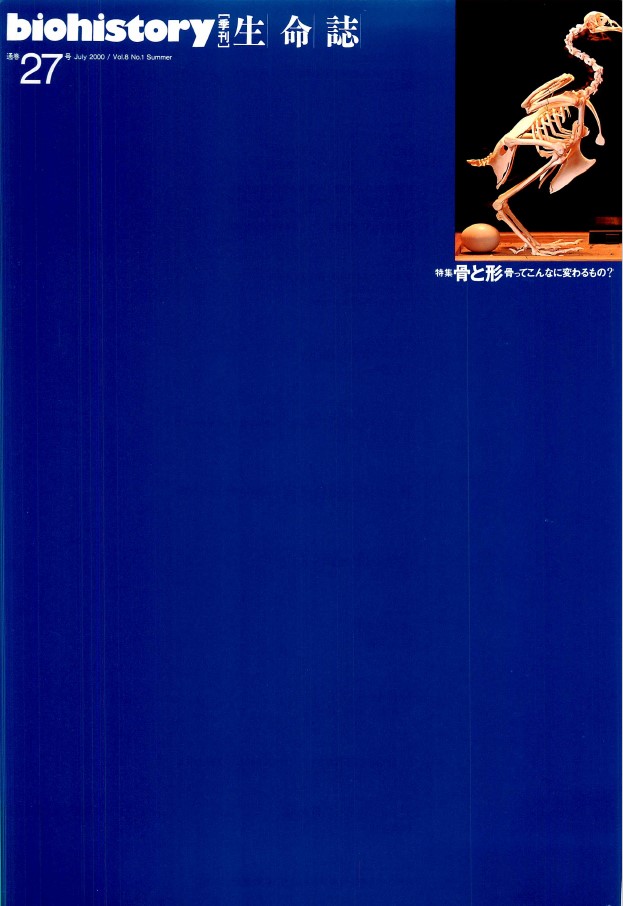
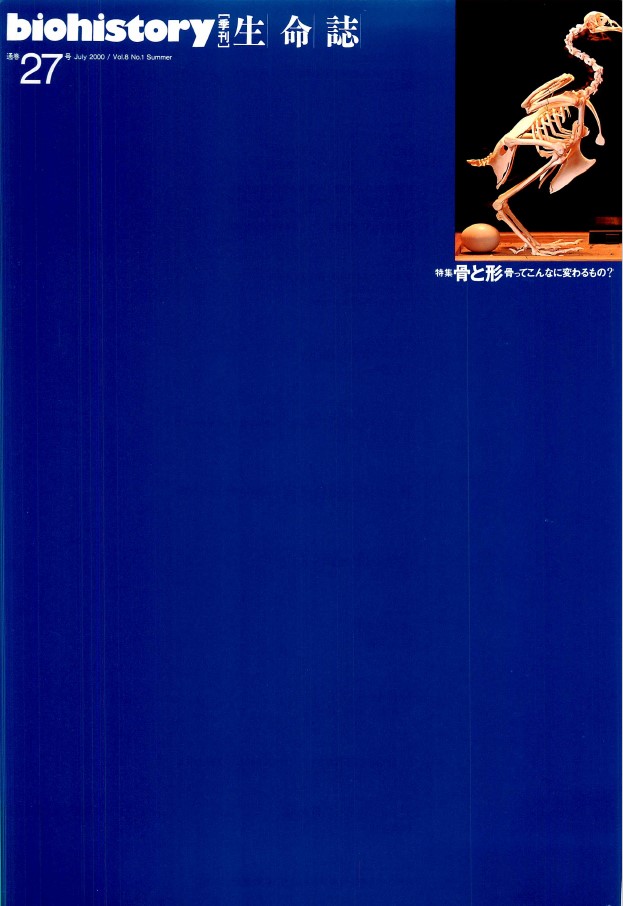
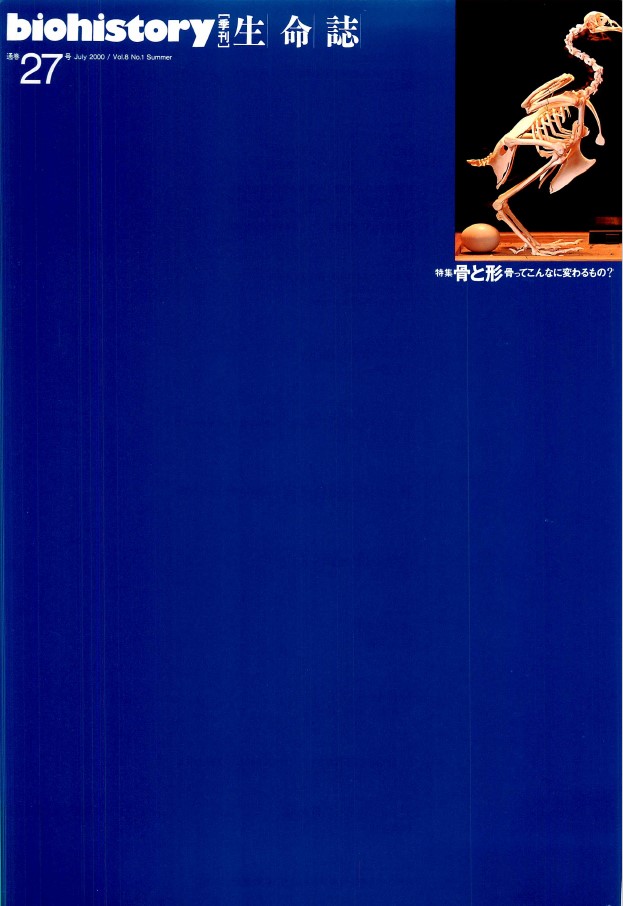
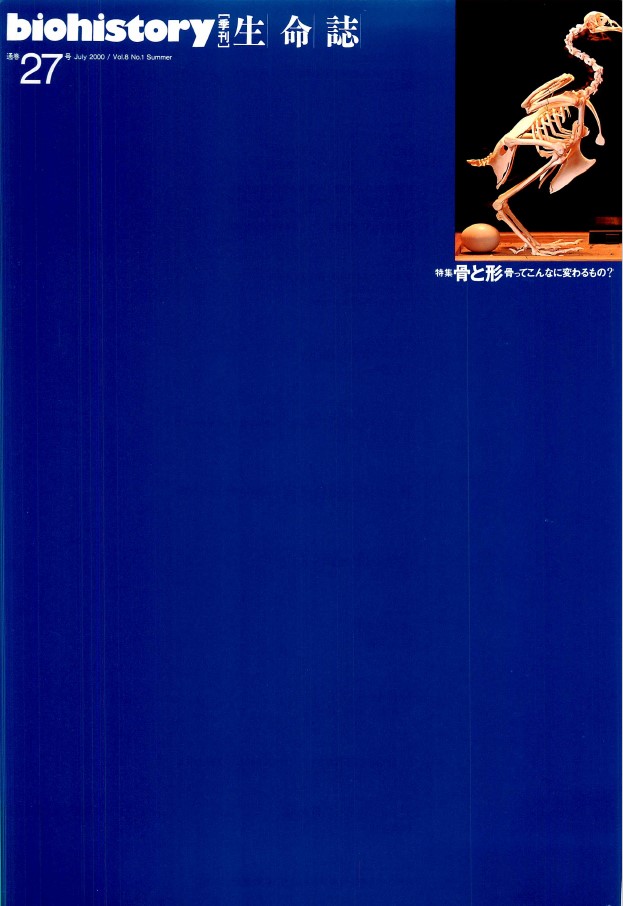
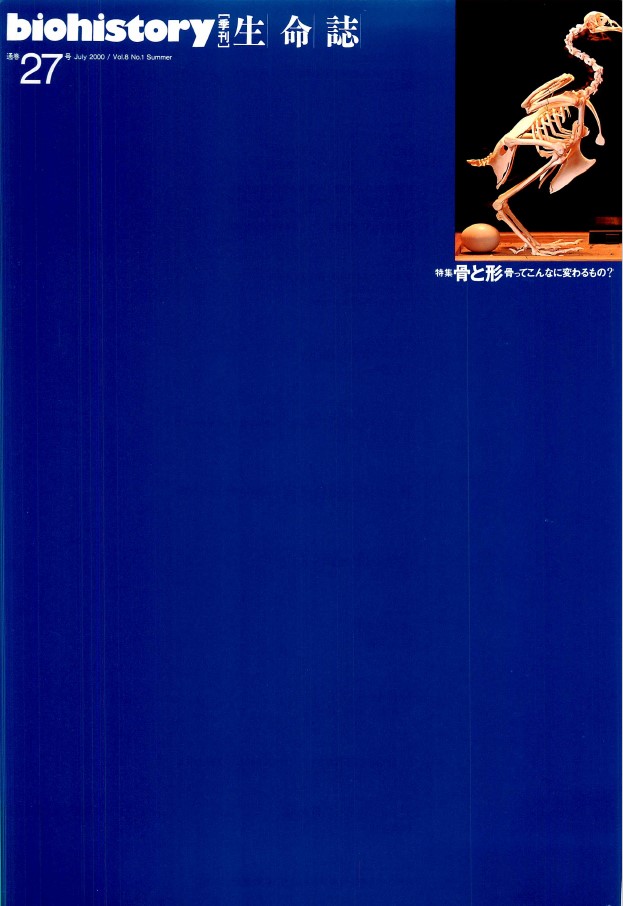
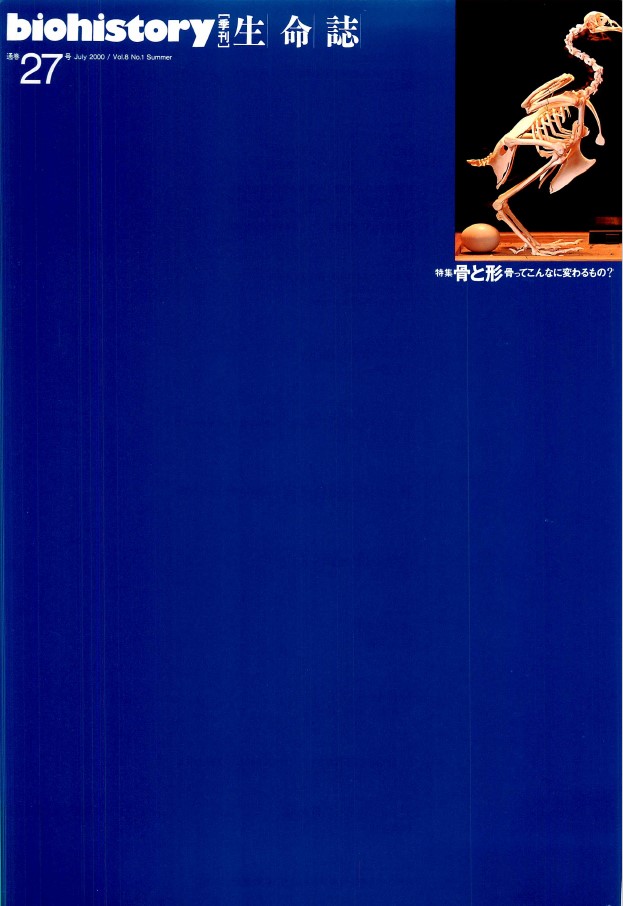
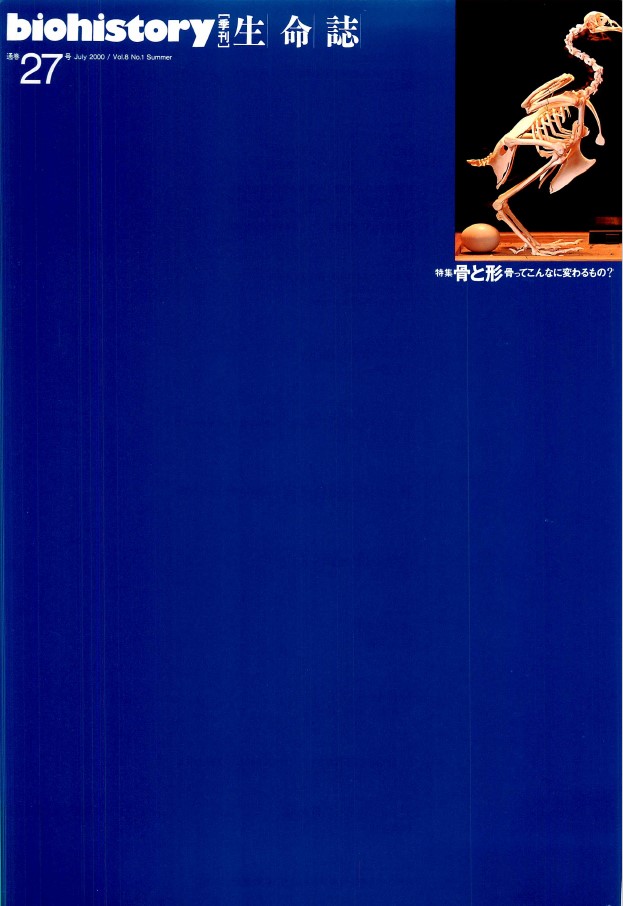
Art
薄様の膜を透かして
伊部京子
1941年名古屋市生まれ。67年京都工芸繊維大学大学院修士課程修了、現同大学非常勤講師。和紙造形作家。82年(株)シオン設立、代表取締役。93年京都府文化功労賞受賞。98、99年SOFA Show(シカゴ)、2000年個展(東京、富士市、スコッツデールコンテンポラリーアートミュージアム)、University of Utah(アメリカ)客員教授など、国内外で、グループ展、アート・インスタレーション、講演多数。
キーワード
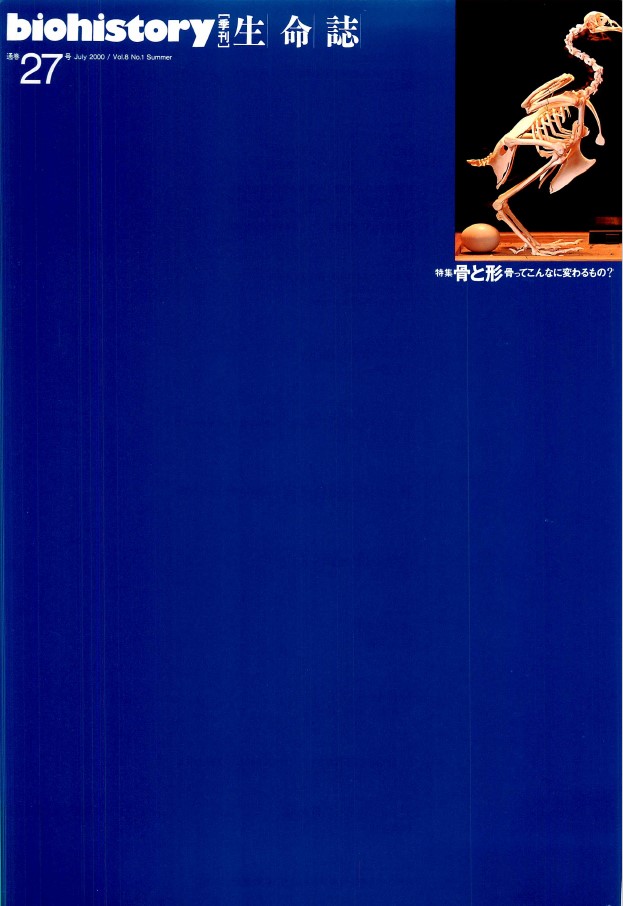
TALK
身体をとりもどす
三浦雅士
1946年生まれ。70年代に『ユリイカ』『現代思想』編集長として活動。80年代に評論活動に入り,舞踏への関心を深めていく。現在,『ダンスマガジン』『大航海』編集長。主要著書に『私という現象』『主体の変容』『メランコリーの水脈』『身体の零度』『小説という植民地』『考える身体』などがある。
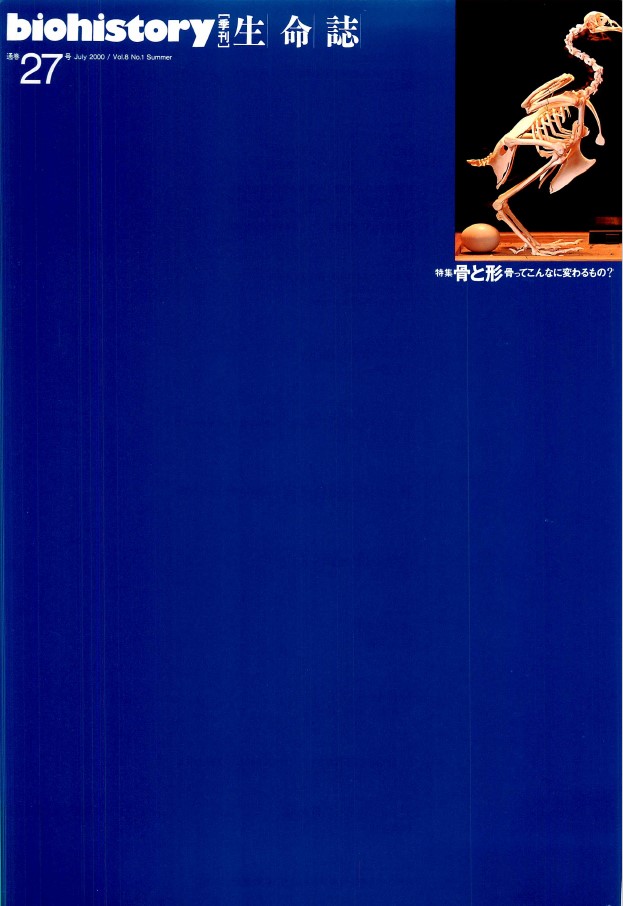
SCIENTIST LIBRARY
未知に挑戦する私の脳
伊藤正男
1928年愛知県生まれ。53年東京大学医学部卒業。熊本大学医学部助手、東大医学部助手、助教授を経て、70年同教授。89年理化学研究所国際フロンティア研究システムに移り、97年より同研究所脳科学研究センター所長。東京大学名誉教授。日本学士院会員、王立スウェーデン科学アカデミー外国人会員、英国王立協会(ロイヤルソサエティ)外国人会員、ロシア科学アカデミー外国人会員、フランス科学アカデミー外国人会員として、世界を舞台に活躍。小脳の研究で有名だが、常に新しいことを求めないではいられないそのパーソナリティは、「大脳的」。
キーワード
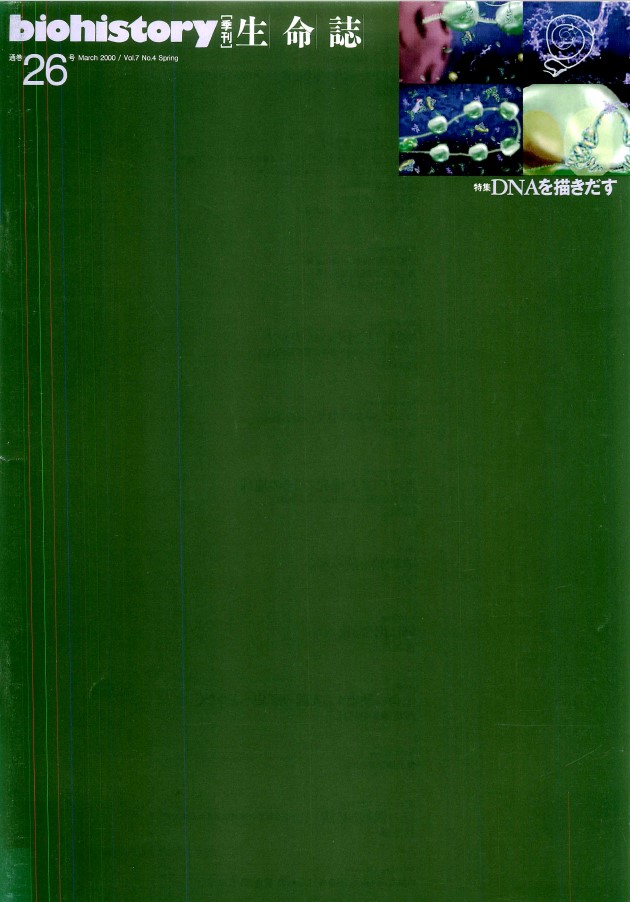
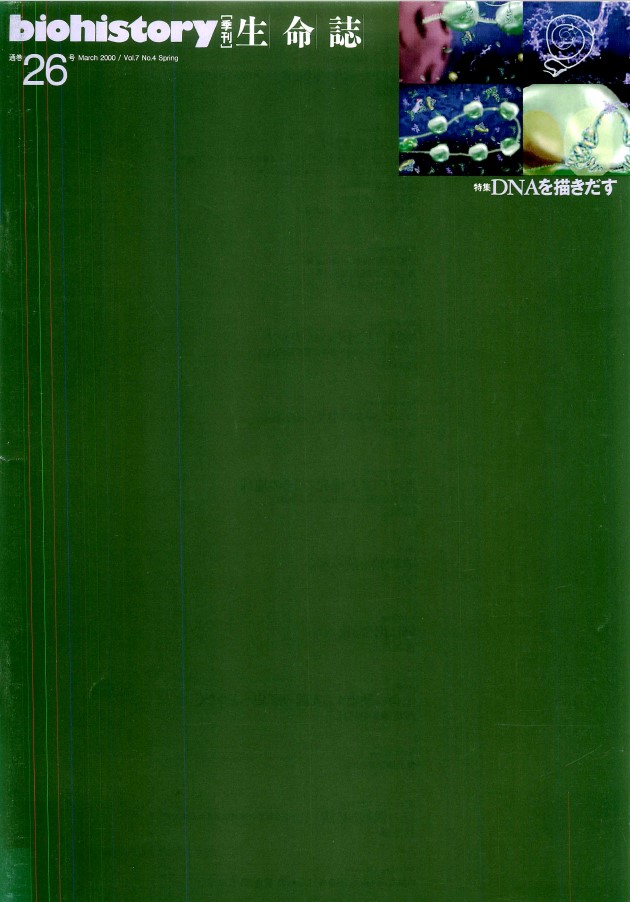
Special Story
正確に研究を表現したい ─ 意味のある絵をつなぐ
工藤光子
生命誌研究館は"科学のコンサートホール"。今回は、映像を使ってDNAの構造と働きの一部を"演奏"することにチャレンジしました。まだまだ演奏は手探りですが、舞台裏にはそんな私達を支えてくれた多くの人たちの協力がありました。 「コンピュータグラフィックス DNAって何?」ができあがった過程を皆さんも一緒にたどってみてください。
キーワード
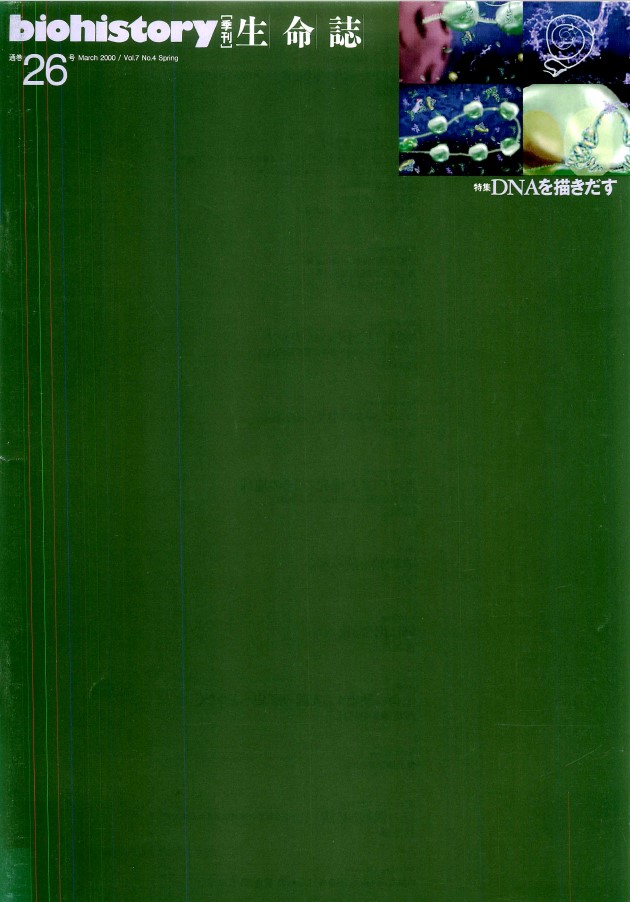
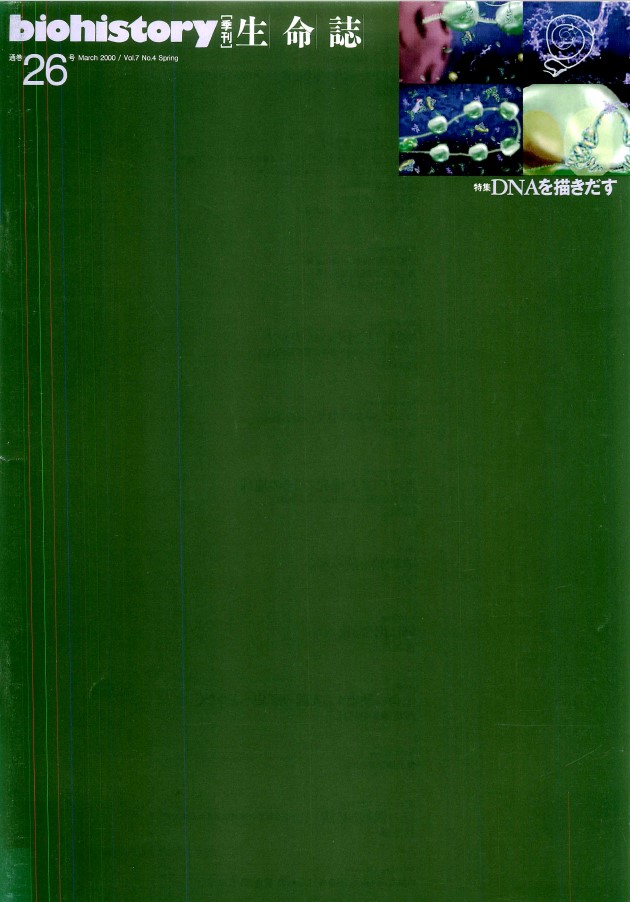
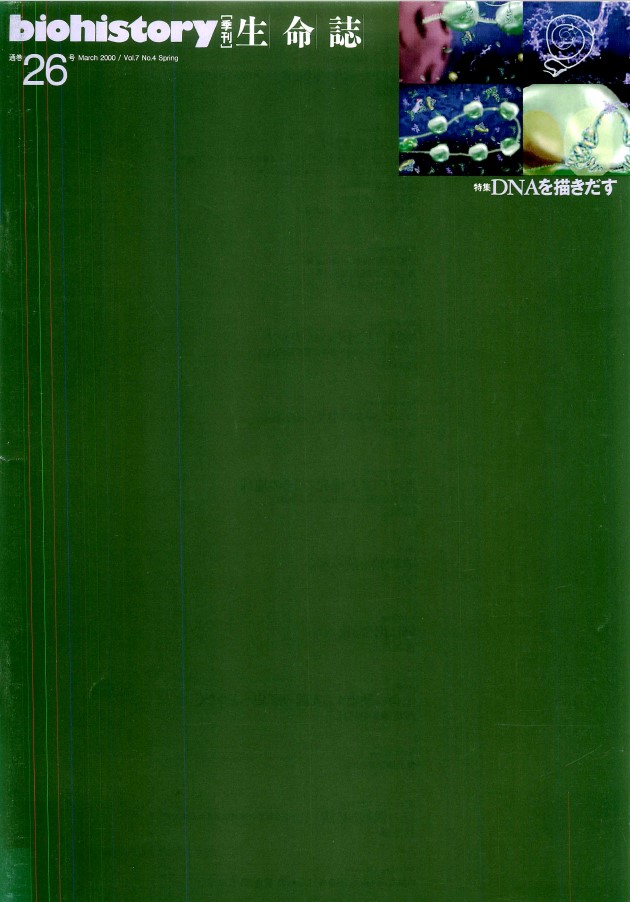
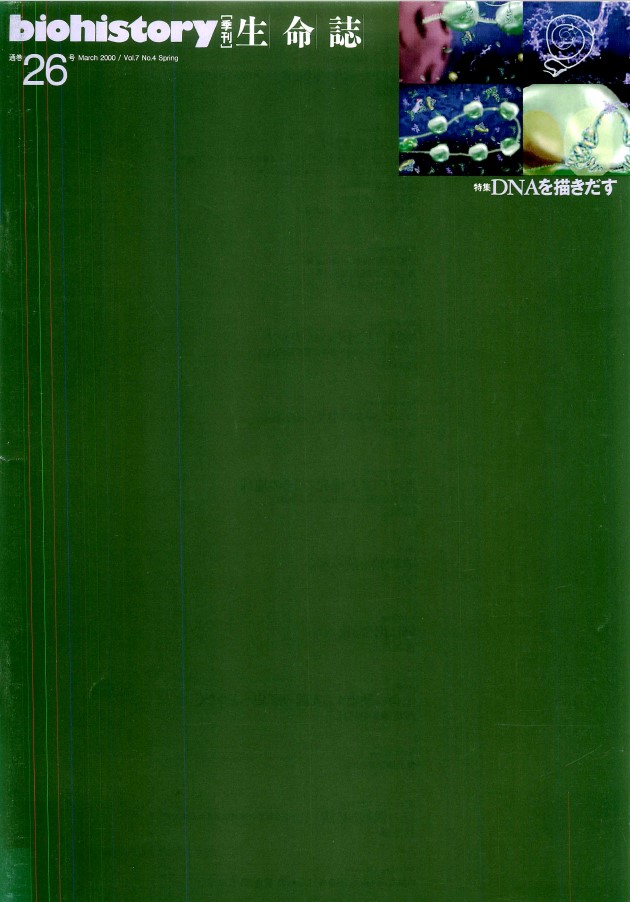
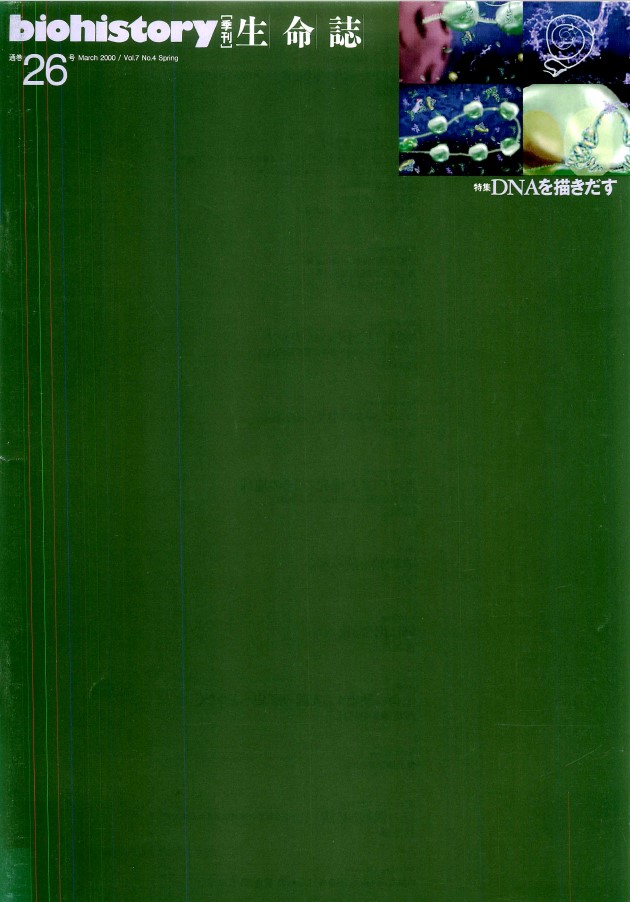
BRH Scope
生物はどこまでわかったか?-システムとしての細胞・個体の理解を目指して
加藤和人
20世紀後半,飛躍的な発展を遂げた生物学。
ゲノムプロジェクトをはじめ,大量の情報が驚くべき速さで蓄積しています。
その勢いで,生物はすべて理解できてしまうのでしょうか。「21世紀は生命科学の時代」と盛んに言われますが,その中味はいったいどんなもの?
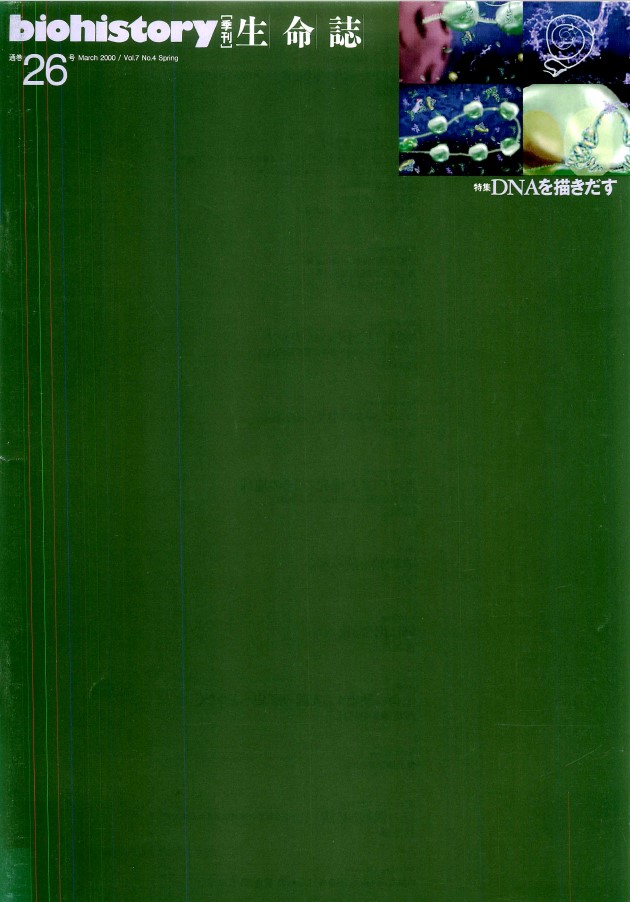
Experiment
コンピュータの中でつくる細胞
冨田 勝
1957年東京都生まれ。81年慶應義塾大学工学部数理工学科卒業後,米国カーネギーメロン大学に留学し, Ph. D:(情報科学)を取得。その後,同大学助手,助教授,準教授,同大学自動翻訳研究所副所長を経て,現在慶應義塾大学環境情報学部教授。同大学医学部教授も兼任。88年,米国立科学財団大統領奨励賞受賞。94年,工学博士(電気工学)取得。生命の不思議に魅せられ98年には医学博士(分子生物学)を取得。「サイエンスアイ」(NHK)レギュラーコメンテーター。
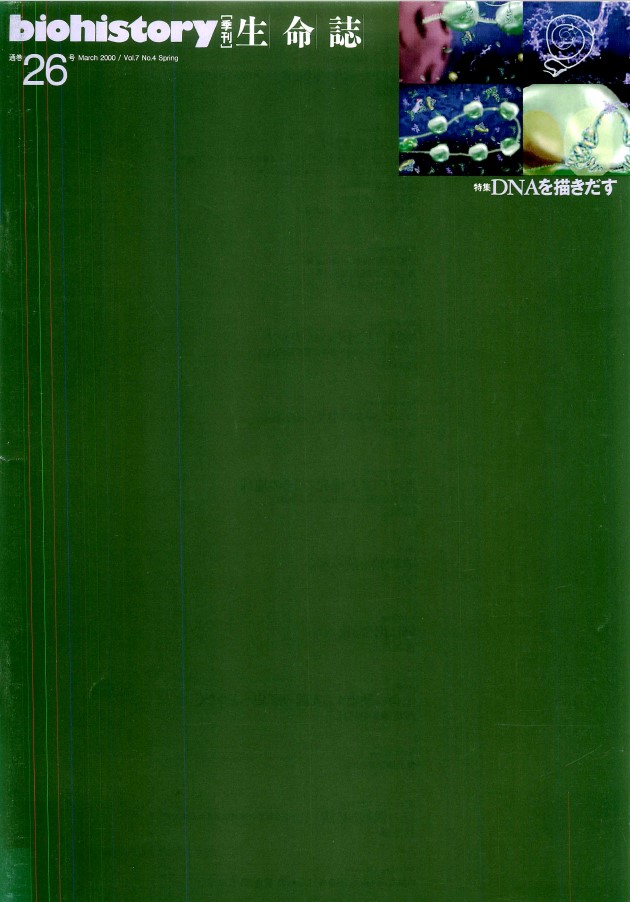
Experiment
カンブリア大爆発のころの地球 地質学と地球化学が描きだす生物進化
松本 良
1947年東京都生まれ。70年東京大学理学部地学科卒業後、同大学助手、助教授を経て、現在東京大学大学院理学系研究科教授。87年から1年間カナダ・ダルハウジー大学に留学。堆積学をを専門とし、イランや中国、カナダなど世界各地を飛び回り、カンブリア紀の地球環境から生物の変遷の歴史を描き出そうとしている。著書に『メタンハイドレード 21世紀の巨大天然ガス資源』(日経サイエンス社)などがある。
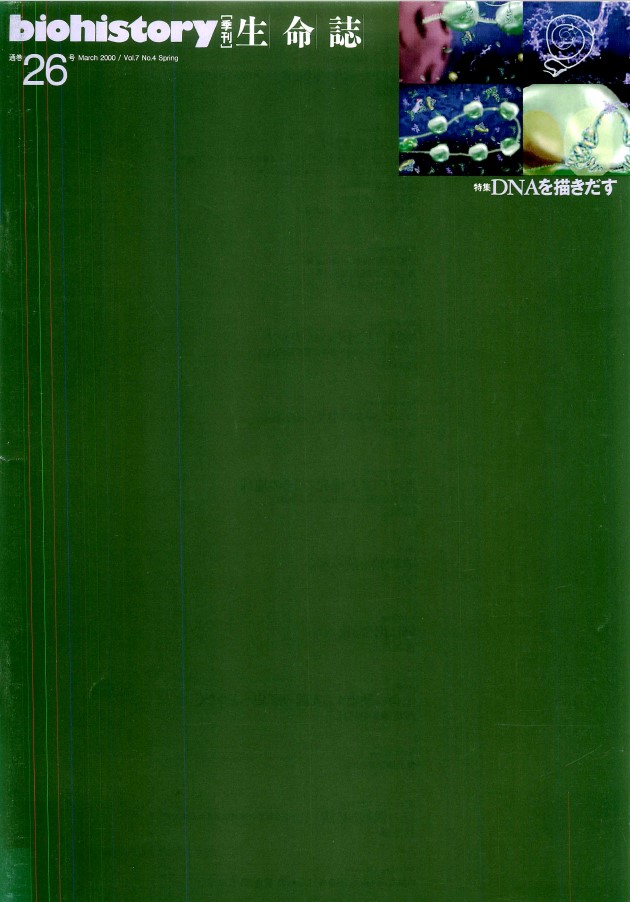
TALK
生命の歴史から人間の歴史へとつなぐ
西垣通
1948年東京都生まれ。東京大学工学部計数工学科卒業。日立製作所でコンピュータ・ソフトの研究開発に携わった後,明治大学教授等を経て,現在東京大学社会科学研究所教授。専門は情報工学・情報社会論。主な著書に『マルチメディア』(岩波新書)『デジタル・ナルシス』(岩浪書店)『思考機械』(ちくま学芸文庫)などがある。
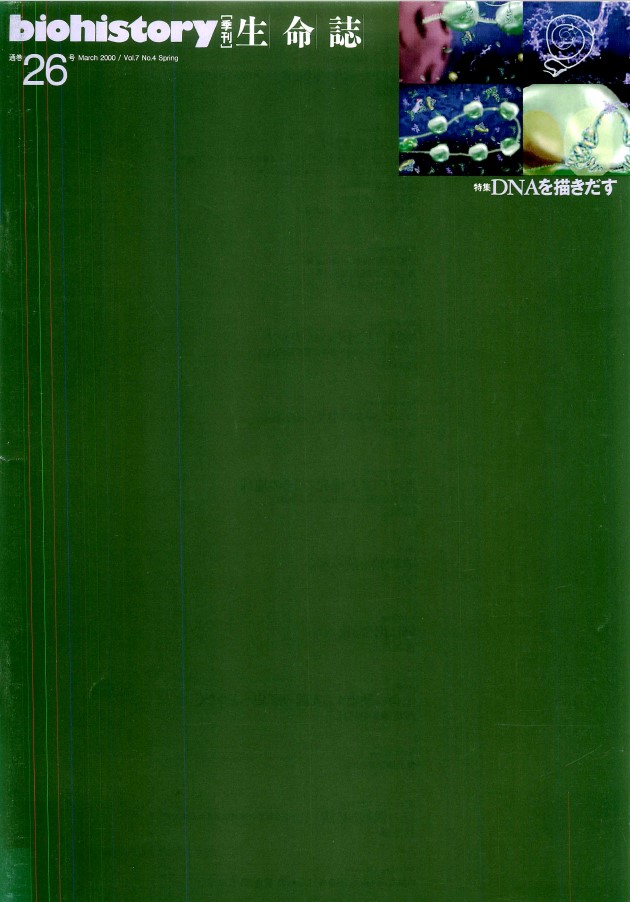
SCIENTIST LIBRARY
私の偶然と必然
松原謙一
1934年、東京生まれ。東京大学大学院化学系研究科博士課程修了。61年、金沢大学医学部助手を経て、64年、九州大学医学部助手。同年、米・ハーバード大学生物学教室研究員。67年、米・スタンフォード大学医学部生化学研究員。68年、九州大学医学部助教授。75年、大阪大学医学部教授、78年、同分子遺伝学研究施設長、82年、同細胞工学センター教授、87年、同センター長、98年より奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授及び財団法人国際高等研究所副所長。いつも穏やかで優雅という定評だが、「テニスに本当の性格が出る」と本人の弁。
-
2025年
地球というわたしたち

-
2024年
あなたがいて「わたし」がいる
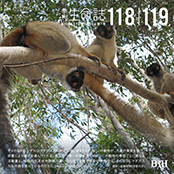
-
2023年
生きものの時間2
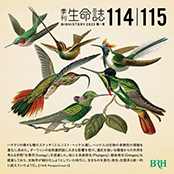
-
2022年
生きものの時間
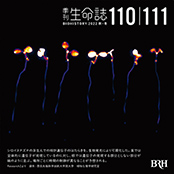
-
2021年
自然に開かれた窓を通して
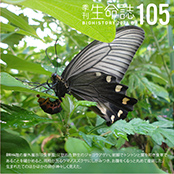
-
2020年
生きもののつながりの中の人間
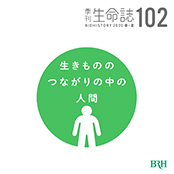
-
2019年
わたしの今いるところ、そしてこれから
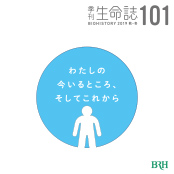
-
2018年
容いれる・ゆるす
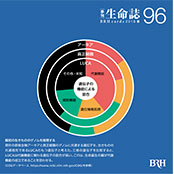
-
2017年
和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-
2016年
ゆらぐ
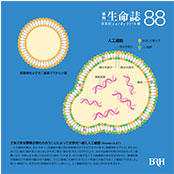
-
2015年
つむぐ

-
2014年
うつる
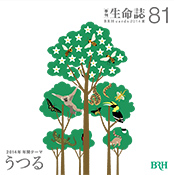
-
2013年
ひらく

-
2012年
変わる
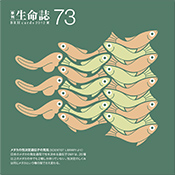
-
2011年
遊ぶ

-
2010年
編む
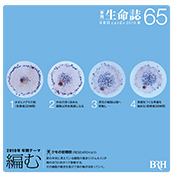
-
2009年
めぐる

-
2008年
続く

-
2007年
生る
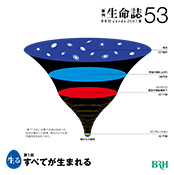
-
2006年
関わる

-
2005年
観る
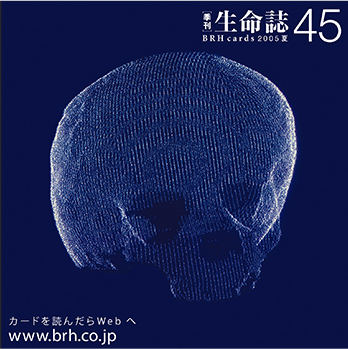
-
2004年
「語る」 「語る科学」

-
2003年
「愛づる」 「時」

-
2002年
人間ってなに?
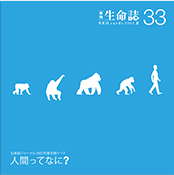
-
2001年
「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-
2000年
「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-
1999年
「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-
1998年
「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-
1997年
「花が咲くということ」ほか

-
1996年
「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-
1995年
「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-
1994年
「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-
1993年
「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、
多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。
さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。
-
![]()
動詞で考える生命誌
生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。
- PC閲覧専用コンテンツです。
-
![]()
生命誌の世界観
科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。
- PC閲覧専用コンテンツです。
-
![]()
生命研究のあゆみ
日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。
- PC閲覧専用コンテンツです。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)




