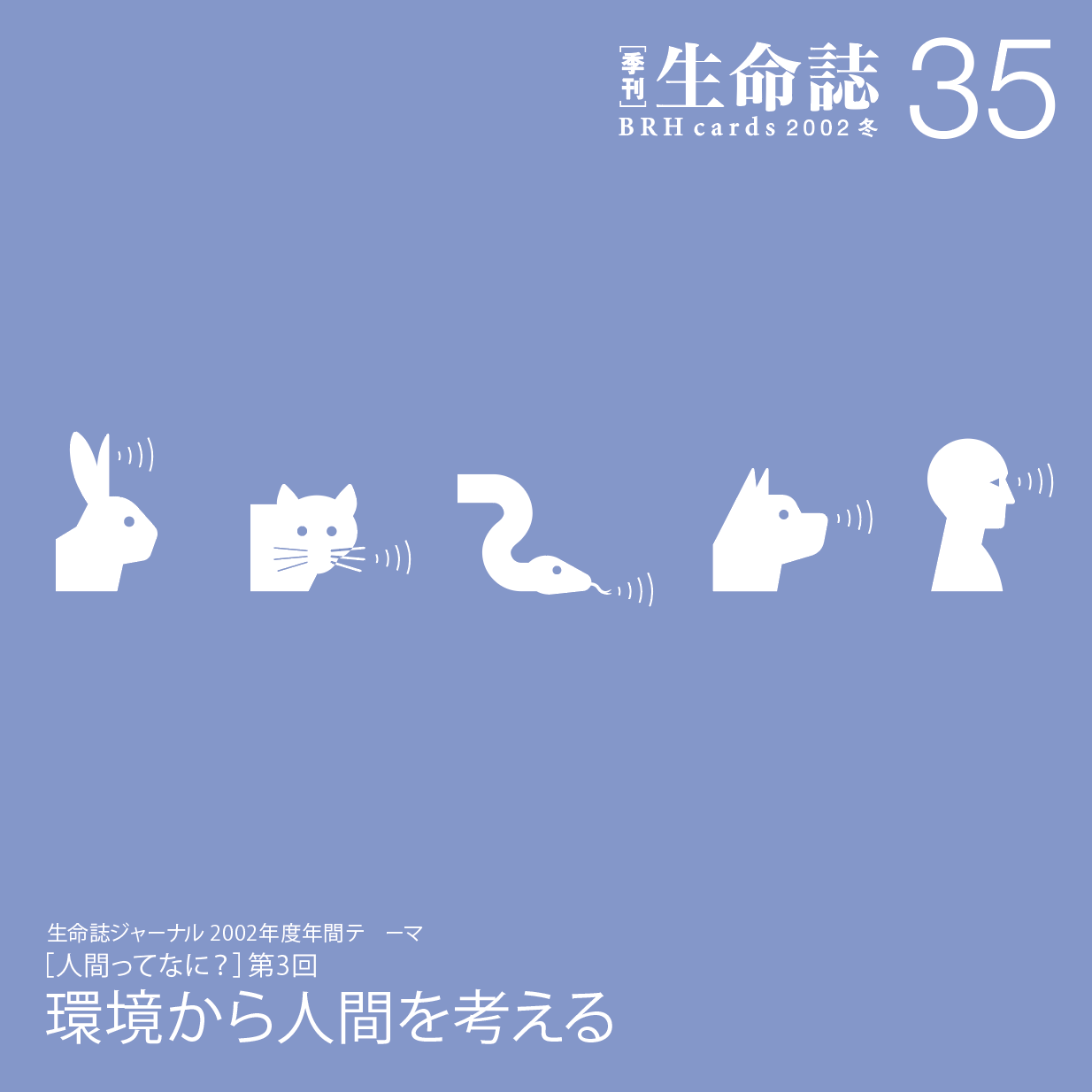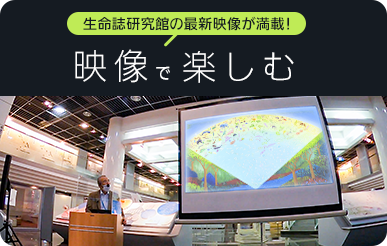検索結果を表示しています。(824 件の記事が該当しました)
.jpg)
SCIENTIST LIBRARY
免疫とアレルギーのしくみを探る ~常識に合わない現象には未知の真実がある
石坂公成
1925 年、東京都生まれ。
48 年、東京大学医学部卒業。
53 ~ 62 年、国立予防衛生研究所免疫血清室長。
57 ~ 59 年、カリフォルニア工科大学化学部研究員。
63 ~ 70 年、小児喘息研究所(デンバー)免疫部長。
70 ~ 80 年、ジョンス・ホプキンス大学医学部教授。
74 ~ 80 年、京都大学医学部教授兼任。
81 ~ 89 年、ジョンス・ホプキンス大学免疫学部長。
89 ~ 96 年、ラホイヤアレルギー免疫研究所所長・カリフォルニア大学内科教授。
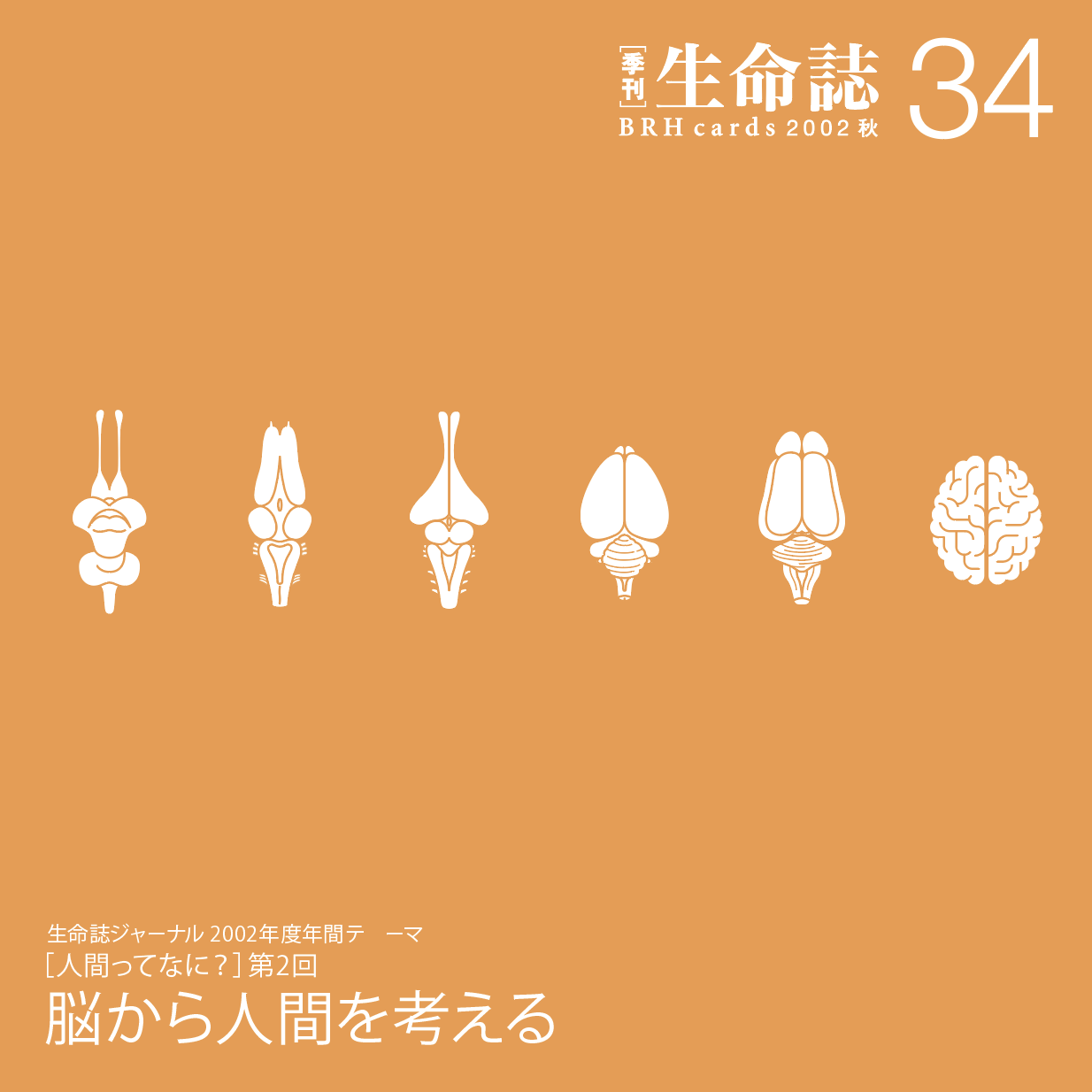
TALK
クオリア - 現実と仮想の出会い
茂木健一郎
ソニーコンピュータ研究所
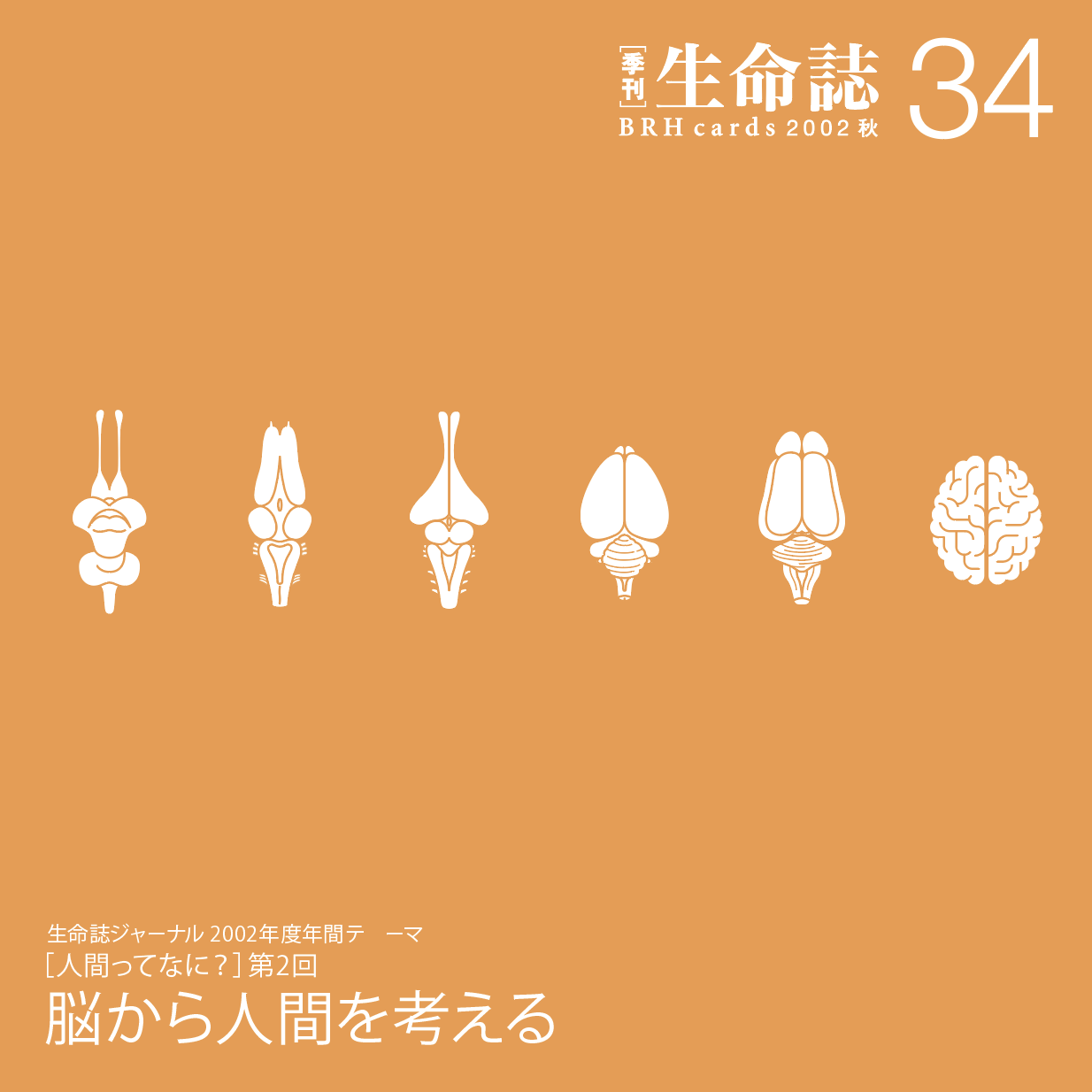
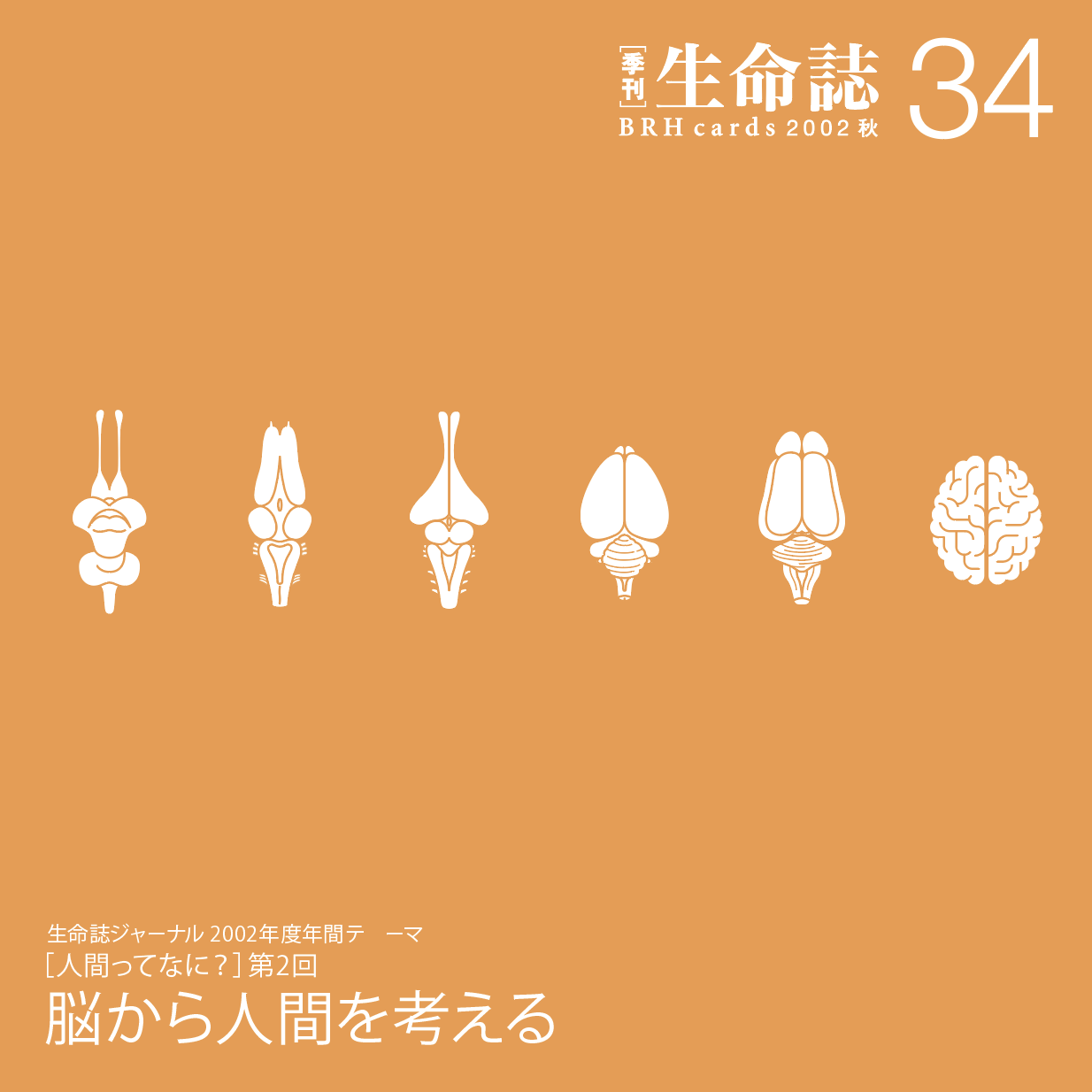
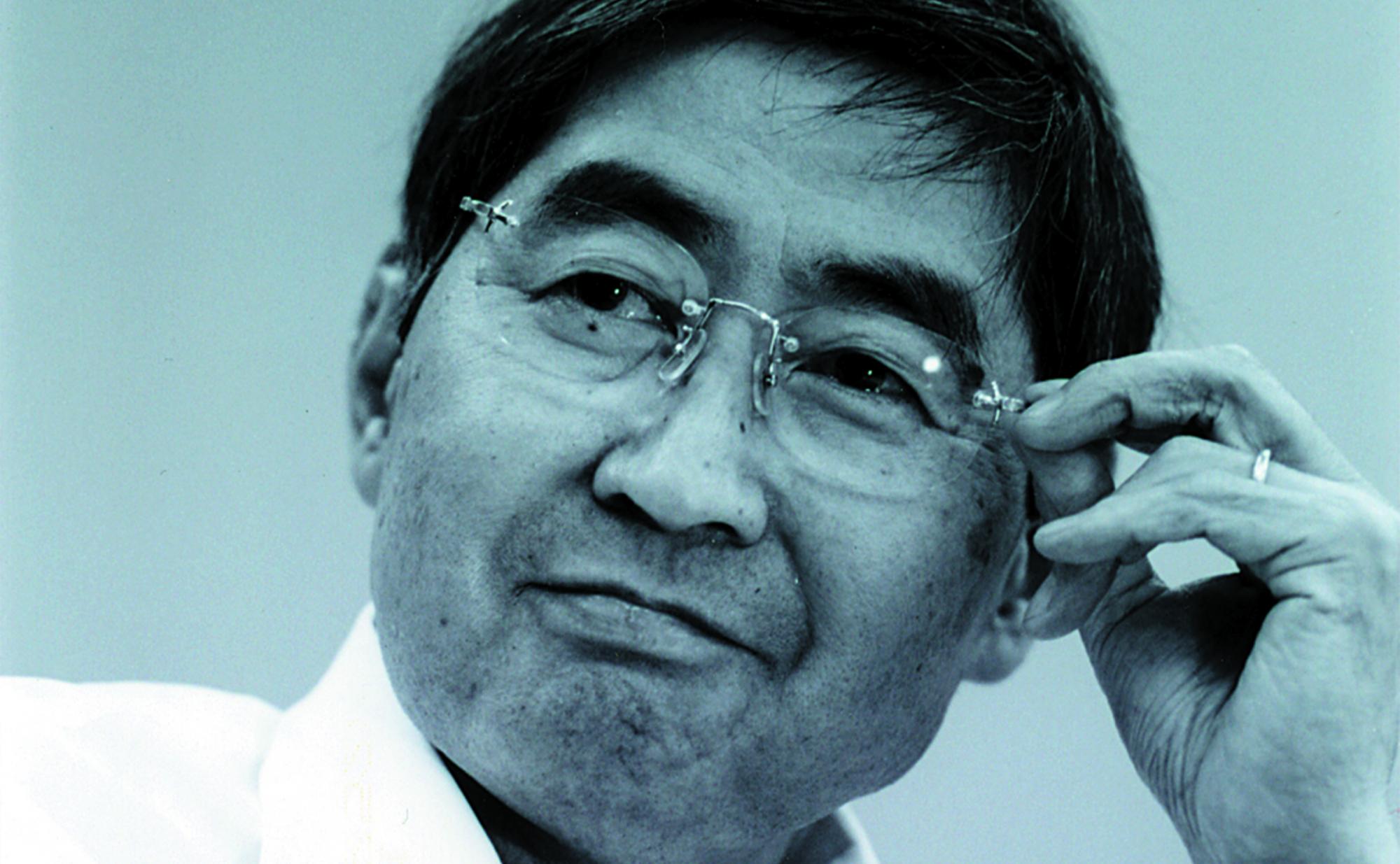
SCIENTIST LIBRARY
自分の頭で考える ~ウイルス研究からがん遺伝子の発見へ~
花房秀三郎
1929 年
兵庫県生まれ。
1950 年
大阪大学理学部化学科入学
1953 年
大阪大学理学部化学科卒業、同特別研究生となる
1958 年
大阪大学微生物病研究所助手
1961 年
米国カリフォルニア大学(バークレイ)
ウィルス研究所研究員
1964 年
仏国コレッジ・ド・フランス(パリ)
実験医学研究室研究員
1966 年
米国ニューヨーク公衆衛生研究所癌ウィルス研究部長
1973 年
米国ロックフェラー大学教授(分子腫瘍学)
1986 年
米国ロックフェラー大学 Leon Hess Professor
1998 年
米国ロックフェラー大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所所長

TALK
情報を切り口に…
辻井潤一 × 中村桂子
東京大学大学院情報理工学系研究科・コンピュータ科学専攻・教授
1949年生まれ。京都大学大学院工学博士取得。京都大学工学部・助教授、フランスグルノープル大学CNRS客員研究、マンチェスター大学計算言語学教授、1992~95年マンチェスター大学計算言語学センター所長を経て1996年より現職。


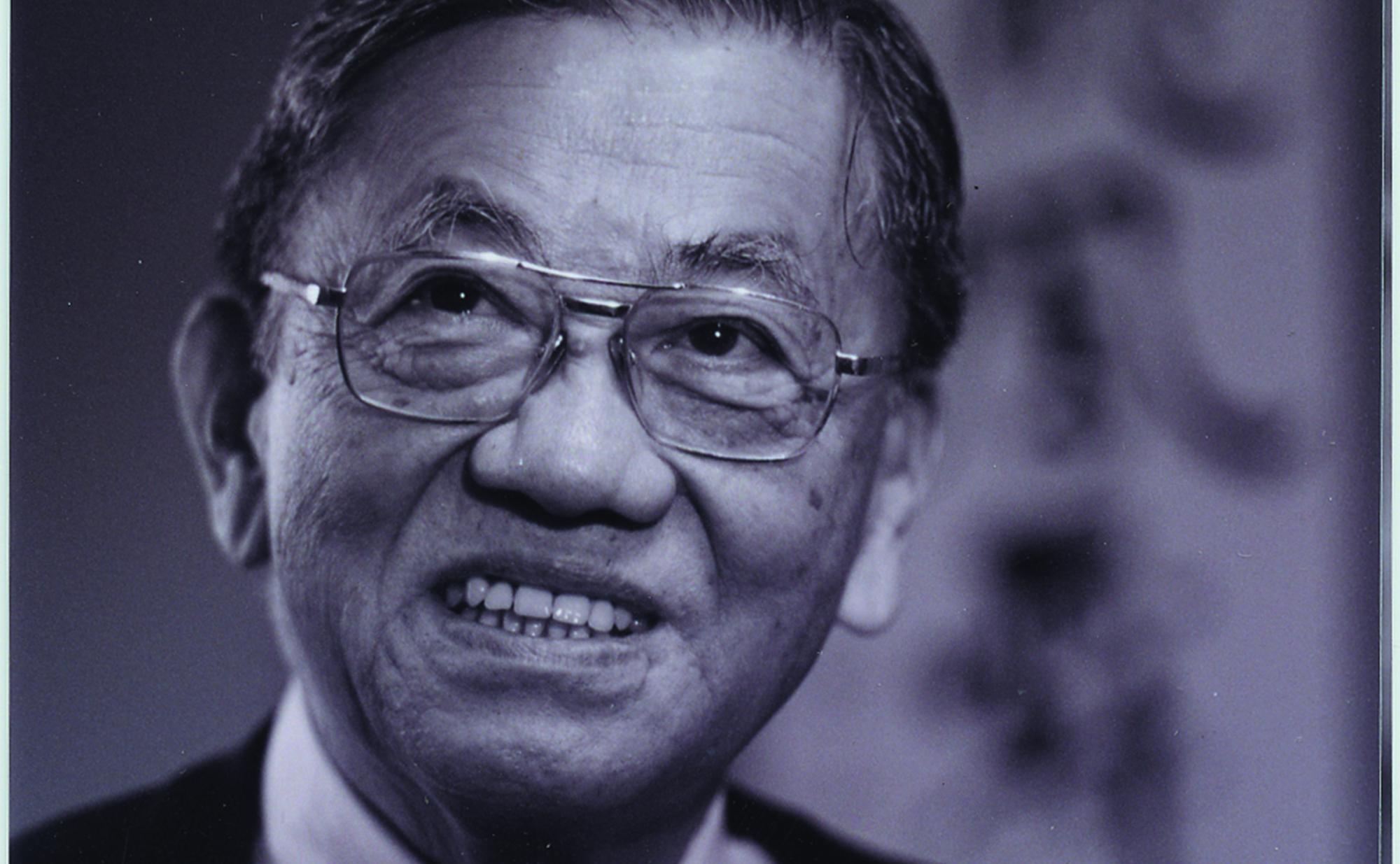
SCIENTIST LIBRARY
チョウとがんと未知なるものと私
杉村 隆
1926 年東京生まれ。49年東京大学医学部卒業。50 年同放射線医学教室助手。54 年財団法人癌研究会癌研究所助手所員。57 年米国国立癌研究所留学。59 年ウェスタンリザーブ大学に留学。60 年癌研所員。62~72年国立がんセンター研究所生化学部長。70 ~ 85 年東京大学医科学研究所教授併任。72 ~ 74 年国立がんセンター研究所副所長。74 ~ 84 年同研究所長。84 ~ 91 年同総長。92 年より同名誉総長。92 ~ 94 年厚生省顧問。94 ~ 2000 年東邦大学学長。日本学士院会員。米国国立アカデミー外人会員。オランダ学士院外人会員。スウェーデン学士院外人会員。集めるのが好き。今ではチョウやカメのオブジェなど気がついたらかってに集まるようになった。
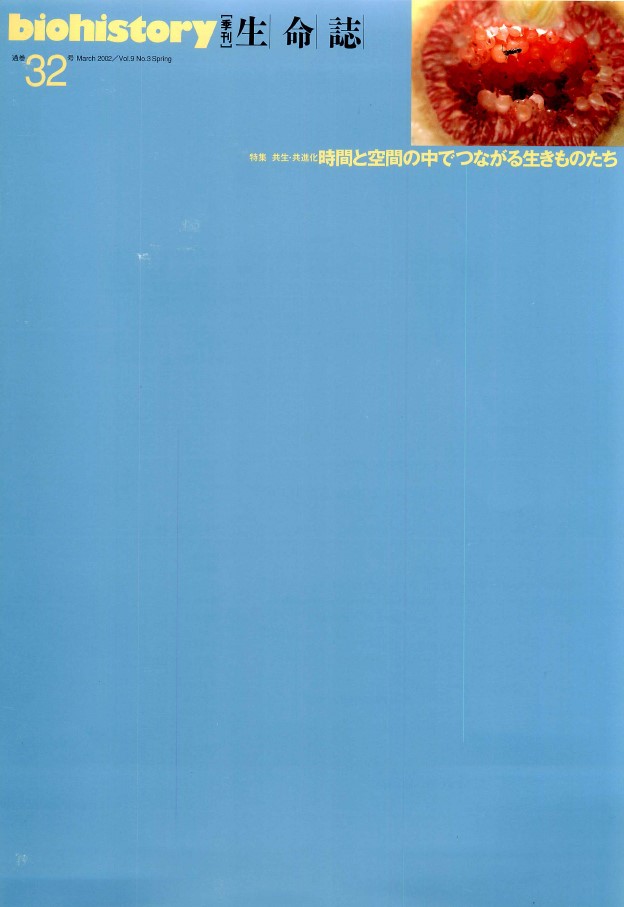
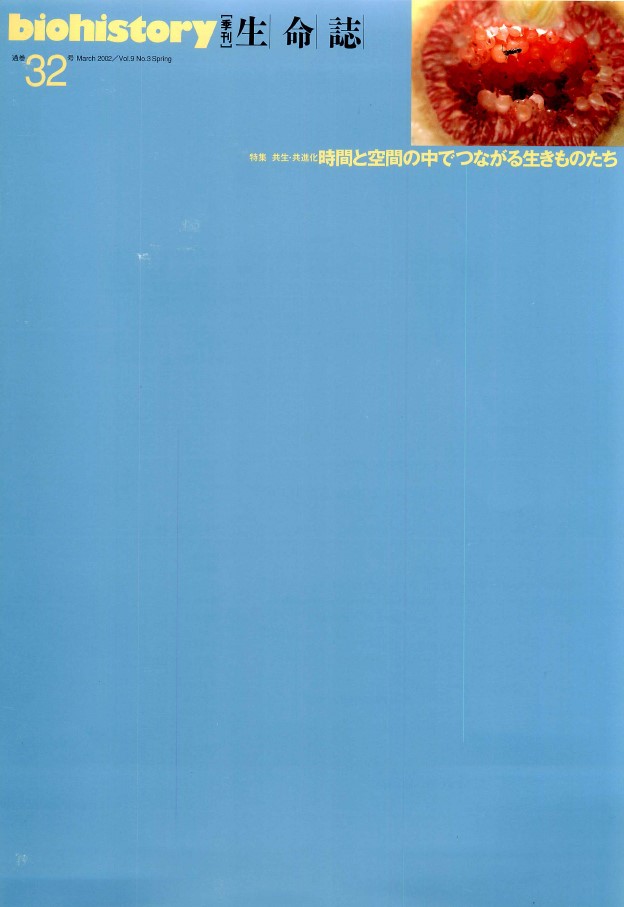
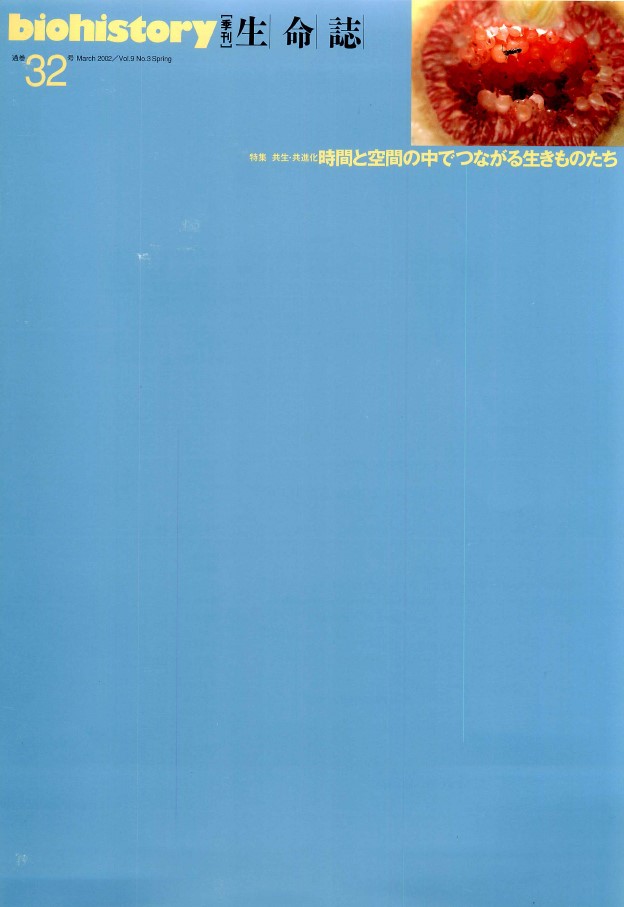
Special Story
花のゆりかごと空飛ぶ花粉 ─ イチジクとイチジクコバチの共進化
横山潤、蘇智慧
よこやま・じゅん
1968 年茨城県生まれ。東北大学生命科学研究科生態システム生命科学専攻助手。植物と昆虫の関係を中心に,生物同士の生態的なつながりが導く「共進化」に興味をもって研究を行なっている。
『植物の生き残り作戦』(平凡社)『多様性の植物学(3 )植物の種』(東京大学出版会)『アンコール・ワットの解明(4 )アンコール遺跡と社会文化発展』(連合出版)分担執筆。
すー ずぃふぃー
JT 生命誌研究館主任研究員。
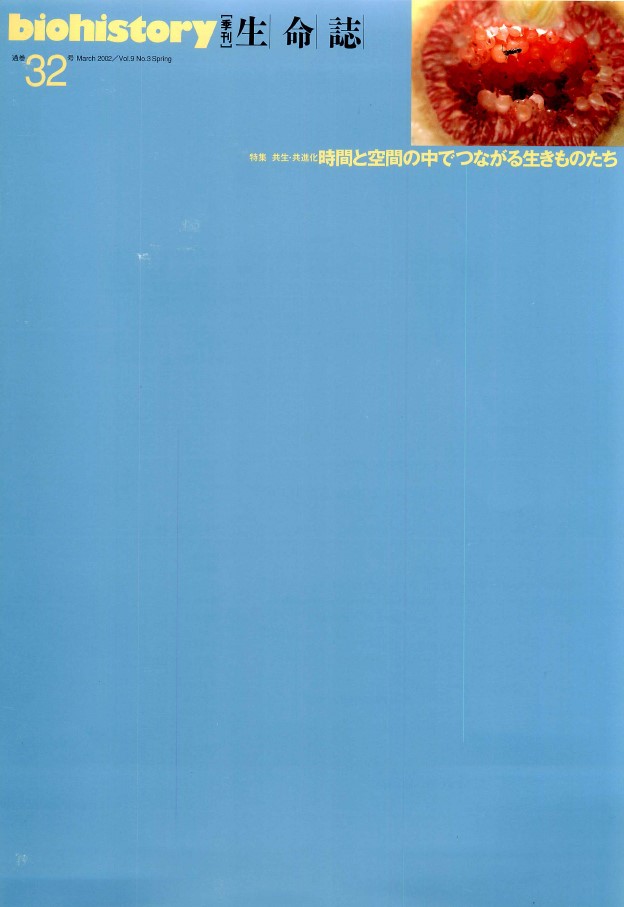
Special Story
相互利用のバランス
Rhett Harrison
1970 年スコットランド生まれ。94 年京都大学大学院に留学,現在京都大学生態学研究センター特別研究員。マレーシアを中心に,熱帯雨林の生態調査研究を行なっている。
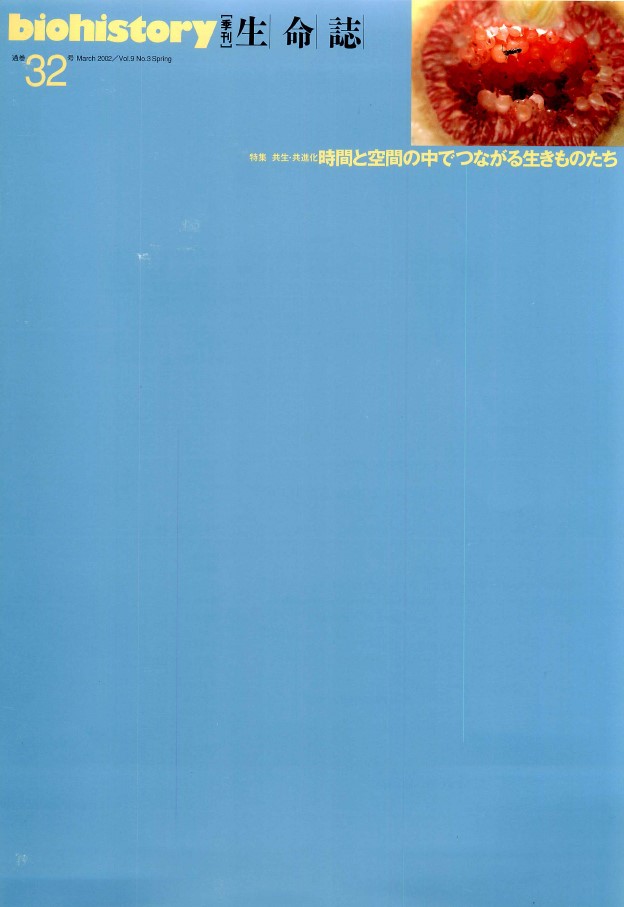
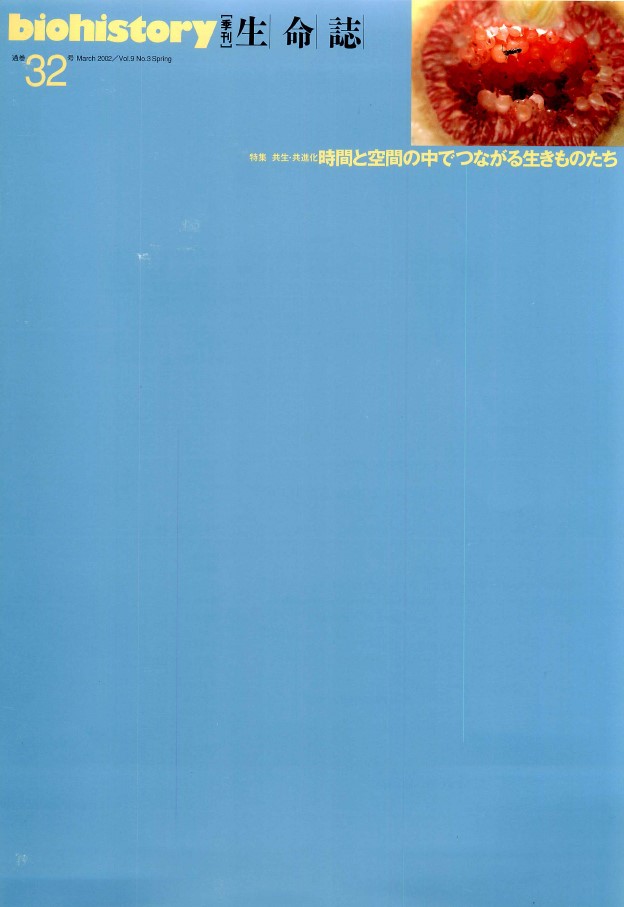
Special Story
ショウジョウバエの甘味受容体
谷村禎一
1951 年岐阜県生まれ。九州大学大学院理学研究院助教授。大きく言えばショウジョウバエの行動発現機構,具体的には味覚とサーカディアンリズムについて,遺伝子,細胞,生理,行動の各レベルからの総合的研究を行なっている。研究とは離れて,ミヒャエル・エンデ,大江健三郎など様々な分野の本を読む会を,月に一度もっている。
キーワード
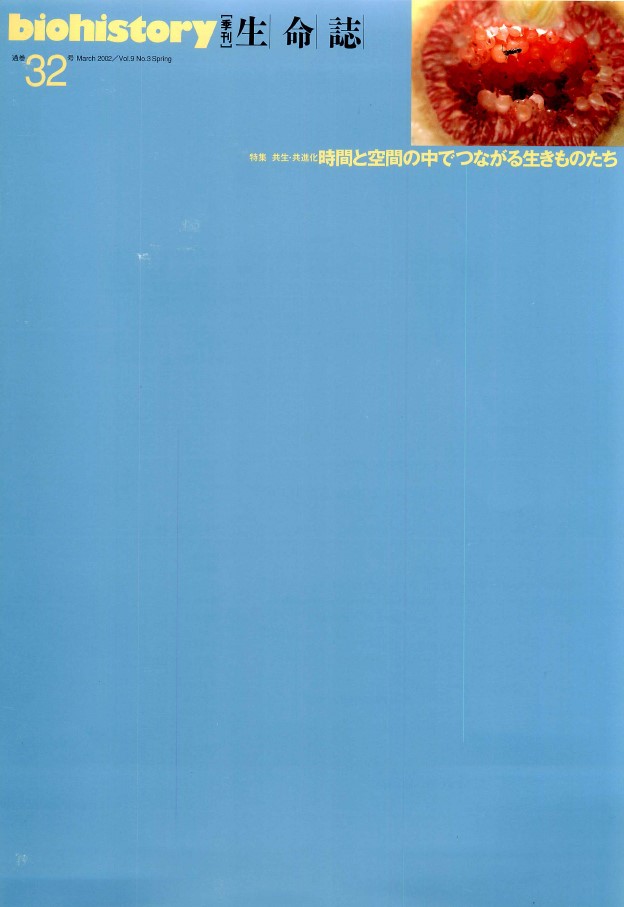
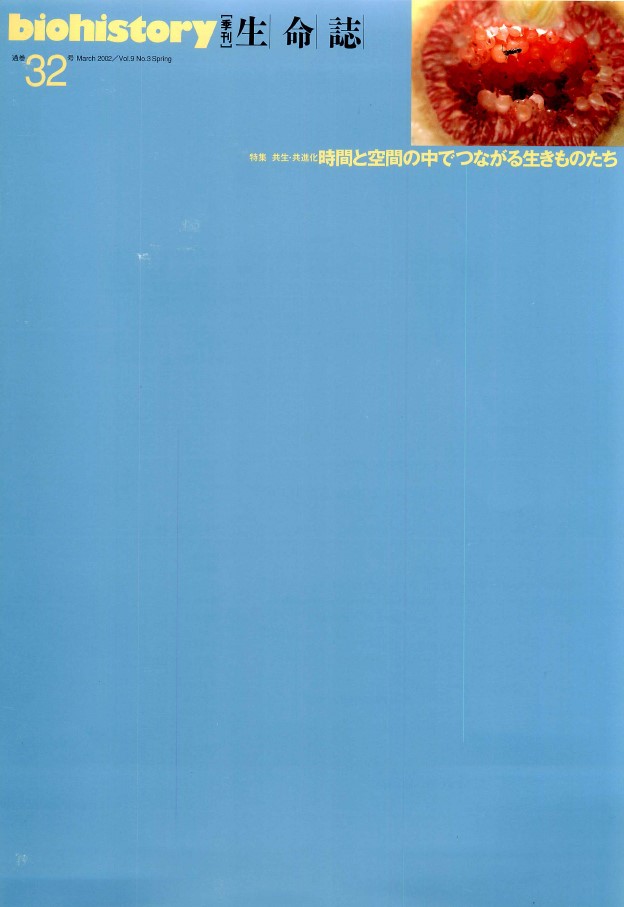
Special Story
雌を求めて迷う雄 ─ 実験生物シロイヌナズナからフィールドの近縁種へ
清水健太郎
1974 年埼玉県生まれ。京都大学理学研究科博士課程在籍。分子生物学を用いたシロイヌナズナ研究の創始者の一人,岡田清孝教授の指導のもと博士論文執筆中。雌雄間相互作用を中心に,植物の多様性と進化を研究。数学者広中平祐の創設した「数理の翼セミナー」と「湧源クラブ」を中心に高校生への理科教育にも携わる。共著書に『新版植物の形を決める分子機構』(秀潤社)がある。
キーワード
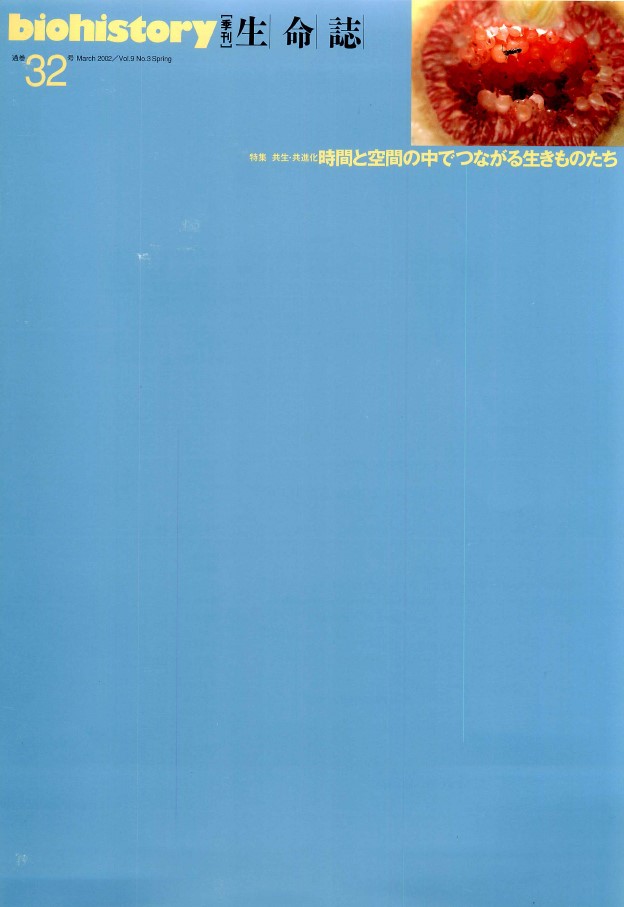
Special Story
魚の乳酸菌飲料? ─ 腸内共生細菌を活かした新しい養殖法
星野貴行
1952 年三重県生まれ。筑波大学応用生物化学系教授。応用分子微生物学。枯草菌,高度好熱菌の分子育種に関する研究に従事してきたが,最近,魚の微生物学研究にも着手した。
-
2025年
地球というわたしたち

-
2024年
あなたがいて「わたし」がいる
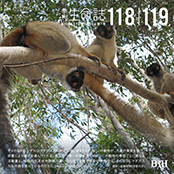
-
2023年
生きものの時間2
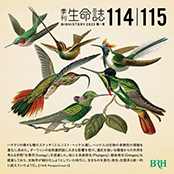
-
2022年
生きものの時間
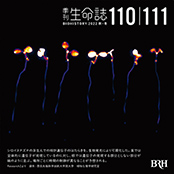
-
2021年
自然に開かれた窓を通して
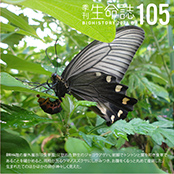
-
2020年
生きもののつながりの中の人間
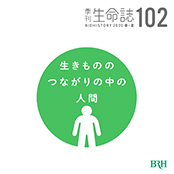
-
2019年
わたしの今いるところ、そしてこれから
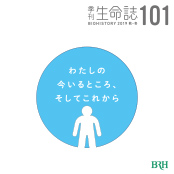
-
2018年
容いれる・ゆるす
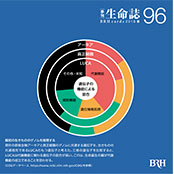
-
2017年
和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-
2016年
ゆらぐ
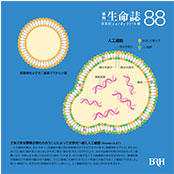
-
2015年
つむぐ

-
2014年
うつる
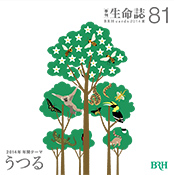
-
2013年
ひらく

-
2012年
変わる
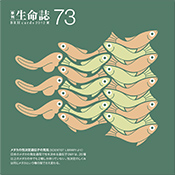
-
2011年
遊ぶ

-
2010年
編む
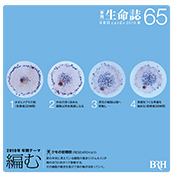
-
2009年
めぐる

-
2008年
続く

-
2007年
生る
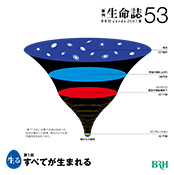
-
2006年
関わる

-
2005年
観る
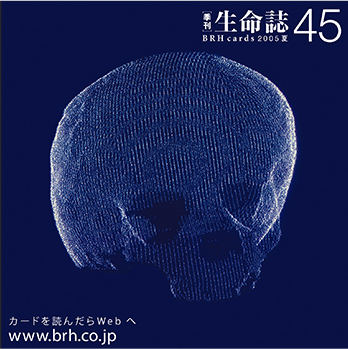
-
2004年
「語る」 「語る科学」

-
2003年
「愛づる」 「時」

-
2002年
人間ってなに?
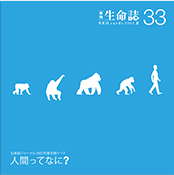
-
2001年
「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-
2000年
「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-
1999年
「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-
1998年
「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-
1997年
「花が咲くということ」ほか

-
1996年
「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-
1995年
「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-
1994年
「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-
1993年
「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、
多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。
さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。
-
![]()
動詞で考える生命誌
生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。
- PC閲覧専用コンテンツです。
-
![]()
生命誌の世界観
科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。
- PC閲覧専用コンテンツです。
-
![]()
生命研究のあゆみ
日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。
- PC閲覧専用コンテンツです。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)