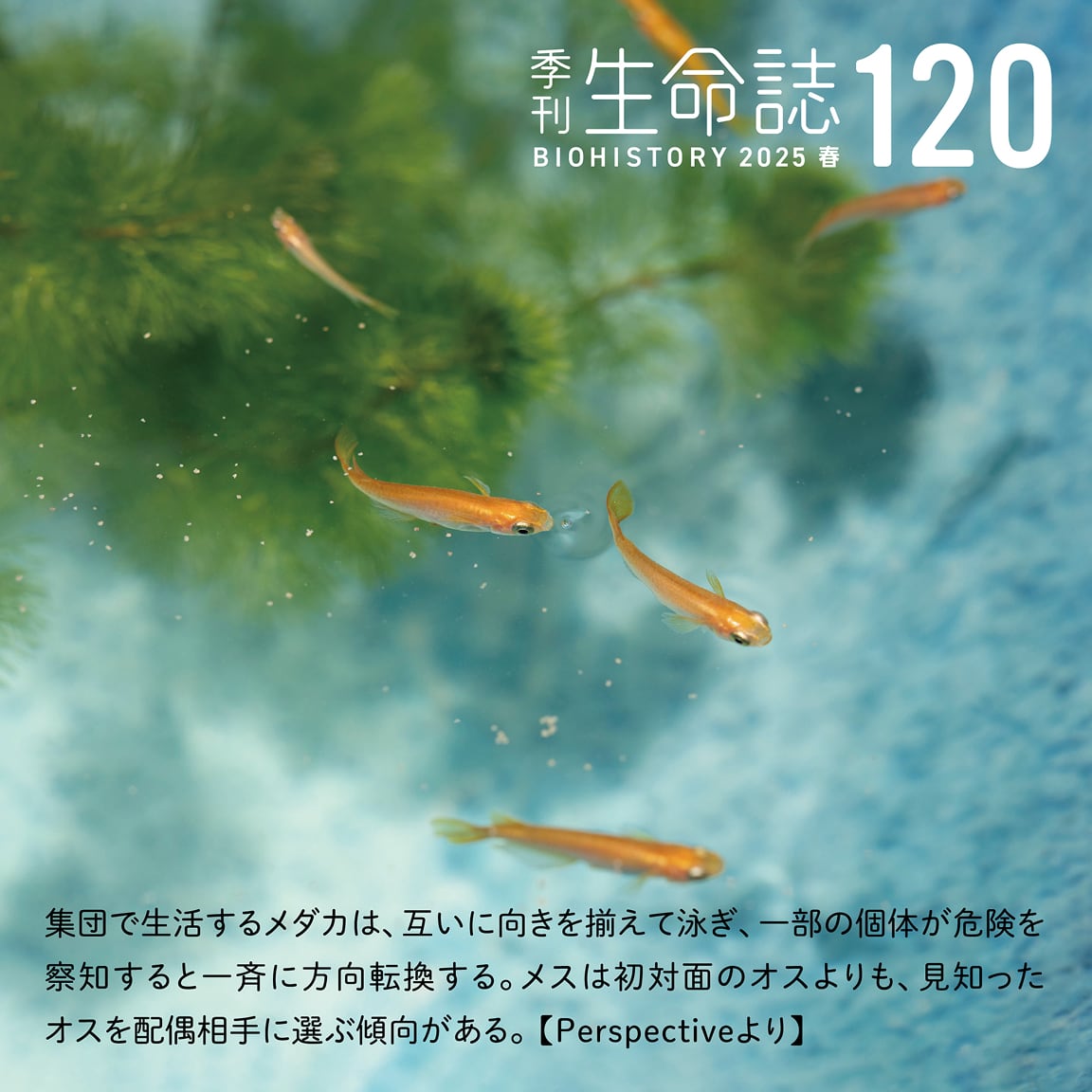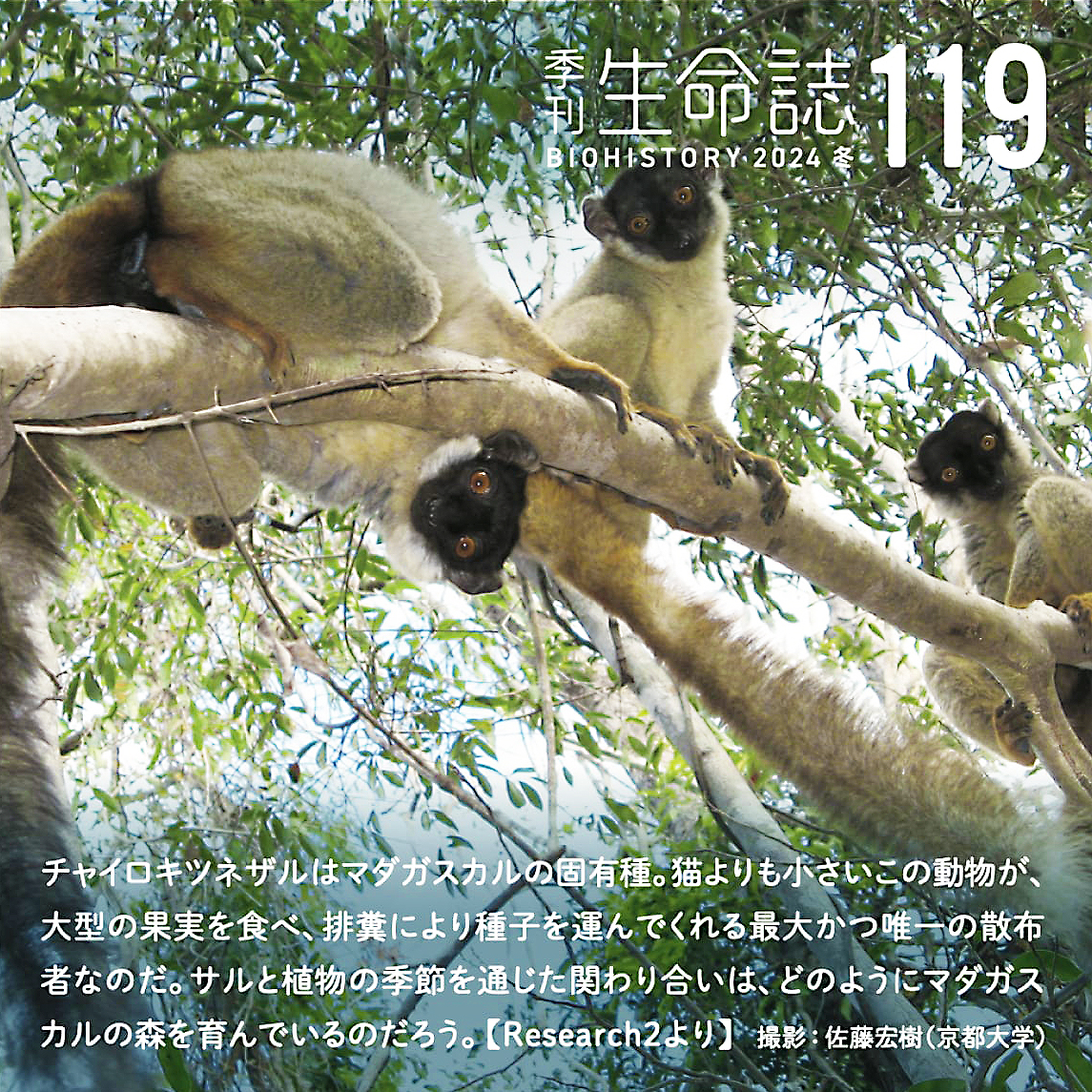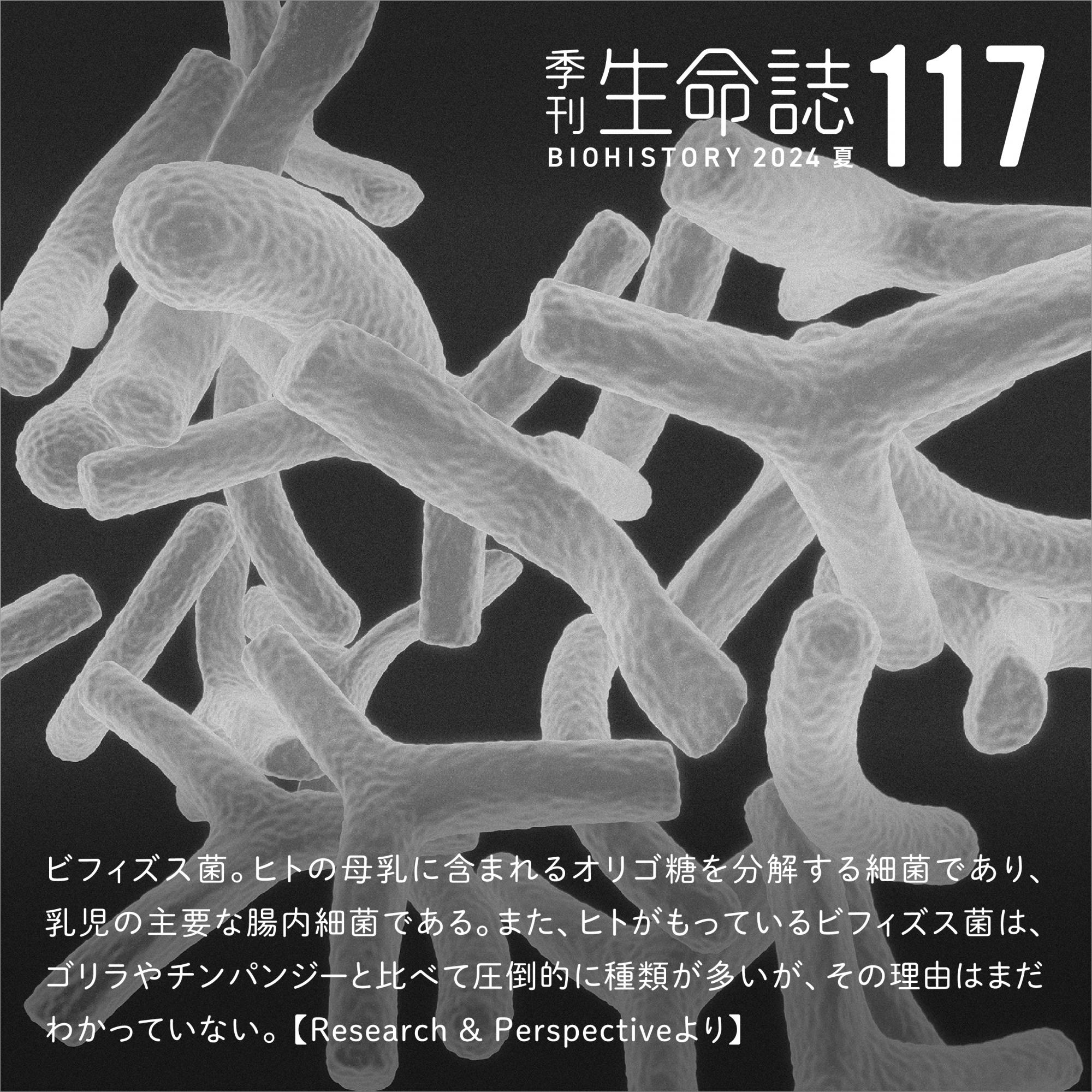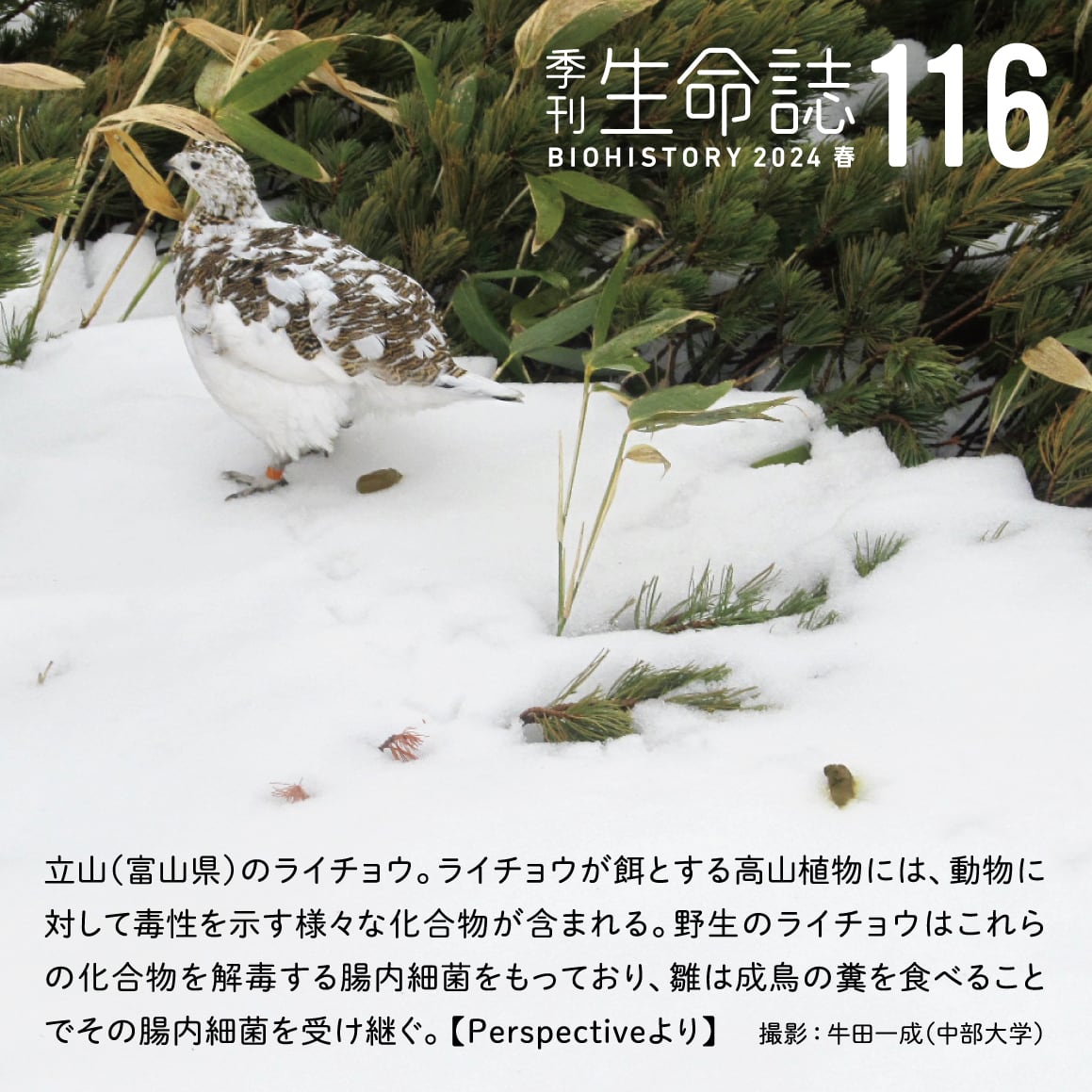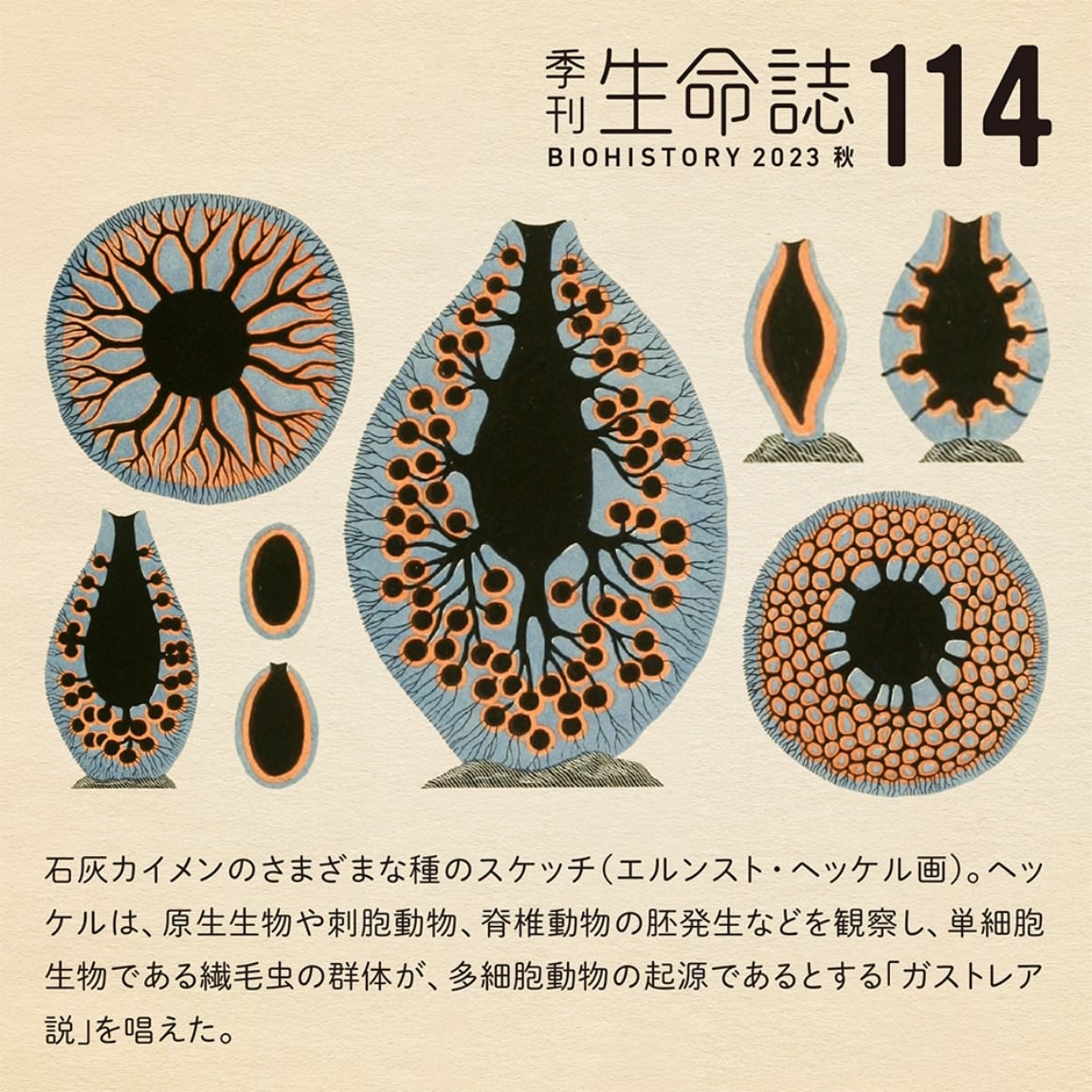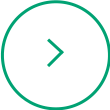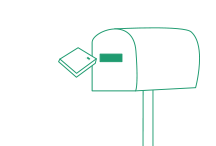Talk
年間特集「人間ってなに?」
人間の脳って特別?
人間とは何かを考えるトークの2回目は、「脳」に焦点を当てます。脳が臓器のひとつであるという視点から、生き物の連続性の中で捉えることで、人間とは何かに迫ろうとします。キーになるのは言語とゲノム。クオリア(質感)から脳と心を研究している茂木健一郎さんを研究館にお迎えしての対談です。

1. 脳はコンピュータではない
中村
生命誌では、ゲノムから自然界の生物たちを見てきましたが、そろそろ人間にも眼を向けなければならなくなりました。人間と言えば、言語と脳。脳について、茂木さんと2つのことを話したい。脳の研究者は、脳を特別視して、関心は人間の脳に集中していますが、生物にとって脳は臓器の1つ。腸が消化するのと同じように、外からの情報を処理するものです。そこで、単細胞生物での情報処理とも通じる感覚器、運動系と一体化した脳の系統的見方が1つ。もう1つは、言語処理はこれとどうつながるのか、またはつながらないのか。この2つが生命誌からの脳研究への関心なのです。
茂木
コピュータの原理がわかった1945年ごろ以来、脳を情報処理機械として考えるいわゆるコンピュータメタファーがあまりにも強いのですが、認知科学でも、コンピュータメタファーで語る人はあまりおもしろくない。コンピュータという考え方に毒されないピアジェ辺りの時代の人が言っていたことのほうがおもしろい。脳も生きている臓器だと見た瞬間にいろいろわかってくることがある。 コンピュータは、ノイズが1ビットでも乗ると誤動作してしまうけども、脳は、一見ノイズに見える部分が非常に大きい。逆に瞑想する時のように、情報の入力が一切なく運動の出力も一切ない状態でも、ニューロンは勝手に自発活動する。ところが今の神経科学の主流はこのノイズを無視している。
中村
デジタルに見てしまうということですね。
茂木
本来の脳は、環境と作用しながら、やわらかくしなやかに動いていくものなのに、デジタルコンピュータのイメージが強すぎるんで、「何で、脳はコンピュータみたいに動かないんだ?」という質問をしてしまうんですね。本来コンピュータなんて縁もゆかりもないようなものだと思うんですよ、脳は。
中村
茂木さんと言えば「クオリア」。この説明は別の項で詳しくしていただくとして、同じ赤を見てもバラの花びらか信号か、それにまつわる思い出があるので赤の意味が変わるということはその通り。そういう柔らかい視点を入れないと、脳研究は先へ進まないのでしょうね。
茂木
クオリアは、人間の意識に深く関係しているので、人間だけが持っているようにも見えるのですが、生物は進化の連続性があるから、突然無から何かができるということはない。クオリアという意識の問題は難しいけれど、例えば赤い色の質感は、おそらく環境の中に繰り返し現れるリダンダント(重複した)な特徴を表しているのだろうと思う。動物にとっても環境の中に繰り返し現れる特徴は同じなわけです。何故色が意識における認識の鍵として採用されたかというと、波長から計算される色という属性を使うとその組み合わせで、環境の中にある表面の様子が非常によく記述できたからだと思うんです。 だとすると、犬や猫、もっと単純な視覚系をもっている動物でも、人間とまったく同じ意味で赤い色を見ているとは言えないかもしれないけれども、環境を見るときの基本的な要素は同じでしょう。だから、おそらくクオリアは進化的に見てかなり早い段階からあるだろうと思う。そこまで行ってしまうと、中村さんが言ったように神経系が特別なのかという話にまでなるわけです。
中村
そう。単細胞も必ず外とのやり取りをやって行動している。外とやり取りをするものが生物であると言ってもいいわけです。ただここで認識するとか、判断するという言葉は使えませんね。私たちが見るとバクテリアも認識し、判断して行動しているように見えますが、それは単なる化学反応の連続でしかありません。
茂木
それ以上に難しいのは、第2のテーマとしてあげられた言語の進化をどう見るかです。おそらく言語も非常に長い時間かけて脳が準備しているものの上に乗っ取るようにできたと思う。ゲノムの場合もその情報系がいきなりできるわけではなくて、その足場みたいなものがあっただろうけれど、それが何なのかはまだわからないわけでしょう。生命の起源の問題の難しさはここにある。それと同じように、言語の足場が何であったかという問題も難しい。
「同じ」「違う」を区別する抽象的な思考に相当するものが言語の準備をしていたと思う。最近、蜂はある場所が前と「同じ」か「違う」かをちゃんと学習できて、しかも特徴が色でも匂いでも、それには関係なく「同じ」「違う」の拠り所となるという話がありますね。ある場所でエサが手に入ったら、それと同じ場所に行くのが良い方法です。一方、ある場所で嫌な思いをしたら、違うところに行くのが良い戦略。だから、空間を移動する蜂のような昆虫にとって、「同じ」「違う」を判断することは、生きる上で非常に重要な能力だったはずです。実際、蜂にはそういう能力がある。このように見ると、「同じ」「違う」という非常に抽象的なロジックに相当するものが、実は動物界に共通してあるだろうと思えてくるわけです。自分と同種の個体を見分けるのも、擬態も、まさにそういう問題です。
人間の言語は、一見他の生物からジャンプがあるように見えるけれども、「同じ」「違う」という論理的な判断のようなものが動物界に広く見られるとすると、実は単純な生物から綿々と蓄積されてきたものをうまく使っていると考えられます。
中村
「同じ」「違う」を区別する機能が言語に乗っ取られる準備として大事だったという指摘はなるほどと思う。でも、今のお話から脳の処理能力として99.9999…%できていたとしても、蜂と私たちとはやっぱり違うでしょう。蜂は学校をつくらない。その差は小さいけれども大きいわけで、その差はやはり言語の力ですよね。
茂木
「私」という意識も、人間にしかないように思えるけれど、動物にもプリミティブな形ではあるに決まっている。人間が自分を特別な存在だと思うように他の動物も思っているかもしれない。自分の種を保存するためには、自分は特別だと思わないといけないですからね。
中村
 当然そうですね。猿は猿中心で、ウグイスはウグイス中心で動いているに違いない。ただそこで「私」という意識を持つかどうか。それはどうしてもまた「言葉」にいってしまう。生命誌はこれまで99.9999…%の連続の話に注目してきて、連続は確かなのですが、0.000…1%のジャンプをどう見るかが気になり出したのです。物質と生命のところでもまったく同じに、生命体を構成する物質についてはすべてわかっても、それで生命がわかるかという小さいけれど100%連続とはいえない問題があるわけです。
当然そうですね。猿は猿中心で、ウグイスはウグイス中心で動いているに違いない。ただそこで「私」という意識を持つかどうか。それはどうしてもまた「言葉」にいってしまう。生命誌はこれまで99.9999…%の連続の話に注目してきて、連続は確かなのですが、0.000…1%のジャンプをどう見るかが気になり出したのです。物質と生命のところでもまったく同じに、生命体を構成する物質についてはすべてわかっても、それで生命がわかるかという小さいけれど100%連続とはいえない問題があるわけです。
2. 人間の特殊性 - 他人の心を読みとる
茂木
色覚のメカニズムは、明らかに連続的に進化してきたものですから(関連記事:生命誌12号「進化する色の世界:徳永史生」)、人間だけ赤いクオリアを持っていることは絶対あり得ない。ただ、3歳児が赤い色を見ているのと、私が今クオリアという概念について考えながら色を見ているのとは違う。人間が色を見るときの見方は、自己反省が含まれている。見ているということ自体を反省するもう1つ高次の心の働きがあるのです。昆虫は産んだ卵から生まれる自分の子孫を見ることはない。自分は死ぬが、次の春が来たら子供が出てくるだろうという感慨に浸ることはない。人間だったらそのような感慨に浸るだろう。一般に自己反省の能力は、言語という飛躍と前後して、人間にだけ備わったものだと多くの人が考えている。
中村
なるほど。3歳児が言語能力を獲得するにつれて、その能力も備わってくるわけですね。
茂木
人間の知性とは何かを考える時に、一番多くの人が非常に重要な問題だと思っているのは、他人の心を読みとる能力です。これは今のところ、人間にしかないと考えられていますが、大論争になっていて、チンパンジーだって他者の心を読みとれるだろうという説もある。その際、 何が本質かというと、人間の持つ、今ここにないものを思い浮かべる能力です。例えば地球の反対側のブラジルのことも思い浮かべることができる。
中村
神様という本質的に見えないものも思い浮かべる想像力であり、それが創造にもつながるわけですが、その能力は言語を持っているから持てるのだと思っています。
茂木
まさにその通りです。チンパンジーが他の個体が泣くのを見て、自分も泣いたとする。しかし、これは、他人の心がわかったという解釈もできるけど、見たままのものに反応しているだけだという解釈もできるわけですね。目の前に見える状況からは直接は推測できないような他者の心の状態を表象化する能力ですね。それは、我々の言語能力とも非常に深く関わっていて、どうやら他人の心の内容を推定する能力は人間にしかないという結論になっている。人間でも、いわゆる自閉症(autism)と呼ばれる人たちには、その能力が欠けているという説があるんですね。そうなってくると、脳科学的に言う知性とは、徹頭徹尾、社会的なものであるということになる。つまり、人間の知性は、そのスタートのところから他人の心を読みとるとか、そういう社会的な知性として発達してきのではないか。言語もそういう文脈の中で考えられると思う。
3. 脳研究はライフヒストリーの中で
中村
人間を知るための脳研究として他の生物との連続と言語という2つの切り口があるのではないかという生命誌からの問いにとても前向きなお話がいただけて、ありがたいのですが、そのような意識で脳の研究を進めていくとすると…。
茂木
まずコンピュータからどんどん離れなくちゃいけないですね。たいていの重要なことは、ライフヒストリーと深く関わっていて、その中で1回しか起こらないわけですから。そういう研究は、今までほとんど真面目にやられていないと思う。進化には、形態の進化もありますけれども、ライフヒストリーというか行動パターンも重要なわけですよね。 昔、アマゾニアンブルーという中型インコを飼っていたことがあります。ある時ふざけて、蛇のおもちゃを見せた。そうしたら、可哀想に、それまで蛇なんて見たことないはずなのに、「ギャッ」と飛び上がった。そして、恐怖の表情を浮かべて、カゴの隅にいる。明らかに本能ですよね。フィールドワークをやっている人は、こんな驚くべき行動をよく知っていると思うんです。その時に中枢神経系がどう働いているかは重要なテーマだと思うんです。どうやってこのような稀なイベントを研究していくのかという方法論は非常に難しいですけれど。
昆虫は結構複雑なことをやっているけれど、本能として植え付けられているものがほとんど(関連記事:生命誌23号「アリは仲間をどう見分けるか?:山岡亮平」)。人間と昆虫の脳の最大の違いは、本能でやられていることと、学習によって非常に柔軟にやられているところの割合にある。要するに文化に相当するものがあるかどうかということですね。文化が違えば脳は違ったふうになるということが人間の場合は重要である。生物の観点から中枢神経系を研究する時に、本能と文化の割合をどのように考えるかが1つの鍵かと思います。
中村
生きものの連続性の中で考えるには昆虫や鳥のそのような行動を知るのは楽しいけれど、もう一方で人間の脳研究として進められているニューロンの研究とどうつなげていくのか。さらには、遺伝子研究とどうつなげていくか。その辺がよく見えないのです。
茂木
 人間でも生活の中の一回性の行動との関係を探る研究が少しずつ出てきている。例えば、『ネイチャー・ニューロサイエンス』に10年前だったら載らないような論文が出る。ビデオを見て何となく様子が変わったなと思ったらボタンを押すというある意味では非常に曖昧なタスクをさせる実験です。「なんとなく様子が変わったな」と思う前後である領域の脳活動が変わる。何がおもしろいかと言うと、今までは、あるイベントを待っていてそれをきっかけにしてその前後の脳活動を見るというタイプの研究はなかった。このような認知プロセスは、人間という生きものが環境の中でしなやかに生きていくということに関係すると思うのです。
人間でも生活の中の一回性の行動との関係を探る研究が少しずつ出てきている。例えば、『ネイチャー・ニューロサイエンス』に10年前だったら載らないような論文が出る。ビデオを見て何となく様子が変わったなと思ったらボタンを押すというある意味では非常に曖昧なタスクをさせる実験です。「なんとなく様子が変わったな」と思う前後である領域の脳活動が変わる。何がおもしろいかと言うと、今までは、あるイベントを待っていてそれをきっかけにしてその前後の脳活動を見るというタイプの研究はなかった。このような認知プロセスは、人間という生きものが環境の中でしなやかに生きていくということに関係すると思うのです。
「発想」も、外からきっかけを与えることができず、内発的なイベントの発生を待たねばならない現象です。人間の場合、何かを発想するときは、むしろ刺激がないことが重要なんですね。京都の哲学の道を年に1回ぐらいは散歩するんです。あそこで西田幾多郎はいろいろ哲学的な思いつきをしたらしいんだけれども、僕が行っても何も思いつかない。俺は頭が悪いんだなとずうっと思っていたんですが、ある時非常におもしろいことに気がついた。じゃあ僕が思いつくのはいつかというと、毎日家から駅まで歩く道なんですね。僕が哲学の道に行くのは1年に1回くらいだから珍しくてキョロキョロしちゃう。毎日歩いている道は全部知ってるから、脳が退屈するわけですよ。それで、ははあと思った。あの「哲学の道」が彼にとって「哲学の道」だったのは、毎日歩いていたからなんですね。哲学の道というのは、別に特別な道ではなくて、毎日歩いている道が哲学の道なんです。刺激の欠如が「発想」のプロセスを立ち上げる。ところがそういうタイプの研究は、あまりないわけです。今までの研究は、ある特定の刺激を見せて、とにかく一生懸命タスクをやらせて、その時に脳がどうなっているかという研究なんです。哲学の道タイプの研究は、逆におもしろい刺激を切ったら、「ああ、そうか」と思いつくことを対象にしなければならない。実際に我々の脳は、そういうふうに動いている。常におもしろいことばっかりだったら、意外と何も思いつかないものですよね。退屈とか不安とか、そういうネガティブなものが、実は重要なんだと思います。感情のエコロジーみたいなものがある。だから、アメリカで抗鬱剤として使われているプロザックなどの薬は危ないと思うんです。鬱状態は鬱状態なりの、何か意味があるはずじゃないですか。
中村
そうでしょうね。鬱のときに静かに考えていたものを、躁のときにワーッと外へ出すということかもしれない。
茂木
他の生物にもそういうのがあるんじゃないでしょうか。例えば、餌が手に入らなさそうな時にはじっとしているとか。実は人間の感情も、そういう言わば原始的な適応からきているかもしれないですね。そういう視点は今まではあまりないんですよ。
中村
確かにそうですね。今の世の中は、退屈や不安を全部なくそうという動きですから。それは機械的な発想でしょうね。機械は常に働けるものではなくてはいけない。
茂木
とにかく鬱や不安が、否定的な状態であるという考え方は変だと思う。否定的なものだったら、なんでそんなものが進化の過程で出てきたんだということになりますよね。鬱や不安は適応的だったからこそ出現してきたに決まっている。そういうことの意味は、やはり人間という生物の生活史を全体として眺めないと、答はわからないと思う。鬱状態になっている時だけを見たら、確かに一見否定的な状態ですが、全体として見るとそれはきっと何か意味があるんですね。
中村
脳究はライフヒストリーとおっしゃったけれど、それと連動する形で身体についての視点にも歴史性が必要だと思うのです。生命科学から時間の視点を入れた生命誌に移ったら、生命科学の時に見えていなかったものが見えてきました。生物学は歴史なのではないかと。そこから2つの方向に眼が広がる。1つは自然も結局歴史だということ、それから人間の一生を歴史として追うこと。後者はライフステージと呼んでいるのですが。
茂木
それはきっと、非常に重要な視点だと思います。
中村
科学は再現性があり、モデル化できるものと考えられており、その定義からすると、生物は外れていて、再現性というよりもむしろ一回性。脳という機械のメカニズムを知りたいですから、神経系を調べることは大事ですし、おもしろいけれども、人間を知るというテーマを立てた時に、やっぱり人間も歴史でしょう。だから、まずライフヒストリーという視点を持ってからじゃあ何を調べるかという、そういう研究の仕方の必要性は大きいですね。
茂木
歴史というふうにおっしゃったのは非常に重要なポイントだと思います。「再現性」を厳密に考える科学主義者が宇宙論なんて科学じゃないという言い方をしたりする。宇宙の歴史なんて1回しかないからですね。でも、それを言っていたら、非常に重要な宇宙論という分野は成立しないわけです。確かに宇宙なんて、実験室の中で100回作れるわけではないが、再現性という縛りを外した瞬間に、むしろ非常に豊かな世界が広がる。脳もまさに歴史ですよね。一人一人の脳はもう二度と作れないわけですから。
中村
生きものがそうでしょう。現存の生きものが出てきたのは、様々な状況があってのことで、もう1回やり直したら、まったく同じことが起きるかというと、多分それはないでしょう。ただそれではでたらめかというとそうではない。地球上の生命体の基本としてはこういう性質があるとかこういう構造をもつという枠はあると思っています。
茂木
グールドが『ワンダフル・ライフ』で書いたような、すごく変な生きものが出てくる。要するに進化のプロセスには、必然性なんかないということですよね。脳もおそらくそうで、逆に普遍性という縛りを要求し続けることによって、研究対象がものすごく陳腐なものになってしまう。人間の言語は本来、例えば夏目漱石が書いた小説は二度と同じことは誰も書かないであろうというぐらい、非常に繊細な神経が行き届いているわけですよね。普遍性、再現性を標榜して言語を研究しようと思ったら、「こんにちは」「ただいま」「おはよう」とか、「ご予約は何部屋ですか」「シングルですか。ダブルですか」みたいな陳腐な例ばかり考えるしかない。おもしろいものほど、1回しかおこらない歴史的なもので、何回も繰り返し起こる言語現象をやろうと思ったら、すごく陳腐なものになってしまう。そこで危険なのは、陳腐なものを研究しているという自覚があればいいんだけれども、それこそが人間だと思ってしまうことです。特に脳の研究は、人間理解という意味で、特権的な地位を持っていると多くの人が思ってしまっていますから。「こういう脳のメカニズムがわかりました」というのを寄せ集めても、陳腐な人間像しか出てこない。そこに非常に構造的な問題があると僕は思うんです。再現性ということの縛りを外して、歴史として見たら、随分、気が楽になるし、そっちのほうが正しい態度じゃないかと思うんです。
4. 一回的だが普遍的なゲノムと言葉
中村
生きものの歴史については、一回性で、同じことは二度と起きないかもしれないけれど、私たちが知っている生物がもつゲノムの基本構造は存在していることがわかっている。どんな変異が起きて変わっても、ATGCは並んでいて、それが複製し、時々間違うということは同じであって、とんでもない変わり方をしたら生まれてこない。チョウとして生まれたものはどんなチョウであろうと、チョウだという保証をもらっている。ある種の規則性を持っていると思うんですね。人間社会の法則性は難しいから、歴史家はそんなことをやらないのでしょうが、生物に関しては、DNAという非常によい鍵があるから、規則性が探せるわけですよ。そこがおもしろい。
茂木
わかります。問題は、それに相当するものが脳にあるかということですね。きっと、人間の場合は、シンボルとか言語がそれに相当するでしょう。
中村
やっぱり言語でしょう。だけど、そういうかたちで脳を研究していらっしゃる方が少ないような気がして。
茂木
そのような意味で言語が本質だと考えている人は日本では少ないけれど、外国では増えてきていると思います。日本では、いわゆる「複雑系」の分野の研究者でしょうか。複雑系の研究者と議論して、いつも問題になるのは、一回的だけども普遍的という、一見矛盾するように見える概念です。歴史は繰り返すというように、一回的に見えるけども実は普遍的な法則がある。そこを捉えるしかない。言語は、実はそれを扱うために進化してきたと思う。つまり人間が、一回性を普遍的なものにするために言語を発達させてきたのだろうと。「雨が降る」という現象は細かく見れば毎回違うけれども、雨が降るという単一の言葉で表現する。おそらくそれが鍵だと思うんですね。
中村
ゲノムがまさにそうなのです。ネコが見る、イヌが見る、私が見る。すべて違うけれど、その時起きている反応は同じでしょう。
茂木
「悲しい」と言っても、いろんな人のいろんな悲しみ方があるけども、「悲しい」ということで、普遍的なものを捉えようとする。それが言語の役割だと思うんですね。
中村
ゲノムも一回性でありながら明らかに普遍性をもつからおもしろいと思って生命誌を始めたのですが、今はゲノムを切り口にする研究は生物学としてはっきりした流れになっています。その眼で脳を見ると、ゲノムに相当するものは言語だと思うのです。このような考え方での研究はまだ主流ではありませんが、大事だと思います。
5. 神経系とゲノムの継続性
茂木
砂漠にいるガービルという動物の実験で、音のピッチが上がる、下がるという2種類のカテゴリーを区別する概念化のプロセスを知ろうとしたものがあります。最初はできないんだけれど、上がる時には餌がもらえて、下がる時には電気ショックがくるということをくり返していると、段々概念化ができていくという過程を脳のニューロン活動として継続して見ている例があります。このような意味での概念化は、言語誕生以前の生物界で非常に共通の能力であるような気がする。そこが壊れてしまった生物は死んでしまう。
中村
ある構造をもたなければ生きものとして成立しないという点ではゲノムと同じということですね。
茂木
そのような意味では人間の脳も昆虫の脳も多くの共通点がある。これは賭けてもいいんですけども、猿の脳で見つかったニューロンは、大抵の場合昆虫の脳でも見つかる。
中村
すごい。ゲノムは、カンブリア紀以前のところで、ほとんど全部準備されていることがわかってきています。その後増えたり、組みかわったりはしていますが(関連記事:生命誌29号「遺伝子の爆発と動物の爆発:宮田 隆」)。
茂木
ある反応特性(註1)をもったニューロンは、実はずっと変わっていなかったりするわけですね。組み合わせが違うだけで。
中村
確かに同じものですね。ゲノムは最初の生物にあったもの以外のところから来ようがない。それが、繰り返し増える。今まで通り使うところもあるけれど、余裕ができたところは別の使い方もできる。そこで変化が起きる。その繰り返しをやってきたのであって、全く新しいものというのは、実際問題として、ありようがないわけです。
茂木
そういう意味でいうと、ニューロンは全部同じですからね。
中村
多分、多細胞生物になった時に基本構造はできてしまって、それの複雑化ですね。中枢神経系は前に集まったほうがいいから集まるとか。それを作っている遺伝子もそんなに新しいものは出てきていないわけです。神経系に関する遺伝子が、節足動物と脊椎動物でほとんど同じですからね(関連記事:生命誌8号「ニワトリの遺伝子をもったハエのかたち:梅園和彦」/ 生命誌11号「キメラ胚で脳に迫る:ニコル・ルドワラン」)。神経の走り方も昆虫と人間は全然違うように見えますが、背中とおなかがひっくりかえっているだけなんです。昆虫はおなか側に神経があって人間は背中側。だから、人間がブリッジして歩けば、昆虫になるわけです。
茂木
遺伝子だと、組み合わせで全然違うものが出来るということが何となく納得できるけども、脳は、あまりそういう目では見てないかもしれないですね。ニューロンという単位が組み合わさっているだけでなく、ニューロンの反応特性も、実は組み合わさっているのかもしれないですね。
中村
新しいものの誕生は、やはり外からの刺激、情報の影響を受けるわけで、ゲノムよりも脳の方が外の影響が強いとは思いますが、中の構造の特性としては、同じように考えられるかもしれませんね。
茂木
人間や猿の脳、特に前頭葉は特別なものだという思い込みがあまりにも強い。でも、蟻や蜂の論文を読んでいると、これ猿と同じじゃないかと思うニューロンがある。例えば、猿で最近見つかったニューロンは、あるタスクをやらせる時に、やらないという選択をすると不味い餌が与えられ、やって正解だった時だけ、美味しいもの、例えばナッツなどが与えられる。ただし、やってみて失敗した時は何ももらえない。要するに、猿は、成功しそうだという確信が持てて、いけそうだと思うとレバーを押すのだけれど、いけそうもないと思うときはむしろ何もやらないで不味い餌で我慢する。 このようなニューロンは、自分の内的な状態をモニターしているから、非常に高次な機能だと言うわけですよ。しかし、似たようなニューロンは、昆虫にもあるに違いない。何かができそうかどうか判断する機構なんて、あるに決まっているじゃないですか、生物として。 地中海にいる蟻を調べた例があって、迷路学習させるんです。蟻にはホームベクターというのがあって、巣がどっちの方向かわかっている。餌をいっぱい食べて、巣に戻りたいという蟻は、迷路が巣に向かう方向だとやる気を起こして学習するんだけれども、巣の方向に向いていないと、どうでもいいやと思うらしくて学習しないという、非常におもしろい実験があるんですよ。
中村
生意気(笑)。
茂木
猿や人間で言うところのモチベーション。高次なことに思えるけれど、実は昆虫にもある。でも考えてみればそんなの当たり前ですね。
中村
それはそうですね。巣のほうに向いてないとやらないぞというとちょっと生意気に聞こえるけれど、無駄なことはやらないよというだけ(笑)。
茂木
もちろん、解釈として人間中心な解釈をしているけれども、機能としてはあまり変わらないと思いますね。
中村
あまり無駄なことをしたら、生きていけないものね。
茂木
確かに、人間は言語を使っているという点は明らかに違う。しかし、今まで猿で発見されている「高次」と言われているニューロンは、実は、他の動物にも全部あるんじゃないかと思う。これは仮説ですけれど。もちろん人間だったらドーパミン系に相当するものが蟻では違うニューロンで担われているという違いはあると思うんですけれど。
中村
ゲノムと重なりますね。生物系を構築する基本的なやり方は既存のものを上手に使う(関連記事:生命誌12号「クリスタン遺伝子にみる眼の便宜主義:森正 敬」)ということですね。F.ジャコブというフランスのノーベル賞学者が、生物は鋳掛屋と言っている。この言葉は若い人には通じないので、ポップアートかしら。脳も多分ポップアートで、勝手にコラージュしているのでしょう。
茂木
なるほど。ポップアートですか。遺伝子は随分長い間使っているけれど、動物は全部神経系で動いていますから、神経系もずっと使っているわけですよね。
中村
多細胞になった時から神経系があるわけだから。
茂木
猿の前頭葉にあるのは、どうも他にもありそうだ、何でだろうとは思っていましたけれど、そう考えると確かに納得できる。
中村
ゲノムを見ている者としては、素直にそうだろうと思える。とにかく生きものは、既存のものを工夫して使っていく。しかも、時々変化が起きるので、その変化を巧みに活用していく。そういうやり方できたわけですね。
茂木
こういうことですね。ダーウィン以来の進化論で、まずすべての生物はつながっていることが常識になって、その後DNAを調べると、完膚無きまでに、人間だって同じだとなった。このような知識は我々も常識として持っているんですが、実は神経系に関しては、それに相当する考えの変化は起こっていない。神経系における進化の本質はまだ明確につかまえられてないということですね。
(註1)反応特性
脳にはさまざまなニューロンがあり、いずれも環境から受けた特有の刺激に反応する性質をもっている。これを反応特性という。たとえば、サルの運動前野近辺に見つかったミラーニューロンは、自分がある行為をしても、他者が同じ行為をするのを見ても、同じように活動する。ちょうど鏡に映したように、自分と他人の行為に伴って活動するので、「ミラーニューロン」と呼ばれる。電気生理学的実験によって、さまざまな反応特性をもったニューロンが見つかっているが、脳全体の中でのこれらの役割を明らかにするのは容易ではなさそうである。
6. 脳研究を生物学の視点から見る
中村
 神経系の進化は、まだ勉強中ですが、茂木さんとお話していてその感を強くしました。生物の臓器の1つですから、身体全体がとっているやり方の外にあるはずがない。けれども今はヒトの脳に特殊性を持たせ、それがコンピュータとつながって、意識や学習という高次機能に集中し、昆虫にはないぞという研究スタイルができ上がってしまっている。それが脳の本質ではない、生命誌の中での脳研究が欲しいという気がして仕方がないんです。
神経系の進化は、まだ勉強中ですが、茂木さんとお話していてその感を強くしました。生物の臓器の1つですから、身体全体がとっているやり方の外にあるはずがない。けれども今はヒトの脳に特殊性を持たせ、それがコンピュータとつながって、意識や学習という高次機能に集中し、昆虫にはないぞという研究スタイルができ上がってしまっている。それが脳の本質ではない、生命誌の中での脳研究が欲しいという気がして仕方がないんです。
茂木
生きものは、実際に野外で見ないとわからないと思うんですね。その実態は、なかなか言葉、イデオロギーにしにくいものですね。学問のディシプリンとしてのイデオロギーになりにくい。
中村
そうですね。実はDNAでも10年前に私が昆虫で研究しようと考えた時は疑問視されましたから。学問ではないという反応でしたが、もう今は変わりました。脳についても同じ流れはできると思うのですが。子供たちはコンピュータも結構だけれども、とにかく生きものを見て欲しい。これから生物学は盛んになるでしょうけれども、生きものを見ていない人が増えてくるとどうなるのでしょう。学問としてのおもしろさが、その基本がない状況でうまく伸びていくかどうか。
茂木
昆虫採集ができなくなってしまっているのも大きいですよね。
中村
採集はすればいいのに。それは自然を知ることで、壊すことではないという認識で。生物学は日常性の大きな分野ですから、どなたとも共有できると思って、研究館を始めたのです。研究所との大きな違いは実験室での研究も自然を意識していることです。
茂木
僕だって、小学校1年の時に、短い竿でゴマダラチョウを採ろうと一週間山に通ったこともあります。あれは人生でも最もインパクトのある体験の1つだったなあ。
中村
意外ですね(笑)。今まで茂木さんは、コンピュータで全部わかっちゃうぞ派かと思っていましたから。
茂木
そういうのを出しにくい文化風土があるんじゃないかな。脳とか認知の研究では。
中村
10年経ったら変わりますよ。分子生物学の中で「隠れ虫屋」という呼び名があって、虫が好きな人が大勢いるんだけれど、それを表だって言ってはいけないという風潮だったのです。ところが、今は「私は虫屋だ」というのがむしろ流行っているでしょう。その先鞭をつけたのは、研究館のオサムシ研究だったと思います。生物学の本流と虫好きが結びついた。それで、「隠れ虫屋」さんたちが元気になっているわけです。脳でも認知をやっていらっしゃる方の中の、「隠れ生物屋」さんが10年後には、生物学を表に出すようになると予言します。
茂木
なるほど。いい予言ですね。
中村
その第1号が茂木さん(笑)。
茂木
神経系の分野で虫とかいうと、なんとなく低級なことをやっているような印象がある。言語とか意識とかいうと「おお、立派だ」とか(笑)。
中村
言語と意識と虫はつながっているという話にしなければいけません。
7. 科学と芸術
茂木
最近、芸術作品に接しての感動というのは、案外動物界全体につながる原始的なものではないかと思ったことがあります。バッハの音楽のあとの感動は、ひょっとしたら動物にもあるのかなという。夕陽を見ている時にそういうことを思っているのかなと思った瞬間に、「ああそうか」と、何となくつながったんですよ。
普通、科学というと客観的な真理を発見すると思っているけれど、実は発見するのではなくて、脳の中で勝手につくったものの一部が、たまたま合っているというだけだと思うんですよ。これの良い例は、アインシュタインが一般相対性理論の最終的な方程式を出したのが、確か1915年なんですけども、それまでにいくつもの、でたらめな方程式を論文として出しているんです。それがでたらめというのは後からわかったわけで、最後の正解の方程式だけが意味があるというわけではない。方程式の創造のプロセスに意味があるのであって、合うか合わないかは、本質ではない。そういうふうに考えると、科学は普通、禁欲的に世界の客観的な法則を見いだすことだと思いがちだけど、実は、ないものをつくり出すというところに本質があるわけですね。アートと変わらないし、何もいないところにオバケが見えるというのと、実は変わらないわけですね。
中村
まさにそうだと思います。そういう時に、我々の感覚で「美しい」と思ったものが、大体合っている。科学の法則を示す式など基本的なものは美しい形ですね。だから、人間の基本は、「美しい」という感覚じゃないかとさえ思うのですが。
茂木
そこですごく不思議に思うのは、美しいという感覚は、動物にもあるのだろうかということなんです。バッハでも何でもいいんですけれど、美しい音楽を聴いて、ああ、感動したと思った時に、我々はそれを普通、すごく高度なものだと思っているんだけれど、実はそういう感情は他の動物にもあるんじゃないかという気がするんです。バッハの音楽を聴いて味わうというプロセスはおそらく人間にしかできないものだけれど、その結果感動したという、結果としての感情はむしろ、大脳辺縁系などの古い脳でやっているわけですから(関連記事:「人間の条件 - 脳と言語、そして音楽 -:中田 力」)。動物にもある。動物は違うプロセスで、人間と同じ感動に至るのかもしれない。例えば、朝、太陽が昇るのを見ると、その時に「アーッ」と感動しているのかもしれないですね。
数学的なものは、自然界にかなりあるような気がするんです。有名な例ではフィボナッチ数列。ヒマワリの種の数がフィボナッチ数列になる(関連記事:生命誌24号「生き物と数:上野健爾」)。自然の中に規則的な数列に基づく構造が広く存在する。人間でいうと、サヴァン(註2)と呼ばれる人たちが、天才的な数学的能力を示すことがある。そのような能力が何で健常児にはないのかというと、むしろ抑制してしまっているからで、サヴァンの人たちは抑制がとれて、原始的なものが出ている。考えてみたら視覚的にそれが何かがわかる能力は潜在的にはあるのではないかという説もある。われわれが何かを見て、それが例えば机と判るには、その背後に膨大な計算を必要とする。われわれは、普段はそれと気がつかないでやっているわけですね。サヴァンの人たちは、そのプロセスに直接アクセスできるので、ああいう天才的な能力を発揮するのではないかという説がある。ものを見る能力は動物にももちろんあるわけで、そう考えると、数学的な能力はむしろ動物界にこそ普遍的にあるのかもしれない。そもそも高度なものと原始的なものというものの区別自体どうなのか。少なくとも、原始的なものが最初にあって、そこから高次なものが出てくるというのではないと思うのです。
(註2)サヴァン
ダウン博士(ダウン症候群の研究で著名なイギリスの精神科医)によって命名され、氏によって「精神薄弱でありながら特殊な才能をあらわす子どもで、その才能はきわめて高度に達することがある」として定義された。ダスティン・ホフマンが主演の映画「レインマン」では、彼が演ずる自閉症の患者が特殊な能力(散らばったマッチを一瞬の内に数えるなど)を発揮する。これがサヴァンの症状である。一度聞いただけの音楽を完璧に暗記したり、日付から即座に曜日を答えたり、数桁のかけ算を一瞬で解いたりと、その天才的能力は多岐にわたる。
8. 生物とは何?
茂木
 計算するためには意識が必要であると言う人たちがいるけれど、少なくとも人間の脳については、人間の意識を構成している要素の最低限必要なセットみたいなものを考えると、とても計算しているから意識があるとは言えない。サヴァン能力に見られるようにむしろ計算過程の本質は無意識であるとも考えられる。いずれにせよ、有機体として脳を見るべきで、要素を取り出しても、おそらくそこには意識が通っていないだろうと思います。
計算するためには意識が必要であると言う人たちがいるけれど、少なくとも人間の脳については、人間の意識を構成している要素の最低限必要なセットみたいなものを考えると、とても計算しているから意識があるとは言えない。サヴァン能力に見られるようにむしろ計算過程の本質は無意識であるとも考えられる。いずれにせよ、有機体として脳を見るべきで、要素を取り出しても、おそらくそこには意識が通っていないだろうと思います。
要するに、全体として意識があるわけで、特定の部分を取り出してもだめなわけです。人工生命が生命だと思っている人は生物学者にはあまりいないと思います。しかし、ある部分だけを取り出して、それをシミュレーションすると、あたかもそれが生命だと思えてしまう。シミュレーションしたものには意識があると言う人たちは、それと同じような間違いを犯しているんじゃないかという気がします。意識の問題は、いろんな意味で生命とパラレルであって、全体性が重要なのです。
コンピュータとのアナロジーで考えてはいけないという理由はまさにここにある。脳は情報処理機械ではなくて、「生きているもの」だということが、非常に重要なポイントだと思うんです。ここでは、歴史性とある特定の豊かさを持ったシステムのことを、「生きている」と言っているわけです。「生きている」という言葉以外の、別の記述の仕方が将来、出てくるかもしれないけれど、現実の生命は、今まで我々が作った人工的なシミュレーションないし機械では、まったく足下にも及ばないような複雑なシステムです。少なくとも、その複雑さまで到達するまでは、「生きている」とは言えないと思うし、意識というものも、そこには宿らないと思うんですね。 ただ、原理問題として、じゃあ何でそもそも意識なんていうものがあるのかというところまでいったときに、論理的には石ころ1個にも意識の原始的なものがある可能性は否定できない。一方で、シミュレーションをうまくやりさえすれば、意識が生まれると断言している人たちみたいに、何の根拠もなく断言することは、少なくともできない。可能性はあるけどもできない。
中村
脳は情報処理機械ではなくて、生きものだということを再認識する必要がありますね。生命誌の中で脳を考えたいというのは、まさにそのことなのです。
茂木
それがすごく重要なポイントだと思うんですよね。そもそもニューロンは、勝手に自発的に発火する。コンピュータというメタファーで考えると、ノイズは邪魔者で、例外的なもののように思うけれど、そうではなくて、脳にはもともとノイズがいっぱいあって、その上でさらに付加する情報を持っているという感じですね。
中村
自然界というのは大体そうじゃないですか。ノイズがあって、その上で、その時々に意味のあるものがポンと出てくる。
茂木
コンピュータとは全く違うということですよね。ところがシミュレーションという概念が出てきちゃった。チューリングマシン(註3)が、どんなものでもシミュレートできる万能性を持っていることが証明されてしまった。そこら辺からおそらく人間が毒されちゃったんですよ。シミュレーションは大したものだと思っちゃった。でもそれは、人間の脳の一種の癖に過ぎないと思うんですけどね。 ラングトンが、人工生命をやり始めたきっかけとして、夜独りで研究室にいてゾッとして後ろを見たらライフゲームが動いていたという話がありますよね。あれは別に、ライフゲームが生きていると言っているんではなくて、ラングトンの脳がそういうものに意味を見いだすような癖を持っていたということです。「幽霊の正体みたり枯れ尾花」と同じです。今までに創られた人工生命って、ラングトンのあの最初のエピソードでほとんど尽きていると思うんですよね、厳しい言い方をすると。
中村
生物研究でもゲノム解析が始まって以来、情報がたくさん集まってきて、これをなんとかしなければならないことは確かであり、生物情報学が生まれたのは必然です。その一つにシミュレーションがあるわけですが、今の社会や経済をコンピュータで何とかしようとしてもどうにもならないのと同じで、たくさんのファクターが重なっているときにシミュレーションでどれだけ意味のあるものが出るのかどうかは疑問ですね。
茂木
意味がある問題もあるんだけれど、それは実は生命の本質にはなっていないということですね。
中村
モデルづくりとして、できるところをシミュレートしていくのは、科学の方法論としてあるわけですけれど、本質がどこまでわかるだろうかということですね。
茂木
考えてみると、ポアンカレ(註4)が天体問題は一般に予測できないことを示した時にすでにシミュレーションという道具は崩壊したと言ってもよいのではないでしょうか。スウェーデン国王が太陽系が安定していることを証明しろという懸賞を出し、ポアンカレが証明しようと思ったら、証明できなくて不安定だとわかった。シミュレーションというのは、結局、あるところだけを切り取って部分的に再現するものですね。太陽系全体は不安定なんだけども、確かに地球は太陽の周りを規則的に周り続けていますよね。本当は、ほっといたら地球や太陽が飛んで行っちゃうような場合もありますよと言うほうが、重要なんだけども、そっちは実はシミュレーションで手に負えない。言語なんかは典型的な手に負えない問題なのではないでしょうか。
中村
生命もそうですね。モデル科学は非常に有効なわけだし、そういう意味でのシミュレーションの有効性はあるけれど、シミュレーションが答ではないということですね。
茂木
シミュレーションは、どんなものだろうとみな概念的な部分の表現にとどまりますね。
中村
昔、茂木さんのお仲間の北野宏明さん(関連記事:生命誌16号「コンピュータでつくる生物モデル:北野宏明」)が細胞のコンピュータシミュレーションを始められた頃、センチュウの細胞系譜がわかってきた時だったので、それを踏まえたシミュレーションができないだろうかと、ソニーの研究所へ行ってお話したのです。コンピュータと生物実験の現場がつながらないかと思って。今システムバイオロジーとして展開していらっしゃるのがどう進んでいくか、楽しみです。
茂木
やはり私たちは様々な形而上学からまだまだ開放されるべきなのだと思います。ホムンクルスという人工生命体をガラス瓶の中で作る。やがてガラスが割れてホムンクルスはエーゲ海へ投げ出されるという話をゲーテが『ファウスト』で書いているのだけれど、あれはすごい先見の明があったと思う。「人工的なものは閉鎖した空間を必要とするが、自然にとっては全宇宙と言えども十分ではない」というすごく美しい言葉を残しています。我々は脳を、あたかも人工的な閉鎖空間の中に置いているような研究の仕方しかしていないけど、本当はガラス瓶から割って外に出さなきゃいけない、というふうにずうっと前から思ってました。
中村
生命誌は生命科学研究をガラス瓶の外に出したいという願いから始めたものなのです。コンピュータを手段として使っていらっしゃる茂木さんからそういうお話を伺えてとても心強い。またお話させて下さい。
(註4)チューリングマシン【Turing machine】
1936年にイギリスの数学者であるチューリングが考案したコンピュータ・モデル。一本のテープと、そこにデータを書き込んだり読み出したりするヘッドからなる。チューリングマシンには、あらかじめいくつかの状態が設定されており、マシンの動作は、この状態とヘッドから読み出されたデータを照合することで決定される。動作には、ヘッドの移動、データの書き込み、状態の変更があり、一つの動作が終わると、次の動作が同じようにして行われる。この一定の手順を繰り返すことによって計算が進んで行き、解が存在すれば、理論上はすべてチューリングマシンがこの解に到達する。現在のコンピュータも、チューリングマシンの原理に従っている。
(註3)ポアンカレ
カオスの問題を最初に提起した人物。1887年、スウェーデン国王が「太陽系は定常な安定した存在であるか否か?」という懸賞問題を出した。これに対して、ポアンカレは、『三体問題と運動方程式について』という論文の中で否と答えた。重力法則のもとにある二物体からなるシステムは周期的な運動をするが、三物体以上だと、周期性を示さずカオスになってしまうことを示したのだ。三物体以上の関係は、初期条件のわずかな違いで大きく違ってくるため、予測することができないのである。
茂木健一郎(もぎ・けんいちろう)
1962年東京生まれ。ソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー。東京大学理学系研究科博士課程修了後、理化学研究所、英ケンブリッジ大学ポスドクを経て現職。クオリア(質感)を重視して、脳と心の問題を哲学的また技術的に解明しようとしている。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)
.jpg)
.jpg)