RESEARCH
自然界に捕食者が存在することの意味
自然生態系は安定している。もちろん現代では開発による生息場所の破壊は少なくないが、たとえば深い森にすむ蝶を例にとると、わたしがこどものころに稀だった種は今も稀で、普通種は今も普通種である。これは偶然だろうか? あるいは自然のバランスが働いているのだろうか?
まずはここから…リサーチのツボ
1.天敵は生態系を安定させない?
生態学者は生態系の安定性をもたらす機構について長年にわたり探求してきた。長い間、天敵による制御とされてきたが、近年の探求の結果は意外なものだった。野外での個体数の変化とそれをもたらした死亡要因を詳しく調べたところ、天敵による捕食が自然のバランスをもたらすことはめったにないことがわかってきたのである。餌種が増えた場合でも天敵はその増加を抑えるほど効率よく捕食することはなく、逆に餌種が減ったからといって襲うのを控えたりはしない。結局、天敵は餌種の個体数を減らしはするが、個体数の調節はしないということが分かった。
現時点の研究者は、生きものたちは、個体数が増えると餌条件が悪くなるので過密をさけるように移動・分散するのが常で、その結果、個体数の調節が空間的に生じるのだと考えている。つまり、自然界では食うものと食われるものの関係によってバランスが保たれるという一般に流布している考えは、ほとんどの場合誤りだということになっている。しかしそれは本当だろうか? わたしは、ここで改めて、専門家の考えにも大きな見落としがあるのではないかと疑っている。
2.天敵の効果を示唆する根拠
外国から新たに侵入した昆虫が、侵入先で大発生して害虫化することがしばしばおきる。しかし侵入種が害虫化するのはたいてい市街地や農耕地など、人手が入った人工的な環境であり、森の奥深くで侵入種が大発生することはめったにない。これは自然が豊かなところでは、そこになんらかの天敵抑制効果が存在することを示唆している。また猛威をふるった害虫も、侵入からある程度の時間が経つと、いつのまにかおとなしいただの虫になるという現象がみられる。たとえば、戦後大発生して街路樹を丸坊主にしたアメリカシロヒトリは、今ではむしろめずらしい虫になっている。そして現在、アメリカシロヒトリにはたくさんの天敵がいる。
さらに、侵入害虫に対して原産地から天敵を導入することで、防除に成功した例がいくつもある。ヤノネカイガラムシは幕末に中国南部から日本に侵入し、あっというまに全国のミカン園に拡がり大害虫となった。しかし、1980年代に中国からヤノネカイガラムシの天敵である寄生蜂を導入したところ、個体数は激減した。現在では寄生蜂とヤノネカイガラムシは、共に細々と安定的に生きながらえている。これは天敵が自然のバランスをもたらすという直接の証拠である。
このように天敵の効果は経験的事実としては明らかなのだが、実は、天敵が餌種の個体数を制御するという仮説の、野外での検証とはとても難しい。なぜなら野外では、天敵の効果と移動・分散の効果とが同時に起きるので、これを分けて評価することができないからだ。
狭い実験空間に餌種と天敵を同居させるという方法を用いた結果は、天敵の強い効果を示している。すなわち、天敵が少ないと被食者は無尽蔵に増え、天敵が多いと被食者は絶滅するのである。しかしこのような実験は、狭い空間に閉じこめたことの不自然さが常に問題になる。大切な移動や分散ができないではないかというわけだ。この問題を回避するには、移動分散が生じない孤立した生息場所で調査をすればよい。しかしそう都合のよい調査地はなかなかみつからない。
3.2種だけで成立している捕食者-被食者関係
15年前、わたしはインドネシアのボゴール植物園でダイフウシ(漢方薬の原料となる果樹)の害虫であるダイフウシホシカメムシの生態を研究していた。ある時、採集した標本に、体色が微妙に異なるものが一匹混じっていることに気づいた。よく調べてみると、似ているのは見かけだけで、触角、腹、脚などの形や長さがまったく違う。どうやら擬態した別種らしい。そのままいっしょに飼っていたら、ある日それがダイフウシホシカメムシの頭に口吻を突き刺して体液を吸っていた。長期間にわたり観察した結果、幼虫から成虫までのすべての発育段階でダイフウシホシカメムシだけを食べるスペシャリスト捕食者であることが判明した。この捕食者は新種であることがわかり、コネチカット大学のシェーファー博士によりRaxa nishidaiと名付けられた。(正式な和名はないが、仮にニシダホシカメムシとしておく)

(図1) ボゴール植物園(インドネシア)
熱帯アジアを代表する植物園の一つ。建物は旧東インド会社官邸。
植物園は閉鎖空間ではないが、ダイフウシの木は野外とは隔離されている。さらに2種のカメムシはともに飛べないので、他の生息場所との間で移動・分散は生じない。したがってここならば、移動分散の効果を除外して天敵が餌種の個体数を制御しているかどうか検証できるに違いない。面白い結果を期待して研究を始めてから10年、わたしはカメムシの生態を追い続けた。

(図2) ダイフウシホシカメムシ(右)を襲うニシダホシカメム
ダイフウシホシカメムシに他の天敵は存在せず、ニシダホシカメムシもこの1種だけを食べて生きている。
4.天敵の存在と捕食回避のコスト
通常の状態では捕食性カメムシ(ニシダホシカメムシ)の個体数はごく少なく、食べられて死ぬカメムシ(ダイフウシホシカメムシ)は全個体数の数%にすぎない。つまり食物連鎖の関係としては大した意味を持っていないように見える。しかし、人為的に捕食圧を上げて、ダイフウシホシカメムシにおきる変化を追跡したところ、実は捕食者は被食者の生活に重大な影響を与えていることが分かった。先に結論をまとめてしまうと、ダイフウシホシカメムシは天敵から逃れようと必死になり、繁殖を犠牲にしていたのだ。捕食圧の増加に伴う行動の変化を詳しく見ていこう。
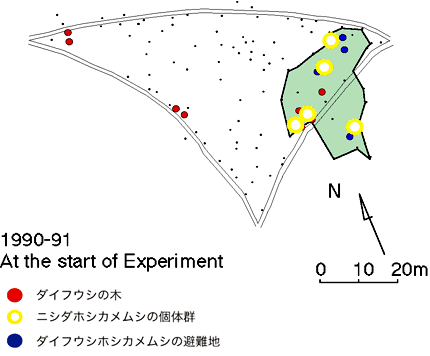
(図3) 実験開始時(1990-1991年)の生態系の様子
実線で囲った領域は、ダイフウシホシカメムシの生息範囲を示している。この状態から、ダイフウシホシカメムシを間引くことで相対的に捕食者の個体数を増加させた(捕食圧の増加)。逆に、ニシダホシカメムシを間引くと捕食圧の減少となる。
[1] 滑空能力の向上
ダイフウシホシカメムシは木の梢で眠り、朝になると地上の餌場所(落ちて腐った果実)へと歩いて出勤し、夕方ふたたびねぐらへ帰る。この朝夕の出勤時、木の根元には捕食者(ニシダホシカメムシ)が集結している。ホシカメムシは重力に逆らって飛ぶことはできないが、飛翔筋が発達した個体は滑空して地面への激突を避けることができるので、滑空できる個体は少なくとも出勤時に襲われることはない。
通常の捕食圧ではほとんどの個体は滑空しない。滅多に捕まらないからである。しかし捕食圧を高めると、多くの個体が滑空出勤し始めた。滑空できる個体とできない個体を解剖して調べると、滑空個体は胸の飛翔筋が発達しているが生殖巣の発達が悪く、一方、滑空できない個体は飛翔筋は痕跡しかなく生殖巣が発達していた。また同一の個体でも、成虫になった直後には飛翔能力が高く、性成熟とともに急速に低下することが分かった。実はこのカメムシは飛翔筋をとかしてその栄養分を生殖巣の発育に転用しているのである。若い間は滑空し、性成熟するとその能力を失うかわりに速やかに生殖を行うという形で生存と繁殖のバランスを保っているのだ。それが、繁殖を犠牲にして滑空し始めたのである。

(図4) 飛翔個体の判定
カメムシは左右どちらかの前翅が上になるように閉じる。どちらが上になるかは、翅を開いてたたむごとに替わり、その確率は半々である。したがって、ある個体を捕まえて背中に横一直線の白線を描いて放し、次に見つけた時にその個体の背中の白線がとぎれていれば、その個体が滑空を行い翅のたたみ方が替わったことを意味する。
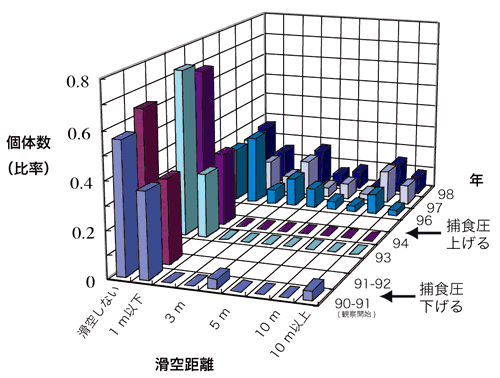
(図5)捕食圧で変化する滑空個体の出現頻度
観察を開始した年は、ほとんどの個体は滑空せず、滑空したとしてもせいぜい1m以下であった。1991年に捕食圧を下げると、飛ばない個体がさらに増え、わずかに存在していた長距離滑空個体が全く見られなくなった。1994年に捕食圧を上げると、オスで5割近く、メスで3割近くの個体が滑空を始めた。なおこのグラフはオスを調べた結果であるが、メスでも同様のことが起こった。
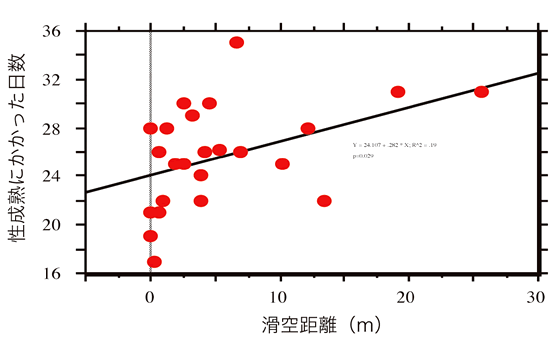
(図6) 滑空能力と成熟にかかる日数の関係
捕食圧を上げた結果、滑空を行う個体が増加した。このときメスの個体で、滑空能力と性成熟するまでに要した時間を調べた(グラフの赤点が1個体を表す)。滑空しない個体(滑空距離が0 m)の場合、成熟までの日数が16~28日の間であったのに対し、滑空する個体はそれが20日以上となり、成熟までの平均日数は滑空距離と比例関係にあった(右上がりの直線)。
[2] オスによる交尾相手メスの警護の減少
ダイフウシホシカメムシは交尾の後、1週間近く交尾姿勢のまま過ごす。これは交尾後警護とよばれ、カメムシではよく見られる現象である。昆虫では一般に最後に交尾をしたオスが受精で有利となるので、オスによる警護は自らの父性を高めることになる。これはそのための適応と考えられている。
捕食圧を高めたところ、オスはメスをあまり警護しなくなった。調べてみると、交尾ペアが捕食者に襲われたときにはメスよりもオスが殺されることが多かった。捕食者が接近すると、単独のときにはオスもメスも捕食者の接近とは反対の方向へ逃げる。しかし交尾姿勢のときには一瞬引っ張り合いが起きたあと、体の大きなメスがオスを引っ張って歩く。捕食者は後から追いかけるので、捕まるのはオスとなりやすい。捕食者は一度に二匹とも殺すことはなく、オスが食べられている間にメスは交尾器をはずしてうまく逃げおおせる。

(図7)ダイフウシホシカメムシの交尾
ダイフウシの実が地面に落ち、果肉が腐って露出した種子に群がるダイフウシホシカメムシのペア。体の大きい方がメス
オスからみると、警護するかどうかは父性を高める利点と捕食リスクとのかねあいで決まる。捕食者が多くなるほど警護のリスクが高くなるので、メスを守らなくなるというわけである。このあたり、呆れるほどドライで合理的だった。しかしこれは同時に自分が父親になれる可能性を低くしていることでもあり、集団としては繁殖が減少する。
[3] 採餌個体の減少
捕食者が増えると、餌場に出勤してこない個体が増えた。また地上で採餌していても、捕食者に出会うとすぐに手近の木に登ってしまった。そのため採餌しているメスは、捕食者が少ないときにくらべ40%も減ってしまった。採餌の減少は、性成熟の遅れを通じて飛翔筋の持続と生殖巣の未発達へとつながった。これも繁殖の減少につながる。
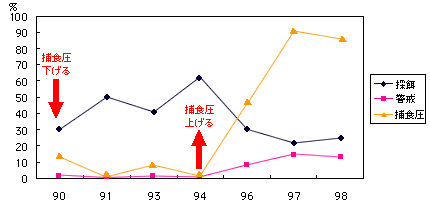
(図8) 捕食圧と採餌時間の関係
捕食圧を下げると採餌時間の割合が増え、警戒行動が低下する。その後、94年に捕食圧を上げると、採餌時間の割合は急速に低下し、逆に警戒行動を多くとるようになった
[4] 天敵不在空間の利用
捕食者が増えると、被食者は次第に餌場から遠い場所をねぐらとするようになった。以前は、地上に降りればすぐに餌場だったのが、通勤距離がどんどん伸びていったのである。捕食者を避けた結果だろう。餌場から遠いねぐらほど未成熟成虫の割合が多かった。
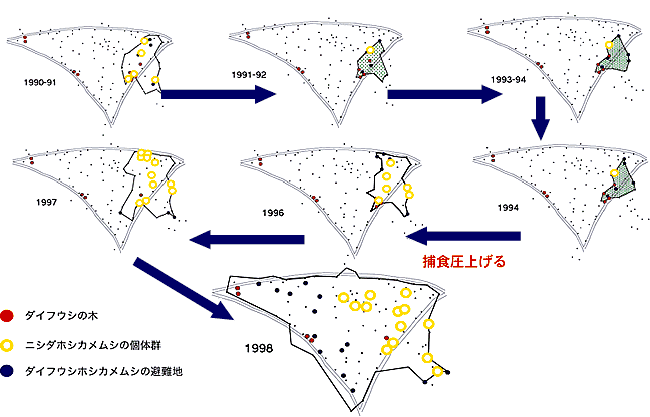
(図9) 捕食圧の操作による生息空間の変化
捕食圧を下げるとダイフウシホシカメムシのねぐらはダイフウシの木の周りに集中する。捕食圧を上げると、次第にねぐらは遠くなった。捕食者を避けて、通勤に不便なところに追いやられたためと考えられる。
1.捕食者の非致死的効果
捕食者を増やしても、被食者は上に述べた捕食回避策をとるため、捕食による死亡率は少し増える程度である。しかし実際には、捕食を逃れた個体も上記の[1]~[4]の過程を通じて大きなコストを払ったことになる。各項目で示したように、繁殖が減少し、全体としては繁殖成功(生涯の産卵回数)が半減していたのである。これは、生態系に対しては、半数が死亡したのと同じ効果になる。
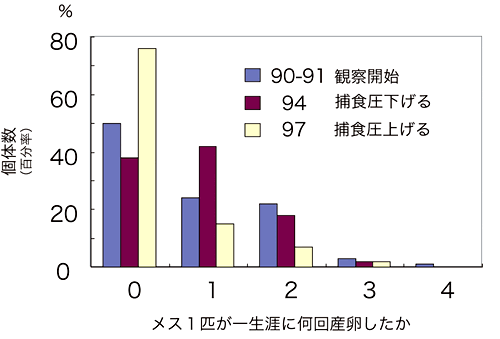
(図10) 捕食圧と繁殖成功の関係
捕食圧が低い時、メスの6割は産卵することができた。しかし捕食圧を上げると、8割近くのメスが生涯に1回も産卵できなくなった。捕食から逃れることができても、結果的には子孫を残すことができなかった個体が大半だったことを意味する。
これまで、天敵の効果はそれがどれだけ被食者を食べたかによって評価されてきた。それは、このホシカメムシではせいぜい数%にすぎない。そこで捕食の影響はあまり大きくないとされてきたのである。しかし現実に生じた捕食死亡率を根拠にして捕食リスクを計算するのは間違いなのだ。低い捕食リスクは食べられる側が必死の対策をした結果であって原因ではない。
非常に危険な捕食者がいたとする。被食者は食べられないように細心の注意を払う。死んでしまってはおしまいだから、過剰と言ってもよいほど気をつかう。一方、食べる方は失敗しても一食抜けるだけだ。すなわち、被食者のほうが失うものははるかに大きい。そこで結局は、捕食者はまれにしか餌となる相手を食べられないというあたりに落ち着く。つまり私たちが今見ているのは、過去の致死的な関係の結果としての非致死的な関係なのである。捕食者が被食者を死に至らしめる(食べてしまう)以外の効果を「捕食の非致死的効果」とよぶ。これは、最近になってようやく注目を集めるようになった見方である。
6.かんじんなことは目に見えない
サン・テグジュペリの童話「星の王子さま」の中で、知恵者のきつねは「かんじんなことは目にみえない」ことを説いた。自然における天敵と被食者の関係も同じではないだろうか?
これまで生態学者が思い描いてきた捕食者は、いわばゴルゴ13のような一撃必殺型だった。しかし現実の捕食者は、実にどんくさい。捕食性カメムシ(ニシダホシカメムシ)はせいぜい数百回に一度くらいしか捕食に成功しなかった。食べられる立場にあるカメムシの場合、餌場でオスが見張りをしている。集団の中の一匹が捕食者の接近に気づいて逃げ始めると、まわりの個体もなだれをうったように一斉に逃げる。こうした状況で捕まえるのは並大抵のことではない。しかし餌となるカメムシが自分と同じくらいの大きさなので、一匹捕らえればかなり満腹になる。しかも捕食者は飢えに強く、たまに捕食に成功する程度で充分生きていけるようになっている。
捕獲がへたくそな捕食者のせいで、被食者はしょっちゅう餌場から追い払われ、採餌時間が減り、大きな迷惑を被るのだが、捕まることはめったにないというのが実態である。こうしてゴルゴ13とは対称的な捕食者像が見えてきた。この捕食者像は、被食者が繁殖率の低下という高いコストを払って捕食を回避するゆえに生じた、いわば、被食者の鏡像としての捕食者像である。捕食死亡という形だけに捕らわれていると、こういうはた迷惑な捕食者の影響はみえない。このカメムシの例から、「捕食者はめったに捕食に成功しない」という観点から自然のバランスを見直すことが必要だと思っている。これをさらに検証するため、現在わたしたちは京都の田んぼにいるカエルやトリ(捕食者)が、バッタやイナゴ(被食者)に与える非致死的効果を探っている。
生物間の関係というと、弱肉強食か共生か。この二つの見方がよく出されるが、それほど簡単なものではない。食物連鎖についても、あまりにもおおざっぱな思いこみで作られている。一つ一つの生きものが懸命に生きていく中で、密接な関係が生じバランスがとれていくのが生態系なのである。
西田隆義(にしだ・たかよし)
1988年京都大学大学院農学研究科博士課程修了。京都大学農学部昆虫学研究室助手を経て、98年より京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻植物保護分野助手。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)
.jpg)











