
TALK
島々をめぐる人々の暮らしの知恵
1.現在の中に連綿と続く歴史を語る
中村
生命誌では、自然、生命、そして人間を考えたいと話し合いを続けています。その切り口は動詞で、今年は「めぐる」です。今日が1回目。
印東
責任重大ですね。
中村
今回、印東さんの『オセアニア 暮らしの考古学』(註1)を興味深く読ませていただいたのですが、まず章の見出しがすべて動詞ですね。「島に住む」「作る」「捕る」「育てる」「食べる」。これはお仲間がいたと嬉しくなりました。普通は、学問の本はこういう章立てで書きませんでしょう。ご自分のお仕事を表現なさると自然にこうなったのかしら。そこで大切になさっているものをじっくりお聞きしたいのです。
印東
ありがとうございます。私が考古学資料を使って復元したいのは、現在の中に連綿と続く人々の暮らしの歴史です。発掘から見つかるのは「もの」がほとんどなんですが、それを並べて研究しても、作ったり使ったりした人たちは主語にならない。そこで日常的な動詞を使ってみたらとてもいい感じになったのです。
中村
生命誌とまったくおなじですね。私の場合、人間だけでなく連綿と続く生きものの歴史です。そこから知りたいのは、今、ここにいる自分であり、まわりにいる生きものです。生きもの一つひとつが、38億年続いた固有の歴史を今ここで展開して、生きているのですから、その物語は動詞でないと語れません。バクテリアからはじまる生きものの歴史、オセアニアに住みはじめた人間の歴史。共に今に続いているわけですね。さっそくオセアニアの人々の歴史を教えてください。
印東
人類がオセアニアへ移動した歴史は大きく二つの時期に分かれます。第一の移動は、5~6万年前の狩猟採集で生きていた人々によるもので、オーストラリアのアボリジニやニューギニアのパプア人の祖先と言われています。そのころは最終氷期(註2)のため海面が低下して陸地が拡大していましたが、ウォーレス線(註3)の走るバリ島とロンボク島の間の海峡は深く、地続きになりませんでした。おそらく竹をつないだ筏のようなもので向こう岸へ渡ったと考えられます。
中村
5万年前と言えば人類がアメリカ大陸に広がるよりも前ですね。陸上動物はウォーレス線を越えられず、今もアジアとオーストラリアでは生態系を構成する種が大きく異なりますけれど、人間だけは果敢に渡ったのですね。
印東
 この人たちはソロモン諸島あたりまでしか到達せず、ミクロネシアやポリネシアの島々は無人状態でした。
この人たちはソロモン諸島あたりまでしか到達せず、ミクロネシアやポリネシアの島々は無人状態でした。
第二の移動は、3200年ほど前にはじまります。土器をもち、根栽農耕を行った人々が、やはり東南アジアから太平洋全体に広がって行きました。私はこのオーストロネシア諸語(註4)を話す人たちの歴史や文化などを研究しています。家畜を飼い、農耕と漁労を行う人々が、多様な環境の島々に住んで豊かな物質文化を生み出した様子を、発掘調査から探るのはとても面白いことです。オセアニアでは言語やゲノムの研究も進んでいるので、関連する学問が手をとり合って歴史を復元できるところも魅力です。
中村
オセアニアに暮らす人と言って思い浮かべるのは、アボリジニや大航海時代の西欧からの入植者で、その間に小さな島々をめぐった人たちの話はあまり知られていませんね。でもオセアニア全体で見れば、小さな島で暮らす大多数が、3200年前にやって来た人たちの子孫ということになるのでしょうか。
印東
そうです。3200年前にやってきた人々は、小さな島々を東へとめぐりながら、2400年ほどかけてオセアニアの隅々まで広がりました。太平洋の北東部に位置するハワイ諸島に辿り着いたのはわずか紀元後800年頃。イースター島やニュージーランドに渡ったのは紀元後1200年頃でした。
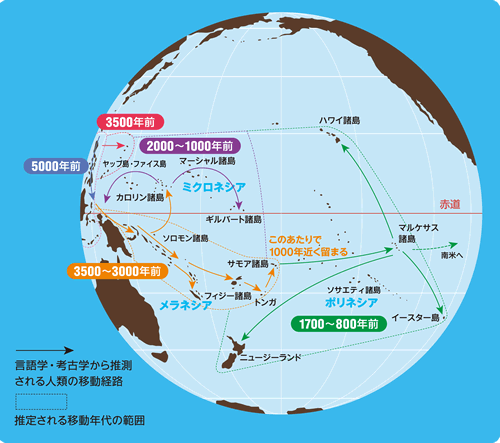
人類移動の地図
中村
人類の歴史の中ではついこの間の話ですね。この移動はどんな変化をもたらしたのでしょう。
印東
基本的には同じような文化を保ちながら移動したのですが、島は一つ一つ環境条件が違うので、それに合わせてさまざまな文化変化が起こりました。とくに、温帯に位置するニュージーランドに渡ったポリネシア人にとって、それまで暮らした熱帯の島々とは自然環境ががらりと変わります。オセアニアの生活になくてはならないココヤシやタロイモなどの栽培植物があまり育ちません。
中村
生活の根本である食が変わってしまうところへ移るのは大変ですね。たまたま流れ着いたのではないのですか。
印東
そういうこともあったと思います。でも、漁をしていて漂着しても子孫は残せません。魚を獲る舟には女性を乗せないためです。意図的に家族や植えつけ用植物や家畜などを舟に乗せて移住したからこそ、その後の人口増加へとつながったのです。
ニュージーランドにはこんな昔話があります。昔、タヒチのクペという航海王が南西へ航海した時に、白い雲が棚引く広い土地を見つけました。自分の島に戻った彼は、「11月に太陽が沈む少し左の方向に行くと大きな島がある」という知識を人々に伝えたのです。そして、十分に移住する準備をした人々がカヌー5隻でニュージーランドへ渡ったということです。
中村
なるほど。移動の原動力は、領土の拡大のためとか、いろいろ考えられますね。好奇心とか・・・そんなこともわかってくるのでしょうか。
(註1) 『オセアニア 暮らしの考古学』
印東道子著。朝日新聞出版(朝日選書 715)
(註2) 最終氷期
氷河時代の周期の中で、地球上の気候が寒冷で大陸の広範囲に氷床が拡大する時期を氷期と言い、およそ7万年前~1万年前まで続いたとされる直近の氷期を指す。
(註3) ウォーレス線
【Wallace’s line】
1868年にイギリスの博物学者A.R.ウォーレスが提唱した生物地理学上の境界線。ボルネオとセレベス、バリとロンボクとの間に引かれ、西側は東洋区の生物、東側はオーストラリア区の生物が分布している。
(註4) オーストロネシア諸語
太平洋の島々および周縁の地域で話されている1000以上の諸語を指す。言語の系統関係についての比較研究により、オーストロネシア祖語という共通の祖先から発達したと考えられている。
2.限られた制約の中で住みこなす
印東
オセアニアは、ニューギニアをふくむ島々からなる南西部の「メラネシア」、赤道から北に位置するパラオ、マリアナ諸島、マーシャル諸島などの小さな島々からなる「ミクロネシア」、さらに中央から東部のハワイ諸島、ニュージーランド、イースター島を結ぶ大きな三角形を描く「ポリネシア」の三つの文化圏からなります(図1)。それぞれの地域に住む人々の外見的な特徴を比べると、メラネシアの人だけは違っていて、皮膚の色は濃く、頭髪は縮れています。この特徴は、メラネシアのソロモンからヴァヌアツ(ニューヘブリデス)やフィジーにかけての人々に共通しています。一方、ポリネシアの人は、むしろミクロネシアや東南アジアの人と似ています。
「ポリネシアの人はいったいどこから来たのだろう」という議論が、18世紀にクック船長がオセアニアを訪れて以来続いていたのですが、その議論に終止符を打ったのが、メラネシアでのラピタ土器の発見でした。この土器が出る遺跡を点々とつないでいくと、島々をめぐる道筋が明らかになってきます。(図2)
メラネシアの島を発掘すると、美しい文様のラピタ土器が、遺跡のいちばん古い層から唐突に出土します。非常に完成された紋様様式をもつ土器なのに、その場所で時間をかけて発達した痕跡が見あたりません。西から土器文化を持って渡ってきた人々が、メラネシアを速いスピードで東へ通り抜け、ポリネシアまで渡って行った移動の様子が浮かび上がります。
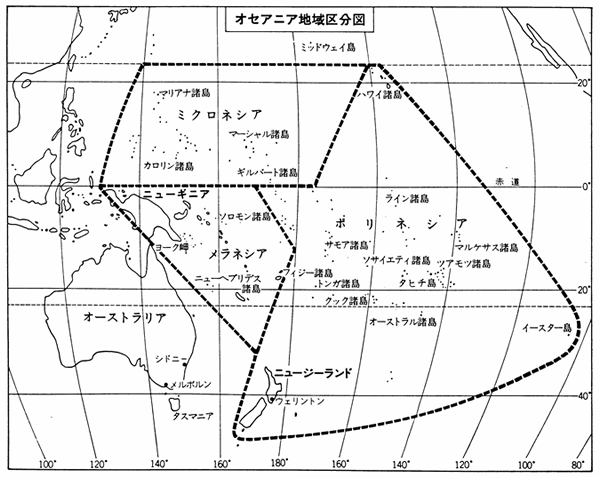
(図1) 「オセアニア地域区分図」
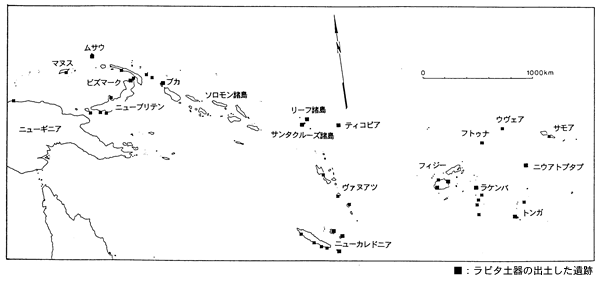
(図2) 「ラピタ遺跡の分布」
中村
なるほど。ラピタ土器の出る遺跡には移動を示すどんな特徴があるのですか。
印東
ラピタ遺跡は海岸沿いか沖合の小さな島から集中して見つかっています。おそらく先住していた第一の集団を避けるために、移動を急いだのかもしれません。無人島だったフィジーまでくると移動するスピードがゆるみ、ポリネシアの西端に位置するサモア、トンガでは1000年も留まってしまう。
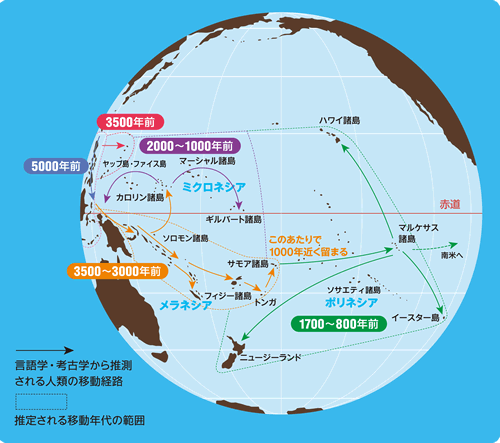
人類移動の地図
中村
気持ちよく暮らせる場所がポリネシアだったのですね。
印東
腰を据えてイモやブタを増やし、人口も増やしていったようです。ラピタ土器が見つかる東限がこのサモア、トンガなんです。
人々の移動と土器の変遷を重ねると、ちょうどフィジーからニュージーランドの東側を南北に走る安山岩線(註5)を境に、地質が変わり粘土の質が悪くなります。そこを越えてサモアへ渡った人たちも、最初は工夫して土器を作りましたが、しだいに土器の質が落ち、最後は土器作りをやめてしまいました。「ポリネシア文化に土器はない」とよく言われますが、実は、掘ってみると昔は作っていたことがわかる。なぜ作らなくなったのかを考えるのも考古学の楽しみです。
サモアやトンガで1000年間過ごした後、温暖化をきっかけにまた東方へ動きはじめます。ソサエティ諸島とマルケサス諸島からは三方向、つまりハワイ諸島、イースター島、ニュージーランドへと一気に広がりました。土器を作るという知識が既に失われていたので、ニュージーランドに住んだポリネシア人(マオリ)は、良質の粘土があるにもかかわらず、土器を作ることはなかった。そこに文化の断絶があるのです。
中村
 連続と断絶、そこから生まれる共通と多様。文化を持っている点、他の生きものと違いますけれど、自然環境に適応し活用して生きていく姿を知ると、やはり人間は生きものだと思いますね。
連続と断絶、そこから生まれる共通と多様。文化を持っている点、他の生きものと違いますけれど、自然環境に適応し活用して生きていく姿を知ると、やはり人間は生きものだと思いますね。
環境が土器作りに向かない島で暮らすための工夫は見られますか。
印東
土器を作れないサンゴ島で使ったのが貝の鍋。トウカムリガイという大きな貝の内側を取りはらい、水と食物を入れて炭火の上で沸騰させます。
中村
なるほど。サンゴ島ならお鍋にするほど大きな貝もありそうですね。ちょっと洒落てますね。
印東
なかなかのアイディアだと思います。それと、鍋を使わないで、熱した石と木の葉だけで調理してしまう、ウムという石蒸し焼き料理法も発達させました。ポリネシアではこの方法で何でも調理していました。石焼き芋と同じ原理です。
中村
生きるために、そこにあるものでやりくりするのが生きものの知恵というのが、最近のゲノム研究での実感ですが、ここでも人間は生きものだと思いますね。
印東
例えば、釣り針は貝で作るのが普通ですが、私のフィールドのミクロネシアのファイス島ではウミガメの甲羅で作ります。
中村
貝はないんですか。
印東
ファイス島は、水没した火山の上にサンゴ礁が発達してできた隆起サンゴ島なので、周囲がすとんと深くなる海に囲まれ、浅瀬もなく貝も少ない。そこで加工しやすく丈夫なウミガメの甲羅を使ったんでしょう。
割れずに完全な形で発掘される例は稀ですが、よく見ると、細部まで丁寧に加工されていて針先には小さく可愛い返しもあり、道糸を結ぶ刻みもある。身近に手に入る素材の性質を知り尽くしているだけに随所に工夫がみられます(写真1)。

(写真1) 「カメの甲羅で作った釣り針」
ファイス島で発掘。右端の大きな物はサメ釣り用、左端は、外形を整えただけの未完成品。
中村
なかなかみごとですね。プラスティックができて、どんな形でも作れてしまうので、便利にはなりましたけれど、身の周りにある自然のものをうまく活かしてきた時のような知恵が無くなってしまいましたね。ある意味で面白さに欠けますよね。
印東
ええ、木の皮を叩いて布(樹皮布)にしてしまうような工夫には頭が下がります(写真2)。

(写真2) 「樹皮布を作る女性」
(トンガ、1996年 印東道子撮影)
ポリネシアに伝わる樹皮布をタパと呼ぶ。クワ科のカジノキの内皮を水で湿らせ10分ほど叩き伸ばす。これを何枚もつなぎ合わせて、腰巻にしたり交換財として使ったりした。
中村
制約があるからこそどう活用するかと考える。正直なところ、私はプラスティックは好きになれないのですが、もうそれ無しで暮らすわけにはいきません。でも制約があった時のような頭の使い方をどこかでする方がよいと思うのです。
(註5) 安山岩線
【andesite line】
環太平洋域の火山帯が噴出する安山岩の分布する地域と、太平洋地域中央部のハワイ諸島などの火山が噴出する玄武岩の分布する地域の境となる地質学的境界線。
3.海を渡り東へ向かう人間の本性
中村
生きものを見ていると、面倒だけれども、私たちの社会づくりにうまく取り入れていかなければいけないと思うことが多いのですが。お話を伺って、人間の社会は、本来、自然と共にあるものなのだと改めて思いました。
印東
 オセアニアで暮らしてみると、私たち人間は、自然界を構成する生きものの一つにすぎないちっぽけな存在だとつくづく実感します。それにもかかわらず、この広い海洋世界になぜ乗りだし、移動し続けたのかという問いは、オセアニア研究者にとって大きな問いであり続けています。
オセアニアで暮らしてみると、私たち人間は、自然界を構成する生きものの一つにすぎないちっぽけな存在だとつくづく実感します。それにもかかわらず、この広い海洋世界になぜ乗りだし、移動し続けたのかという問いは、オセアニア研究者にとって大きな問いであり続けています。
中村
そこが面白い。理屈抜きで、人間って知りたがり屋であり、面白いこと新しいことのやりたがり屋なんじゃないかしらなどと思ったりしますが。
印東
人口が増え過ぎて押し出されたという説もありますが、果たしてそれだけで未知の世界へ赴くものでしょうか。オセアニアは、東南アジアから見れば太陽が昇る東の方角です。太陽の生まれる方角には何かあると考えたに違いないと、私自身は思っています。
中村
なるほど。日出づる処への憧れですか。ちょっと宗教的な面も感じられますね。
印東
もう一つ、オセアニアの赤道周辺は、海流も風向きも東から西へ向いているので、漂着物を見て海の向こうにある陸地を確信したのかもしれません。
中村
それは具体的な手掛かりですね。今は地球上すべてについての地図があるので、どこへ行くかを知ったうえで出掛けますが、島があることすら定かでないのに出かけるわけですから。
印東
オセアニアは地球上で最後の人類の空白地帯でした。その広大な海原へ進出するには、潮の流れや星座を手掛かりにカヌー(写真3)を駆っていく航海術の発達は欠かせません。
それにしても、なぜ海流や風向きに逆らってまで東へ行ったかと考えると、帰りが楽だったからかもしれないとも思えるんですよ(笑)。何にもなければ追い風に乗って手ぶらで帰ってくればよい。

(写真3) 「伝統カヌーで出発」
(ミクロネシア・ングルー環礁、1980年 印東道子撮影)
アウトリガー式カヌーにパンダナスの葉を編んだ帆をあげて帆走をする。
中村
「行きはよい、よい、帰りはこわい」の逆ですね。かなり思慮深いですね。
印東
人々の生活を見るとココヤシがとても重要な資源の一つで、これさえあれば、衣、食、住すべてがなんとかなる。誰かが新しく島を見つけたら、まずココナツを2、3個植えて戻り、実がつきはじめる頃にみんなで渡ったのかもしれません。
中村
「名も知らぬ 遠き島より 流れ寄る・・・」というヤシの実の歌を聴くと、なぜかそこへ行ってみたい気持ちになりますでしょう。オセアニアの島々にもさまざまなものが流れ着いたでしょうね。
印東
太平洋を東へ横断した人たちは、最後には南米にまで辿り着いたようです。南米原産のサツマイモがポリネシアの島々に広まっていたのがその証拠です。
中村
最近、温暖化で地球があやしいから火星へ移住しようと言う人がいますけれど(笑)。困って追い出されるというのはあまりいただけない。でも、もっといい所があるかもしれないという気持ちが新しい所へ行かせるという話は魅力がありますね。
印東
ラピタ文化を残した人たちの住居跡を見ると、家を杭の上に建てていた。つまり、波打ち際でカヌーを横付けできる家に住んでいたらしいのです。
中村
高床式ですか。舟が日常に深く入り込んでいる中で、その延長上で他の島へ行くということだったのかもしれませんね。
印東
現在も、東南アジアには家舟(えぶね)で暮らす人たちがいますが、舟を下りて陸で生活したがりません。人間の移動に関してはまだわからないことがたくさんあり、現代に見られる人間の行動からも学ぶ部分は多くあります。
中村
3200年前の太平洋地域での二回目の人類の移動は、生きものとしてのヒトの行動を基本にしながら、今の私たちにつながる人間っぽい行動という両方の重なりが見られて面白いですね。
4.土器と言葉とDNAで起源を探る
中村
オセアニアの三つの文化圏は、日常の生活でもそれぞれにどんな違いがあるのでしょうか。
印東
基本的には東南アジアから持ち込んだタロイモ、ヤムイモ、パンノキ、バナナなどの栽培植物は三つの地域に共通しています。家畜もイヌ、ブタ、ニワトリがセットとしてオセアニアに持ち込まれましたが、島によっては揃っていないものもありました。特に、ミクロネシアでは一部の島を除いてブタはいませんでした。
中村
ミクロネシアは言葉も他の文化圏と違いますか。
印東
ミクロネシア中東部の言葉はオーストロネシア諸語ですので、ポリネシア語と共通の祖語に辿れます。ところが、西部ミクロネシアのパラオやヤップ、マリアナ諸島などで話されているマラヨ・ポリネシア語は、少し古い時代にフィリピンやインドネシアの影響を受けた言葉で、かなり異なります。
中村
すると一部を除けば、オセアニア全体として言葉はほぼ共通しているということですね。
印東
そうですね。更に大きく見ると、ニューギニアとオーストラリアを別にすれば、オセアニアの言葉は、比較的最近分かれたためよく似ていて、単語もかなり共通しています。クック船長が案内役としてニュージーランドへ連れて行ったタヒチの人は、現地の人々とタヒチの言葉で問題なく会話することができました。
中村
スウェーデンとノルウェーでお互いが自国語で話して通じるのを見て驚いたことがあるのですが、言語の多様性と共通性も興味深いテーマですね。
話を戻して、オセアニアに広がったラピタ土器を持つ人たちは、どこからやって来たかという問いへの答はどうなのでしょう。
印東
東南アジア島嶼部だろうということ以外は未だに謎なんです。というのも、3200年前に精巧な紋様のついたラピタ土器(写真4・図3)がいきなりニューギニア北岸のビスマーク諸島や周辺の島々に出現するのです。徐々に紋様などが発展した痕跡が見つからない。東南アジアからも見つかっていないので、ラピタ文化はオセアニアで発生したと考えた研究者もいたくらいです。でも、土器以外の様々な道具類の系統や家畜骨などから総合的に判断して、ラピタ文化の起源は東南アジア島嶼部に求められます。

(写真4) 「刺突で装飾を施したラピタ土器片」
(サンタクルーズ諸島出土)
実に精巧に描かれた人の顔や幾何学模様は、人々の高い技術と芸術性の証。
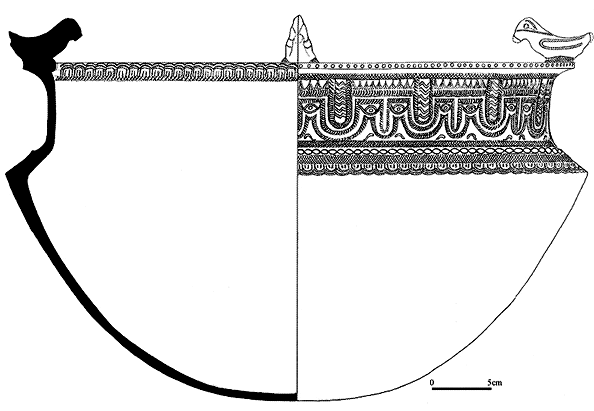
(図3) 「ラピタ土器復元図」
(Bedford & Spriggs 2007より)
人間の顔をモチーフにしており、目が並んでいるのがわかる。口縁に乗っているのは鳥形粘土像。
中村
海に沈んでしまった遺跡もあるでしょうね。
印東
初期の遺跡が海岸低地に多いことを考えるとたくさんあると思います。それと、イリアンジャヤや東ティモールのように調査が進んでいない地域もまだあります。一番可能性があるのはフィリピンからインドネシアの島々だと言われています。
言語学の研究からは、先ほどのオーストロネシア諸語の祖先形態が台湾に先住した高砂族と呼ばれる人たちの言葉に近いことから、台湾、フィリピンと南下したとする有力な仮説が提唱されています。
中村
最近では、DNA解析もなさってますでしょう。それでの起源はどこになるのかしら?
印東
 母方由来のミトコンドリアDNAは台湾やフィリピンとつながり、父方由来のY染色体ではマレー半島とつながるようです。女と男の動きが違っていた可能性が見えてきています。それをどう解釈するかが難しい。東へ移動して広がった集団の中で、メラネシアの島々に残り続けた子孫と先住集団の間でDNAの混ぜ合わせが起こり、数世代をかけて両者の形質的特徴を持った人々がメラネシア内に広がった。その一部は赤道を越えてミクロネシアへ北上したと説明ができるのです。
母方由来のミトコンドリアDNAは台湾やフィリピンとつながり、父方由来のY染色体ではマレー半島とつながるようです。女と男の動きが違っていた可能性が見えてきています。それをどう解釈するかが難しい。東へ移動して広がった集団の中で、メラネシアの島々に残り続けた子孫と先住集団の間でDNAの混ぜ合わせが起こり、数世代をかけて両者の形質的特徴を持った人々がメラネシア内に広がった。その一部は赤道を越えてミクロネシアへ北上したと説明ができるのです。
中村
ミトコンドリアDNAの示す台湾やフィリピンからの南下の流れが、ラピタ土器を持った人々だったと考えられるということですね。
印東
最近のDNA研究では、ポリネシア人に特有のDNA配列が、アフリカ大陸の東にあるマダガスカル島の人々から高確率で見つかったのです。ここでもオーストロネシア諸語が話されているので、東南アジアから東へ向かった人々の他に、西へ向かった人々がいたことが遺伝学的にも裏付けられたと言うことです。
中村
そこまで広がっているのですか。考古学、言語学、生物学、さらに現在の文化を重ねることで見えてくるオセアニアの歴史学。まだまだこれから面白いことを見せてくれそうですね。
5.丈夫な土器と華奢な土器
印東
これまでラピタ文化をもった人々がポリネシアまで渡った様子をお話しましたが、ミクロネシアの西部を見ると、最古のラピタ遺跡より数百年も早くから、パラオからマリアナ諸島にかけて人々が住み着き、別系統の土器を持っていました。私はヤップ島で発掘調査を行いましたが、そこの土器から見えてくる歴史も面白いのです。
中村
えっ。ラピタとはまた違う流れが見えてくるのですか。なかなか複雑ですね。
印東
 ヤップ島は小さな大陸島(註6)で、私がはじめて調査に入った1970年代は、ジェット機が発着しているにもかかわらず、村では男性はふんどし、女性は腰簑をつけてトップレスという伝統的な身なりでした。歴史的に社会が階層化され、土器作りは階層の低い村で行われていました。その中でも、もっともよい土器を作ったことで知られるギタムという村に、まだ土器作りのできる女性がいたのです。これはチャンスと飛び込みました。
ヤップ島は小さな大陸島(註6)で、私がはじめて調査に入った1970年代は、ジェット機が発着しているにもかかわらず、村では男性はふんどし、女性は腰簑をつけてトップレスという伝統的な身なりでした。歴史的に社会が階層化され、土器作りは階層の低い村で行われていました。その中でも、もっともよい土器を作ったことで知られるギタムという村に、まだ土器作りのできる女性がいたのです。これはチャンスと飛び込みました。
考古学では、発掘されたものが当時の暮らしの中でどのように作られ、人々がそれをどのように用いたのかを知りたくても、生活様式が変化している現代社会にはそうそうヒントは転がっていない。ところがヤップでは、過去2000年の間に変化した土器を、発掘した土器片で確かめることができるうえ、それを作った伝統的な土器作りを目の前で見せてもらうことができるのです。
中村
歴史が生き生きと見えてきそうですね。
印東
ヤップ島の土器の特徴は、割れた断面がバウムクーヘンのように層状になっていることです(写真5)。めぐりめぐって変化した土器が、なぜそんな変わった特徴を持つようになったのかを解き明かしたい。でき上がったものだけでなく変化の過程で作られた土器片や、土器作りに利用された粘土の性質も見たかったのです。
そこで三つのストラテジーを考えました。まず考古学的な発掘、つぎに女性の土器作りを観察、さらに土器作りに必要な粘土や砂など、どんなものが利用されてきたのかという環境調査です。

(図1) 「ヤップ島土器片の断面」
歴史時代まで作られていた断面が特徴的な土器。断面が層状の土器はきわめて珍しい。
中村
なるほど。もの、人、自然の三つから探ることで全体を捉え理解を深めようという考え方、生きものを見ている立場からもとてもよくわかります。
印東
ヤップ島の女性の土器作りには変わった特徴がたくさんありますが、いちばん特徴的だったのは、粘土で形を作った後、ゆっくり時間をかけて乾かすことです。フィジー島などの土器作りでは、形を整えた後、一週間と置かず焼いてしまうのですが、ヤップ島では3~4ヶ月かけて小屋の中でゆっくり乾かします。それなのに、火にかける直前に水で濡らしたのにはびっくりしました。せっかく時間をかけて乾燥させたのに、湿らせて火の上においたのですから・・・。実はこの水分から発生する水蒸気の圧力が、層状の断面を作っていたことがわかったのです。詳しいことは省きますが、丈夫で壊れにくい土器にするには砂を混ぜて高温で焼く必要があります。それに適した砂がないヤップ島では独自の工夫を生み出し、断面が層状の土器が生まれたのです。
中村
材料と、作り方と、環境条件という三つの条件が重なり、必然的に生まれたものとしての土器、人間と自然の関係の重要性を見せてくれていますね。
印東
ヤップでいちばん古い地層から発掘される最初期の脆い土器は均質性が高く、先ほどのラピタ土器とおなじように細かい石灰質の砂が混ざっていました。その後、技術的な改良を試みたかのように多様な土器が出土し、試行錯誤していた様子もうかがえます。最後に層状の丈夫な土器が作り出され、再び均質性が高くなりました。このヤップに特有の丈夫な土器は周辺の島々でも発掘されています。
中村
島と島の交流があったことを示しているわけですね。メラネシアのラピタ土器もやりとりされていたかもしれないと思うのですが。
印東
そうですね。でも、手間ひまかけて紋様を施したラピタ土器がやりとりされた背景と、紋様もなく形も一種類しかない実用的なヤップの土器がやりとりされた背景はかなり違っていたでしょう。
中村
ヤップの土器とラピタ土器では、まったく違う歴史と意味をもっているということですね。
印東
 ラピタ土器でも紋様のあるものは1割以下しか存在しません。紋様を施すのに要する時間や手間などを考えると、作り手側に交易に使う意図が伺える。それに対してヤップでは実用土器として作られ、サンゴ島民側の求めに応じて交換される。
ラピタ土器でも紋様のあるものは1割以下しか存在しません。紋様を施すのに要する時間や手間などを考えると、作り手側に交易に使う意図が伺える。それに対してヤップでは実用土器として作られ、サンゴ島民側の求めに応じて交換される。
手の込んだ紋様のラピタ土器が作られた期間は長く見積もって100年程で、急速に簡単な紋様や無紋の土器に変わっていきます。おそらく新天地で暮らしはじめた人々は、生活が安定するまでの間、他の集団から援助や物資をうけ、紋様をつけたラピタ土器と交換したのかもしれません。植えつけた作物や家畜が育ち、新しい土地で自立して生活できるようになると、集団間の絆が薄まるとともにラピタ土器の紋様も簡素化し、無紋化していきました。
もちろん別の解釈もあって、例えば「負け犬仮説」をおっしゃっている斉藤成也(註7)さんは、出て行った負け組から勝ち組の母集団への捧げ物ではないかとおっしゃいます。でも私には、彼らが負け犬とは思えません。むしろ冒険心に富んだ人たちだと感じています。新しい島を発見して手つかずの資源を占有できる魅力は大きいでしょう。負け犬仮説よりは、新天地仮説のほうが夢があって、私は好きですね。
中村
これまでのお話を伺って私も新天地仮説だと思いますね。
印東
よかった(笑)。けれども、そもそも大きくて華奢なラピタ土器が本当に島嶼間を行き来したのか、私は少し疑問に思っています。両手で抱えきれないほど大きな土器を小さなカヌーにひとつ載せたらもう満杯ですからね。未だわからないところの多い土器です。
中村
ラピタ土器が今の暮らしに伝わらなかったのは、本当に残念。ところで先ほどのヤップ島では、今でも土器は作られているのでしょうか?
印東
実は、私に作って見せてくれた女性が最後の一人で、数年前に他界されました。
中村
次の世代には伝わらなかったのですか。
印東
ヤップの土器作りは、いちばん階層の低い村の女性の仕事だったのです。実は彼女は階層の高い村の、しかも首長の息子と結婚して、もう作らなくなっていたのですね。調査の時には頼み込んで作ってもらったのです。土器を作る行為が社会的に低い地位と結びついていたことも、知識が途絶えた一因とも考えられます。
(註6) 大陸島
大陸の一部が海進などで分離されるか、大陸付近の海底が隆起して生じた島。
(註7) 斉藤成也
国立遺伝学研究所教授。著書に『DNAから見た日本人』(ちくま新書)など。
6.複雑さ、曖昧さをめぐる知恵を
中村
とっても多様なオセアニアの小さな島々ですが、もうほとんど研究されているのですか?
印東
飛行機が発着する島と周辺の島々はかなり調べられています。しかし今でも舟でしか行けないような島々には未調査の島もかなりあります。
中村
そういう島にも人は暮らしているのかしら。
印東
住んでいますが、どんどん減っています。やはり文明化されて便利な機能がある島に吸い寄せられるように集まってしまうのです。例えば、ハワイやニュージーランド、タヒチなど。
中村
今あげられた名前は、観光地として私たちがよく知っているところですね。
印東
タヒチやハワイ、サモア、トンガなどは資源が豊かな火山島で、歴史的に、王や首長がいて、平民や奴隷もいる伝統的な階層化社会が発達しました。豊かな資源を背景に人口も増え、島全体を制御するしくみとして、階層化に基づく文化が生じました。
中村
考古学から今を知りたいとおっしゃいましたけれど、例えば南米のインカの遺跡では発掘された物が語る古代文明と現代との間には断絶があるでしょう。現代の生活の中まで連続性が保たれているところがオセアニアの面白さですね。
印東
まさにそうです。島という海に囲まれた環境が歴史を続かせてきたのかもしれません。
中村
ダーウィンは島々をめぐり、そこにいたカメやトリなどたくさんの動植物に見られる多様性と共通性から進化を確信しましたが、人間も生きものですからおなじ。歴史を見るには島という環境はとてもよいと言えるわけですね。
印東
 島は「天然の実験室」です。ある限られた自然環境の中で、人間がいかに適応し、いかに生活を変化させたかを見る姿勢は、考古学でも大切にしているものです。
島は「天然の実験室」です。ある限られた自然環境の中で、人間がいかに適応し、いかに生活を変化させたかを見る姿勢は、考古学でも大切にしているものです。
中村
文化と自然環境との絆を確かめることになるわけで、生物学での進化論にあたるものが見えてくるわけですね。
印東
ええ。それと人間の身勝手さ。人間が無人島に新しく移り住んだ場合、最初に食糧として狙ったのは鳥だったことが実証されています。発掘するといちばん古い層から今ではもう見つからない多様な鳥の骨が大量に出てきます。そして時間が経つほど出土する種の数や量が減り、それに代わってニワトリやブタなど家畜の骨が増えてきます。初期の移住者たちは農耕民というよりもハンターに変身したわけで、絶滅させた鳥類もたくさんありました。
中村
どうしても食べなくてはならないのはわかるけれど、どうも人間は食べ尽くす破壊者になりがちですね。
印東
持ち込んだ栽培植物や家畜が立派に育つまでの間は天然の資源に頼らざるを得ません。ニュージーランドも、もとはモアという巨鳥が闊歩していた無人島だったわけです。今モアはいない。
島では何を食べるかだけでなく、あらゆる生活面で自然環境の制約がかかってきます。おなじサンゴ島でも周りにサンゴ礁のあるなしで魚の獲り方もまるで違う。サンゴ礁の豊かな島には浅いラグーンが広がり、そこへ手網を持って入れば女子供でもわりあい簡単に魚を獲れる(写真6)。ところが、私が調査しているファイス島など隆起サンゴ島にはラグーンがなく、魚を獲るには外洋に出る航海術や底釣り用に工夫した釣り針が必要です。その場合、集団で魚を獲りに行くことで人々の連携が強まります。

(写真6) 「大潮には女子供も浜に出て海の幸を得る」
(トンガ、1996年 印東道子撮影)
中村
サンゴ礁のあるなしで人間社会の性質が変わる。自然の中の人間ですね。
印東
そして島で生きていくためにいちばん大切なことは人と人とのつながりです。とくに資源の限られたサンゴ島での暮らしを見ると、共同体の一員として生きることが、生命を維持することと密接に関係していることを強く感じます。例えば、小さな島だと数十人しか住んでいませんから、獲った魚は皆に等しく分配します。「自分が釣った魚を分けるのはいやだ」なんて言ったら生きていけない。資源の限られた小さな島では平等な社会が多く、仲間を統率するリーダーはいても、階層化社会は発達しませんでした。
中村
島と島の交流はどれくらい行われているのでしょう。
印東
資源の限られた小さなサンゴ島の人々は、平穏なうちは自分らでやっていけても、台風が来たり、干ばつや津波に遭えば助けが必要になると知っているので、いざという時に補償を受けられるよう、隣の大きめのサンゴ島や近くの火山島などと日頃から接触を密にしています。その手段としてミクロネシアで最近まで受け継がれてきたものが伝統的なカヌーや航海術です。島の人々のおかげで私たちもその航海術を知ることができます。現在、「みんぱく」に展示してある大きなチェチェメニ号(写真7)は、ミクロネシアのサタワル島で20世紀まで連綿と受け継がれた船大工の仕事です。

(写真7) 「チェチェメニ号」
(国立民族学博物館蔵)
カヌー本体の片側に舷外フロートを持つシングル・アウトリガー式カヌー。船首と船尾が同形なので前後どちらにも進める。
中村
島と島をつなぐための技術が、現在まで連綿と続いていることは、人々にとって、外と関わり続けることがいかに大切かを物語っていますね。
印東
ある島の生活を特徴づける要因の一つは島固有の環境にありますが、周囲にどんな島があるかという関係の中で決まってくるところも大きいと思います。小さなサンゴ島とは対照的に、サモアやフィジーなど資源の豊かな大きな火山島に住んでいると自己完結型になり他の島との交流も廃れがちです。
中村
考えさせられるお話ですね。文明社会は、自分たちの国や経済を大きくしようと競い合ってきました。でも本当は、オセアニアの島々のように小さな社会をたくさん作って、その中で生きていくために皆で結束を固めて、いざという時のために外とも日頃から仲良くしておくという暮らし方は、とても人間らしくて優れているように思えるんです。地球を全部小さな島の集まりにしてしまったらどうでしょう。
印東
面白いですね。ただし遠洋航海は、つねに危険を孕みます。漂流して命を落とした人も多かったはずで、航海には様々な祈りやタブーが伴われます。島の人もできるなら危険を冒した航海はしたくなかったのではないかと思います。
中村
海は、豊かな恵みの場であると同時に恐ろしい試練の場でもあるということですね。
印東
それと、漂流という出来事は、新しい島を発見する大きな契機でもあります。海は、島と島を隔てるものであり、繋ぐものでもあるわけです。人々が島々をめぐる中には、偶然としか言えない出来事もたくさんあったでしょう。
中村
そこが自然界の面白さですね。繋いだり隔てたり、優しかったり恐かったりと常に両面ある。ところが現代社会は、自分たちに都合のよい面だけを見て科学技術を進めてきました。ありのままの自然が面倒で、そこから切り離して作った都会の中で、制御しやすいことだけやってきたけれど、そろそろ人間も生きものだという基本に戻る時ですね。豊かだけれど命を奪うという自然界がもつ二元論では捉えきれない曖昧さ、複雑さを、学問にも、生活にも、もう一回、取り入れないと本当の知恵にならないと思いますね。
7.最先端に浮かぶ島々
印東
ミクロネシアの多くの島では、サメは自分たちの祖先と考えて食べません。ところがカメの甲羅で釣り針を作るファイス島だけは、自分たちの祖先がサメだという考えがなく、発掘される魚骨の分析からも、サメを多く獲っていたことを示しています。
中村
そのいきさつは神話や民話のような形では伝わっていないのですか。
印東
「島を釣り上げた話」(註8)などの民話は比較的共通したものが周囲の島でも見つかり、ファイスだけ違うということはないようです。もっとも、オセアニアの神話は大変豊富だったのに、早い段階でキリスト教が入ってしまうとそれが消えてしまう。
中村
いろいろな神様がいなくなったのは残念。神話ってその人たちの世界観でしょ。そういう意味で現代人にとって学ぶことがたくさん入っていると思うのです。
印東
神話をたくさん比較研究された大林太良(註9)先生のような方のお仕事と考古学を結びつけることができれば面白いと思います。
けれども今、世界中にグローバル化の波が押し寄せ、民族誌そのものを調査したいとフィールドに出ても、土地の古いものを知っている方がほとんどいらっしゃらなくなってしまいました。手仕事がかろうじて残るくらいです。私が調査をはじめた30年ほど前は、伝統的なものがたくさん残っていたのですが。
中村
その頃は日本にも地域のつながりがありました。現代は大変な時代ですね。自分たちの歴史を壊して地球上から消しつつある。急いで調べないと間に合いませんね。
人間は10万年前にアフリカを出て以来、さまざまな自然の中で、それぞれの場を生かした生活・文化を作ってきたのに、それをこの数十年で全部壊している。50年先はどうなるのかしら。
印東
伝統的なものが失われ、均質な文化になりつつある。オセアニアでも、まだ飛行機便のない離れた島では伝統的なものも続いていて、しばらくは調査できるでしょう。ただ交通アクセスが困難で調査が大変な島には若い研究者はあまり行きたがらないんです。
中村
「え、コンビニないの」って言うでしょ。文化人類学や民族学はどこへ行ってしまうのかしら。
印東
私の調査しているファイス島には電気もガスも水道もありません。昔の話を覚えている島の人もまだかなりいますけれど、島の子どもたちは中学を出ると高校へ通うために自分の島を離れて生活するしかなく、島のお年寄りから話しを聞く機会を奪われています。次の世代を担う若者が伝統的な知恵を学ばずに学校の知識だけを身につけ、しかも一旦、島外で経験した便利な生活に慣れてしまうと、不便で現金の得られない島へは戻らないことも多いのです。
中村
残されたのは、仕送りで暮らすお年寄りと子どもたち。日本の地方とおなじ現状ですね。
印東
島では、子どもたちに教育を受けさせたいという思いは強く、それにはお金が必要なので出稼ぎに出る、という近代化の生み出す負の循環からどのように抜け出すかが課題ですね。
昔の島の暮らしは現金いらず。帆のついたカヌーひとつで漁もすれば隣の島へも行けたのに、今はガソリンを買わなくてはモーターボートが動きません。
中村
 すべてがお金で動くために貧困が生まれてしまうのが現代社会ですね。すべてを自給自足しなくても、自分の島で足りないところは周囲の島々とのつながりを基本にしながら、新しく入ってくるものともうまく折り合いをつけられたらよいですね。またそういう時代がめぐって来て、古さと新しさを融合させた本当の豊かさが生まれるとよいのだけれど。
すべてがお金で動くために貧困が生まれてしまうのが現代社会ですね。すべてを自給自足しなくても、自分の島で足りないところは周囲の島々とのつながりを基本にしながら、新しく入ってくるものともうまく折り合いをつけられたらよいですね。またそういう時代がめぐって来て、古さと新しさを融合させた本当の豊かさが生まれるとよいのだけれど。
印東
私が調査に行く島の人々はお米が大好きですが、サンゴ島の痩せた土地で米は作れず外から買うほかない。最近は、そこを考え直して自分たちの島で作れるタロイモやサツマイモに戻ろうという動きもありますが、すべてを賄うことは難しいですね。コーヒーも飲みたいだろうし、ランプには石油も必要。これらをシステムとしてうまく採り入れた新しい時代がめぐってくれば、人口の一個所集中という流れを止められるでしょう。
中村
今日はオセアニアの話ですが、実際には、地球全体が大変なことになっていますね。資源はいつまでもあるわけじゃなし、どう考えてもあるもので工夫しなくてはいけないことは明らかで、その知恵が、文化そのものが、地球上から消えてしまうのは残念ですね。
印東
そう、私たちがいくら記録しても、引き継いだことにはなりませんから。
中村
オセアニアはとても象徴的な場所ですね。消えていくものをみごとに見せてくれている。地球全体として、今、何が起きているかがなかなか見えてきませんが、小さな島の上で、最終的に何が起こるかを先に見せてくれているように思えてなりません。
印東
オセアニアの島々は、地球環境の変動についても最先端にいます。海抜の低いサンゴ礁から成るツバルやキリバスでは、確実に海面上昇の危機に直面しています。
中村
あの辺りへ行かれた実感としてですか。
印東
島に住んでいる人々から「海岸はもっと向こうにあったんだよ」って聞きますし、私自身もそう感じます。ところがツバルで調査している人には「海面は上がっていない。地盤が沈下しているせいだ」と主張する人もいるんです。
中村
具体的に海岸線が上がっているという事実とそれの生活への影響は変わらないわけなのに。
印東
道路やタロイモの畑が塩水に侵されてきているので、最低限の自給自足も成り立たなくなっているという事実が大切だと思います。その上、援助金でお米を買って生活するにしても、生活する場そのものが海の中に沈みつつあるのです。
中村
それでは、そこに住んでいることの意味がなくなってきますよね。
印東
キリバスでは、何年か後に水没するという計算に基づく大統領決定により、10万人の全国民に技術を身につけさせ、毎年、オーストラリアやニュージーランドなどに熟練労働者として移住させる政策をはじめています。
中村
残念ですね。
印東
 オセアニアには、小さくてもココヤシが生い茂り、海洋資源も豊かな島はたくさんあります。陸上資源に乏しいサンゴ島でも、数千年前から人間が暮らした痕跡が見つかります。人々が島をめぐりながら育んできた歴史を解き明かすにつれ、人間のもつ限りない好奇心や知的能力を確認できる宝庫だと感じています。
オセアニアには、小さくてもココヤシが生い茂り、海洋資源も豊かな島はたくさんあります。陸上資源に乏しいサンゴ島でも、数千年前から人間が暮らした痕跡が見つかります。人々が島をめぐりながら育んできた歴史を解き明かすにつれ、人間のもつ限りない好奇心や知的能力を確認できる宝庫だと感じています。
中村
実はこれまでこの辺りは太平洋という海として見ていました。今日のお話でここにはたくさんの島があることの意味がよくわかり、それがアジア大陸、南米大陸、オーストラリアを結んでいるという姿が見えてきました。そう思って地図を見直すと、人の暮らす地球が全体として見えますね。眼からウロコといいますが、まさにそういう感じです。
地球のことを考え、人間の歴史を考える大事な場を教えていただきありがとうございました。これからも関心を持ち続けていきたいと思います。
(註8) 「島を釣り上げた話」
ポリネシアに伝わる、半神半人のマウイとその家族が登場する不思議な物語の一つ。兄たちと漁に出たマウイは魔法の釣り針でいくつかの島を釣り上げる。ファイス島にも海から釣り上げられてできたという神話が残っている。
(註9) 大林太良
(1929-2001)
民族学者。東京大学名誉教授。東南アジア、オセアニア、北方民族の神話と日本の神話を比較研究した。
写真:大西利明
対談を終えて
中村桂子
地球儀を眺め、この島いっぱいの地域を太平洋という海としてしか見ていなかった不注意を恥じました。数千年の時間の中で、さまざまな自然と人々の暮らしとの関係ができ上がり、また変化していく様子は、生命誌の縮刷版のようです。フィールド研究者独特の大胆さとていねいに考える落ち着きとの混在がとても魅力的でした。
印東道子
失われゆく知恵を受け継ぐ
中村さんとお会いするのは今回が初めてでしたが、テレビなどで拝見して感じていたとおりのやさしくおだやかな方でした。専門にされている生命科学からは、かなり離れた分野のお話をさせていただくために脱線ばかりしてしまいましたが、深い教養と知識にもとづいた的確な質問で助けていただき感謝しています。
中村さんとお話ししていて強く感じたのは、人類が営々と蓄積してきた伝統技術や知識が失われつつあることへの危機感です。現代のグローバル化したテクノロジーは、オセアニアの島々をも飲み込もうとしています。時空間をめぐって代々受け継がれてきた知の蓄積が急速に忘れ去られつつある現状にどう対処したらよいか、新たな宿題を見つけた気がしています。

印東道子(いんとう・みちこ)
東京生まれ。1976年東京女子大学文理学部卒業。同史学科助手を経て、ニュージーランド・オタゴ大学人類学部大学院博士課程修了。Ph.D.。北海道東海大学国際文化学部助教授、教授を経て2000年より国立民族学博物館教授。総合研究大学院大学教授を併任。専門は、オセアニア考古学、文化史。主な著書に『オセアニア 暮らしの考古学』『島嶼に生きる』『環境と資源利用の人類学』ほか。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)
.jpg)











