
TALK
自然からいただく清らかなもの
1.ご飯ができましたよ
中村
大阪の高槻で生命誌研究館を始めてから一人暮らしの日が多くなり、それで気づきました。お料理するのは食べてくれる人がいないと面倒なものです。出来合いのものは自分の味覚に合わず外で買って帰るのもいや。その時、助けになるのが一汁一菜です。昔は手抜き料理だと思いましたが、この頃は土井さんのお墨付きがあるので(笑)。
土井
『一汁一菜でよいという提案』(註1)は多くの若い人が共感してくれました。意外と、今の若い女性もよい家庭は食事から始まると素直に考えるようで、しっかりお料理できなくてはいけないと思って結婚や出産の時に本気で悩むんです。
専業主婦の時代は社会にも勢いがあり、家庭料理も食卓におかずをたくさん並べるのが豊かさ、基本は一汁三菜とされました。でも今、仕事をする女性にとってそれは難しく、今でもたくさんお料理しないと手抜きのように感じるのです。
一汁一菜は具沢山の味噌汁とご飯だけで十二分という食事です。具材の変化で季節を感じ、付け足されるおかずに驚きや楽しみを発見する日常の食卓の提案です。「そんな簡単なことでいいの?」と驚かれましたが、実際、一汁一菜という形は日本の家庭料理の原点です。味噌汁を具沢山にすればおかずの一品を兼ねますし、なぜかご飯と味噌汁は毎日食べても飽きないものです。一汁一菜に付け足すおかずは、無理せず自分が食べたいものや家族に食べさせたいものでよいのです。
中村
なるほど。それでつくづく思いました。食べものは体をつくるものですが、更に人と人との関係をつくるものですね。
土井
楽しみとしてのおかずは中華風でも西洋風でも、酒の肴でもよいのです。「命を養うもの」と「楽しみで食べるもの」を意識して区別するとよいですね。

中村
あらゆる文化に汁物があるのはそれが基本だからでしょう。
土井
フランスの家庭でも毎日の食事は温かい野菜スープにチーズとパンが基本、フランスの一汁一菜ですね。温かいスープを飲めば体は温まり、家に帰ったという気持ちになります。野菜の少ない土地でもお肉をスープにすれば大勢で分け合えてお腹いっぱいになる。一方で謝肉祭の焼肉はご馳走です。焼肉やお寿司などハレのご馳走を食べた時に感じる快楽的な美味しさと、味噌汁やお漬物など普段のケのものの儚い美味しさとは明らかに別ものです。
中村
その区別を明確にしながら暮らしの基本はやはり毎日をどれだけ大切にするかであるとわかっていることですね。
土井
簡単な食事を丁寧に続けると、結果、毎日が充実することがわかります。慎ましさの中でいろいろな感覚が研ぎ澄まされるように思います。普段がご馳走ではその感受性が失われてしまいます。
中村
現代はご馳走がいっぱい、情報がいっぱいです。皆がスマホばかり見ていると、ふとした風に心地よさを感じるという感覚を共有できなくなってしまいます。自分の感覚で知る喜びを大切にしたいですね。だから私は、人間は生きものの一つと言い続けています。
土井
科学をご専門としながらとても人間的な発言をなさる、中村先生のような考えをお持ちの科学者に私は初めてお会いしました。数値化も証明もできない感性や人情のようなものまで受け止めてくださる。
中村
私は日常が好きなのです。科学でわかることは面白いのですが、それが日常とつながらなかったら意味がない。それで生命誌研究館を始めました。
土井
学問は何の為にあるのか。中村先生の生命誌は真心がこもっています。人が幸せになる学問ですね。
中村
生きものを研究するだけでなく、普通の人の感覚で「生きている」ことを広く考えたい。でもその思いを共有してくださる方は今それほど多くありません。

土井
他の分野に大勢いらっしゃいます。中村先生がまど・みちおさんの詩を語られているのをラジオで聞いて、そのお話ぶりに引き込まれ、心豊かで温か味溢れる視点に心を動かされました。
中村
ありがとうございます。宇宙を見ましょう、ミミズもカも含めて小さな生きものをちゃんと見ましょうという心は詩も科学も同じです。お料理にも同じところがあるのではないでしょうか。
土井
西洋では、料理でも何でも人間が作る主体で、自然さえ制御するものと捉えますが、日本では、おおらかに自然からいただくと考えますから。特に和食の世界は自然に和する気持ちが大切です。例えば、杜氏の伝統でも「この旨い酒は自分が作った」と奢る気持ちを戒めなければならないと言われますし、私たちも普段「ご飯を作った」とはあまり言いませんね。
中村
確かに、「ご飯ができましたよ」と呼びますね。
土井
できたということですね。結婚する時も「結婚することになりました」と、何か他の力が働いてそうなりましたという風に言います。
中村
生命誌を考える動詞の一つに「生る」があります。作るに対して自ずと生成してくるという感じです。お料理はもちろん手をかけますけれど素材が持つ自ずと生成する力を引き出すという感覚ですね。
土井
自然の作用と自分が一体になる「おかげ様」の感覚、特に和食は一本の丸木から仏を掘り出すようにして、既にあるものを掴むのです。
中村
自然の「自」という字は、本来は「おのずから」ですね。「自然に」と言う時もこの感じです。これを「みずから」と読むのは西洋風なのでしょうね。現代は自然を客観的対象として見ますが、本来人間は自ずと生まれたものの一つとしてあるのだと思います。
土井
この頃は日本でも科学的に数値化されたデータを根拠に自然を語ることが当たり前になってきました。私たちを畏怖させ、戒めてくれる自然という大きな存在を失ってしまったようで、そこが問題です。
中村
自然への驚き、素材への信頼を持てば、自ずから美味しいものになるという気持ちですね。

土井
不味くしないことが和食の極意と言えます。中村先生はお料理も随分とお上手なんでしょうね。
中村
とんでもない。いい加減な人なので。ただ冷蔵庫をパッと開けて、あり合わせでサッとなんとかするのは得意です。
土井
それはお料理の基本です。すぐにレシピが欲しいと言う若い方は目分量が苦手です。料理を数値化して再現しようとするレシピという発想はそもそも西洋のものですし。
中村
私はほとんど目分量というか味わいながらです。
土井
計量に頼らず目分量でやれば手際もよくなり「どうかな?」と伺う気持ちが自ずと生まれます。
中村
対話ですね。
土井
その通りです。私はよく、素材である「お芋の気持ちになってごらん」というように言います。お芋が気持ちよくなるようによく見て待つ。よい煮たち加減は綺麗な音をたてているものです。ゴトゴト強火にして「早く煮えろ」と自分の都合を押し付けてもうまくいきません。素材を傷つけない穏やかな気持ちから美味しい料理ができあがるのです。
昔から日本人は擬人化が得意ですね。「鳥獣戯画」を見ても、身近な動物、お野菜や生活道具まで、それらと会話するように気持ちを入れて楽しみます。私も糠漬けをしていると、ふとそれが生きもののように感じられます。目に見えない菌の存在を知らなくても、糠床の匂いや固さ、糠に手を入れた時の感覚で、相手のご機嫌を伺ってお世話するわけです。すると心を通わせた結果、不思議なことに美味しくなる。糠漬けが美味しくできるようになるのは料理人の人間的成長によるものだと思っています。
日本の調味料である味噌や醤油の発酵に麹菌が使われるようになってから千二百年も、その菌を守り続けて来た先人の感覚や真面目さには、人間の能力として想像を超えるものがありますよ。
中村
ほんとうに。犬や猫はもちろんお芋の気持ちにまで入れるのは日本人に独特のことかもしれません。酵母菌もバクテリアも単細胞で見えませんけれど生命力は強く、旨味を作ってくれますでしょう。最近は、腸内細菌は私たちの一部と見た方がよいということになってきました。
(註1) 『一汁一菜でよいという提案』
土井善晴著。グラフィック社(2016)。
2.お母さんの料理が伝えるもの

土井
和食は自然との関わりからできるもの。お漬物一つとってもそうです。例えば糠床も、これまで木製の樽やポリ容器なども試しましたが、薪で焼いた古い甕に変えて安定するようになりました。
中村
素晴らしい。薪で焼くところまでは行きませんが、私も小さな甕を使っています。
土井
冷蔵庫の無い昔は、暑い夏、外から帰って飲む甕の水が冷たくて気持ちよかった。甕の中は温度変化が少ないからです。甕の糠床は菌も安定するようです。
夏は毎日、茄子や胡瓜を糠漬けにして食べています。気温が落ち始めると白菜の季節が始まります。白菜は塩漬けにして、暖かくなるまでほぼ毎日食べますが、酸味が出るくらいに日を置いたものが特に美味しいようです。これも微生物が旨味や栄養素、ミネラルを産生しているおかげですね。
秋から冬にかけては地下に栄養を蓄えるお芋や根菜類をよく食べます。更に水菜やほうれん草、小松菜、キャベツ等、何度も霜に当たり風雪に耐えた冬の菜っ葉は甘味が増してとろけるようで、二月頃の小松菜なんて驚くほど美味しくなります。冬は虫が付かず農薬の心配が少ないのもよいところです。
やはり一年を通じて、日本の暮らしと一体化した「旬」のものが一番です。ところが最近は季節ごとに手に入る野菜の種類が少なくなりました。スーパーの品揃えが一年中同じ、胡瓜にトマトにサラダ類、手を加えずそのまま食べられるものが店棚の大半を占め、手のかかる牛蒡やお芋は後ろの方に少々の扱いです。
中村
便利な野菜ばかり、どのお店も同じ品揃え。でもお野菜ってほんとうは多様ですね。大根の絵本を作った友達がいて、それを見ると大根だけでなんと豊富な種類があるものかと嬉しくなります。生物多様性というと面倒ですが、毎日の食べものが多様だったら自然に考えられるようになりますね。

土井
「旬」の美味しさは格別です。いくら技術が進歩しても、この美味しさは絶対に作れないでしょうね。野菜を品種改良して、生でも食べやすくアクを無くすとその野菜が持つ本来の美味しさまで消えますし、その時、栄養価値まで犠牲にしているのです。どうも日本人って、色や形などの見た目ばかり重視して味覚を軽んじるようです。甘いだけのトマトを人工的に作っても、そこには昔食べたあのトマトが持っていた自然な美味しさはありません。効率等の人間の都合を押し付けて、本来野菜が持つ命の力を弱めているからだと思います。自然にはかなわないのに。
もう三十年程前になりますが、五月の連休の頃、土地の人と山に入って自然に生えている山うどを始めて食べた時、「これほど美味しいものはない」と頭をがつんと打たれた気がしたことを思い出します。
それまでの料理屋では高値の促成野菜を仕入れていたので、この時、自分が自然の美味しさを知らなかったと初めて自覚しました。以来、とにかく野菜の旬の姿や美味しさをもっと知りたい、記憶に焼き付けたいとの思いで、暇さえあれば篤農家を訪ねました。その時、畑で採れた野菜の力強さ、美しさに心が震え、こんなに綺麗だということを皆さんに伝えたいと思って、ある写真家に撮影をお願いして雑誌の連載にもなりました。ほんとうにキャベツ畑に立っていると、あまりの美しさに、赤ちゃんがキャベツ畑から生まれてくるという伝承も納得できます。
中村
野菜は生きものですからね。
土井
でも野菜は生きものという当たり前のことを、ほんとうにわかることはとても難しい。教わるものでないようにも思うのです。よく大根足なんて言いますね。土の中から引き抜いたばかりの大根をすぐ水に浸けて泥を洗い流すと、本当に真っ白で、なんて綺麗なんだってびっくりします。
中村
綺麗なものを大根足と呼ぶんですね、安心しました(笑)。
土井
そう思います。大根役者と言うのも、実はどんな場面にも重宝して役に立つ、そういう親しみや愛情を込めた呼び方だと思います。
中村
生命誌はまず小さな生きものに接して生きているということをよく見るところから始まります。生活からそういう場面が消えていることが気になり、喜多方の人たちと小学校農業科という取り組みを始めました。授業ですから、種をまくところから始まり一年中、先を考えていくのです。最初は「面倒だ」と言っていた子が一年間、自分の責任で育てていると「僕は、枝豆に水をやりながら大きくなれよと声をかけました。」と言うようになるんです。子どもの気持ちの変わりようが愛おしくて続けています。

土井
命と関わることで情緒や責任感を自然と持つことができるようになる。子どもたちにとって素晴らしい経験ですね。家庭料理も同じように考えられます。普段、親が料理する音を聞き、匂いを嗅いだり見たりする何気ない経験から、子どもは情緒を身につけ、想像力を育んでいくのだと思います。それを「美味しいね」って家族と食べる時、背景にある人の気持ちや自然を含めて、美味しいと感じられるようになる。
中村
作文に、自分が作った野菜をお母さんがお料理してくれて家族で食べる喜びを書いた子どももいました。お料理は親からつながってくるものです。私も結局、母がやっていたようにお台所してますよ。身に染み付いている。お料理にはそういう力がありますね。
土井
家庭料理は命をつくる仕事です。そこが子どもにとっての「居場所」になるんだと思います。毎日、自分のために作ってくれるお料理から子どもは実に多くのことを受け止めるでしょう。そうやって親の心、日本の心が伝わっていくのだと思います。だから人間は毎日を一生懸命に暮らすことが何よりも大切。それだけで、子どもにちゃんと伝わると思います。
中村
家庭の味はレストランと違ってグルメ感覚で美味しいとか、美味しくないとかいうものではないんですね。家ごとに独特のお料理ができてきて、それを共有する喜びが味の思い出になってきます。私は何でも生きものに引きつけるのですが、生きものと同じでお料理も多様性に面白味があるのかもしれないと思います。
3.清潔とけじめの賜物

中村
世田谷の自宅はすぐ近くを流れる野川という小さな川のハケの斜面にあります。下流は等々力渓谷、上流は深大寺に大きな池があり、そこに溜まった山の水が野川沿いに地下水脈を形成しているそうです。その地下水が有難いことにうちの庭で湧くのです。
土井
東京でそんな贅沢な話があるんですか。
中村
その代わり、毎日、大きなボトルを抱えて斜面を降りて水を汲んでくる。これが主人の日課になっています。
土井
その水でお茶でもコーヒーでも飲まれたら美味しいでしょう。
中村
ええ。夏は麦茶を冷蔵庫に入れておくと汗をかいての外出から帰った時、美味しいですね。先日、たまたま水を切らして水道水で氷を作ったら娘にばれました。
土井
よい水で作る氷は透き通って綺麗ですが、水道水では白く濁ってしまいます。ちゃんと知っているんですね。
中村
地球に水がなければ生きものは生まれなかった訳で、水あっての我々です。でも現在の機械文明は、水より火、つまりエネルギーに眼を向けてきました。木、石油、原子力と進み、それを豊かさとしてきました。でも今、機械と火の時代から生命と水へと文明を転換させるところに来ていると思います。美味しいお料理は美味しい水と食材からできるわけですから、お料理は生命と水の時代をストレートに表現できる場ではないかと思うのです。
土井
すべての料理は水から始まります。最近、和食の出汁が海外からも注目されましたが、フランスでも中国でも家庭では、毎日のスープを水から作ります。お味噌汁だって出汁の前にまず水が大事です。純粋に素材を味わってもらうには出汁さえ邪魔になるのですから。
ご飯を炊く時も、綺麗な水で加減してすぐ火を入れることで、お米のポテンシャルが存分に引き出され美味しく炊き上がります。前の晩に水加減して、翌朝、自動的にスイッチが入るのでは決して美味しいご飯は炊き上がりません。というのは、お米と水が出会った瞬間から発酵が始まるので、一晩置くだけで雑菌だらけの水でご飯を炊くことになるわけです。こういうご飯は美味しくないし腐りやすいものです。
綺麗な水で炊くご飯は傷み難いものです。更に炊き上がったご飯をおひつに移すのも余分な水分を取り除くため。だからおひつに移したご飯は冷めても美味しい冷やご飯になっています。
ほうれん草のお浸しは、茹でたほうれん草を水に晒して、食べやすい大きさに切り、水気を絞って盛り付けます。その時の水気の絞り加減、つまりほうれん草に触れる手加減一つで味が変わります。それを突き詰めるとどんどん「何もしなくて美味しい」というものになっていきます。和食は、季節やその場にふさわしい器を選んで盛り付けて完成します。しつらうと言いますが、その盛り付けをした瞬間、お料理から人間の気配は一切消えなくてはなりません。

中村
フランス料理やイタリア料理ではシェフの名前を言い、個人の作品であることを強調しますけれど、和食は人間の気配を残してはいけないというのは面白いですね。そもそも日本では自然そのものが神様でしたね。
土井
料理人が目立ってはいけません。あくまで自然、素材が主役です。お料理をいただく時、食べる人と自然が直接触れ合うところに調和する心が生まれます。その楽しみの場が和食の世界です。ユネスコ無形文化遺産に登録された和食の対象は、実は家庭料理なんです。お料理は自然の恵みだから美味しい。季節の旬を大切にすることが、人間の喜びや楽しみ、健康につながるのです。それぞれの土地にある自然を敬う心と、おばあちゃんやお母さんがつないできた台所仕事が一つになって、祭祀や慎ましい暮らしを作っている。伝統の家庭料理は人間としての自然の営みそのものです。そこを世界が評価しているのです。
中村
それは気づきませんでした。文化遺産と聞いた時、有名料理店の高級なお料理を思い浮かべていました。家庭料理に本来の日本文化の姿があり、それが文化遺産だという指摘はあまりされていませんね。お話を伺ってたくさんのことを考えさせられました。家庭料理を疎かにする傾向がなきにしもあらずですから。そのご指摘は大事なことです。
土井
お料理が暮らしの中で伝統行事と結び、健康や自然と結んでいることが美しいと評価されたのですから、主役は各地で家庭料理を育み続けたおばあちゃん達、お母さん達です。だから中学や小学校の校長先生が朝の朝礼で「皆さんのおばあちゃんやお母さんのお料理が無形文化遺産になりました、おめでとう!」と言ってあげて欲しい。子どもたち嬉しくて家へ走って帰りますよ。
中村
誰もそう受け止めていませんでしょ。肉じゃがでもいいのかな。自分の料理が文化遺産なんだという意識をみんなが持てばお料理が楽しくなりますね。
土井
私が一汁一菜と言っているのはそこです。一汁一菜は和食を伝える方法でもあるのです。一汁一菜は汁飯香、味噌汁とご飯と漬物が最小単位です。それをお膳に並べるとちょうど三角形になり、手前にお箸を横に置くというスタイルが基本です。
お箸を横置きで揃えるのは世界中を見渡しても和食だけ。それは一つのけじめであり結界なのです。「いただきます」と言って結界を解いて初めてご飯という清らかなものと一緒になる。我々が昔からつないできたそういう何気ないことを伝えていかなくてはなりません。

中村
確かにお箸を横に置かないと形になりません。そこにも意味がある。和って深いですね。
土井
お膳の縁が高いのも結界となってけじめをつけている。お膳の縁高の内側は清らかな世界です。更にお膳を三、四人で共有したものがちゃぶ台です。普段ご飯をいただく前の「手を洗いなさい、お膳を片付けて、拭きなさい」というお母さんのしつけが大事なのは、それが食事にけじめをつけることだからです。食べものはみな神様ですから、私たちは清潔にして、清らかなものに触れるのです。
中村
確かに、和の世界には清いという価値観がありますね。
土井
お刺し身なんて清潔とけじめの賜物です。今では、山の上でも火を入れず生のまま食べられる安心感は世界中どこを探しても他にありません。一尾の鯛から白い身を取り出し、食べられるところ、食べられないところを分ける。その所作はまるで一本の木から仏様を掘り出すようです。それが和食を象徴する「お造り(お刺身)」です。「造る」という字は酒・味噌の醸造や、巨大な建造物・造船など、人間には到底作れそうにないものに当てますね。お刺身を「お造り」というのは神様のお造りになったものですから。お供え物の下には白い紙と羊歯を敷きますね。同様にお刺し身には白い大根のけんと緑の葉を敷きます。ハレの食べものですが、そもそも神様の食べるお供えものなのですね。それを神様と一緒に食べるのがお祭りの日の神人共食です。
中村
和食のハレの場のお料理には、際立ってけじめと清らかさが象徴的に現れているのですね。これからお刺身をいただく時にちょっと緊張しそうです。ただお料理に限らず最近はハレに眼が向きすぎているように思います。生命誌では、小さな生きものたちの日常から多くを学んでいますので、日常、つまりケの中に大事なことがたくさんあると思っています。
4.お台所で自然と触れ合う
土井
和食の基本は一つ一つを大切にすることです。昔から山に住む人と山菜や茸を採りに行くと、彼らは採って来た山菜を一種類ずつきちんと分けて、きれいに揃えて、その扱いの丁寧さに驚かされます。そして、それぞれを干したり塩漬けしたりします。それぞれをきちんと別々にして味わうのです。ああいうお年寄りの仕事を見ていますと、私たちは昔から自然の一つ一つと向き合い大切にしてきたのだとわかります。
中村
普段は手抜きの私でもおせち料理を作る時は、母や姑の手つきを思い出し、伝統を大事にしようと思います。一年に一度でも思い出し、それをまた次の世代につなげていくことの大切さを改めて思いました。実は今年の私たちのテーマが「和」であり、「和える」がさまざまな素材を混ぜて一体化するのにそれぞれが生きているところが面白いと思っています。
土井
混ぜると、和えるは全く違うことですね。今気づかされました。和えるのはいただく直前ですね。混ぜると違って綺麗に整えることが和えるなんですね。絵の具も三色を混ぜると灰色になりますが、その直前、それぞれの色が生きている状態で止めるのです。和えるは、美しく調和した瞬間だと思います。
中村
混ぜるのではないというところが大事ですね。素材としても、色としても個々が生きており同時に全体として一つの味になっている。和えものこそ日本文化という気がして仕方ありません。

土井
和食は素材を大事にしますが、それは素材の命、即ち生きていることを大事にすることですね。命の輝きはどれも一瞬で、やがて死に近づいて行きます。つまり食材が持つ時間のある瞬間をいただくのが和食です。侘び寂びも同じところから生まれた美意識でしょう。だから和えものはお料理を出す直前にさっと和えて器に盛り、天盛りを添えるのが約束事です。天盛りを「とめる」と言いますが、松葉に切った紅生姜、山椒の芽、柚子などをとめます。それがもう誰も触れていないもの、そこは清らかであるという証になるのです。その時、人間は消えるんです。
中村
この小さな世界になんとたくさんの意味が込められているのでしょう。柚子をちょこんと置くことで人間の作為を消すなんて、いつ誰が考えたのでしょう。
土井
作為のないところにお天道様の秩序があると思うのです。天盛りは、昔からのおまじないみたいなものですが、何か大切なものを守っている。視覚的にも綺麗ですが、真っ白な上用饅頭の真ん中に赤い点を打ってもらうことで気が収まると思いませんか。
中村
天からの授かりものということで、徹底的に考えてやりながら名を消して出す。日本人ですね。今、社会からその心意気が消えてしまいました。一流の仕事をやりながら、俺じゃないよって知らん顔するというその美しさ。
土井
「用の美」を唱える民芸は匿名のもの、そこには自己主張がありません。人間の作為が見えると薄っぺらいものになります。お料理も、素材と相手の為を考えて無心に徹するところから美しいものが生まれてくる。民芸にも料理にも通ずる心は道具になりきるということかもしれません。道具は決して自分を美しく見せようとせず、ただその先にあることの為に存在します。それが用のものの美しさですし、職人さんの仕事も常に次のものに与えていくことに徹しています。
場の研究所の清水博先生(註2)は、見返りを求めない純粋な「与え」を与贈(よぞう)と呼んで、その大切さを唱えていらっしゃいますが、そうした純粋なところに美しさが生まれるということが不思議です。
中村
自然だけで生きるのではなく人工の世界を作るけれど、それが主張をし、時に自然を壊すようなものでなく存在する。日本は、自然の一部としての人間の生き方を上手にやってきたんですね。家庭料理は日常の中ですべての人が職人技を身につけるよい機会かもしれませんね。畑で野菜を育てるところから、その野菜やお魚をどんな風にお料理するかというすべての過程に大事なことが詰まっています。
土井
本当にそう思います。お料理する時、食材に手を触れます。その時、自然と触れ合っていることになりますね。山や海へ行かなくてもお台所で自然と触れ合える。いくら頭で考えても新しい料理なんて思い浮かびませんけれど、この南瓜で何ができるかなと手に取っていると、手が考え出すのか本当に新しいことができますよ。器を並べたり盛り付けたりする時も、自分の頭が考え出すより先に無意識の美意識を信じて手を動かすほうがよいようです。
中村
手と頭は生きものとしての人間の特徴です。それを連動させて働かせることで、美しく自然になじむものを生み出せるのですね。

(註2) 清水博【しみず・ひろし】
1932年、愛知県生まれ。東京大学名誉教授。NPO法人「場の研究所」所長。専門は<いのち>の科学、生命関係学、<いのち>と場の哲学。著書に『場の思想』など多数。
5.いかに不味くしないか
土井
意外に思われるかもしれませんが、和食で大事なのは視覚、次が触覚です。舌触りのよさ、熱いか冷たいか、硬いものから柔らかいものまで和食ほど幅広い食感とその組み合わせによる豊かな味わいを持つ料理はありません。美味しいと感じる時、ひんやり冷たいとか、コリコリ、カリカリという食感一つ一つが美味しさを補完しています。補完というより、熱さ、冷たさを感じる触覚が味覚より優先されるんです。熱過ぎたり、冷た過ぎると味がわからなくなりますが、ご飯は炊きたての熱々を喜ぶのも日本人の特徴です。ご飯の美味しさはやや冷め加減が一番よくわかります。ぷんとご飯の匂いがする塩おむすびの美味しさがそれです。
中村
和食は、まずはお料理の見え方、舌触りに関わる食材の切り方、器への盛り付けなどが大事で、味覚は最後でいいというのは面白いです。総合なのですね。
土井
味覚は、味付けと関わりますから人工的なものになります。味覚を料理の中心に据えると和食から離れて行きます。 スペインのバスク地方のあるご家庭で肉料理をごちそうになった時のことです。お肉を焼いてくれ、それを小さく切ってフォークで刺して食べたら「豚肉だけ刺すんじゃない。赤ピーマンのオイル漬けなどをいろいろ合わせて刺しなさい」って。お肉だけでは食べものじゃない、組み合わせを工夫して初めて食べものになるって。そのサンセバスチャンという町は、楊枝にいろいろ刺して食べるピンチョスの発祥地です。西洋の人はお刺し身を出されても、ただ包丁で切った魚の切り身をどう評価したらよいかわからない。でもそこにクミンなどの香辛料を少々かけると「このマリアージュ、あなたのアイデアは素晴らしい」と褒めてくれます。何かを組み合わせることが外国向けには大事ですね。
中村
でも、お刺身の盛り付けは美しいですし、ツマなど組み合わせがありますけれど、そういうところを見てもらえるように、日本から発信したいですね。組み合わせは生きものの世界が得意とするところです。私たちの体を構成している部品は決して注文品でなく、あり合わせを組み合わせる工夫から新しい生きものが生まれてきます。その中で選択されたものがこのような多様な形で存在しているのです。
土井
和食の美しさは、お膳に至るまでにどれ程のけじめがつけられて来たかという仕事振りの結果としてあるのです。海で漁師が釣った魚が港に水揚げされ、トラックで運ばれ市場の仲卸が魚を締める。その魚を料理人が包丁で綺麗にさばく。食卓にお造りが上がって、それを綺麗だな、美味しいなと感じる時、そのお造りに関わった人の工夫のすべてが表れているのです。鮮度を保つ技術は日本が世界一です。一つ一つの過程で人間にできることは、いかに不味くしないかという、その積み重ねです。
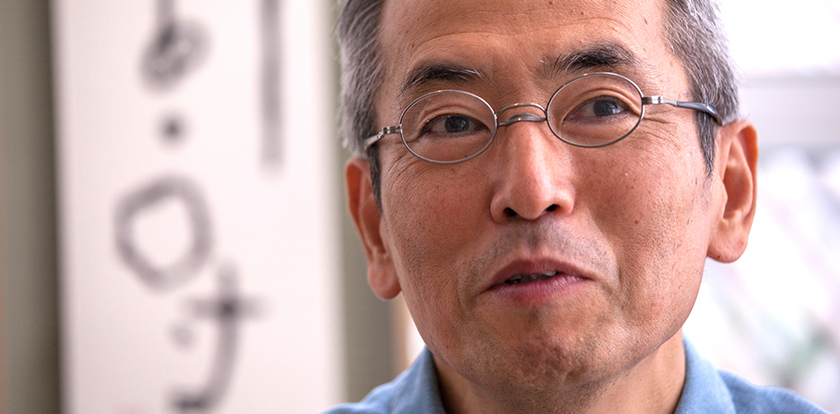
中村
手を加える時はどうしてもプラスを考えますが、不味くしないという一見マイナスの思考が実は自然の中での積極的な生き方かもしれないのですね。今ちょっと引き算の生き方が大事になっているように思います。
土井
その工夫が結晶した和食を介して皆で自然を楽しむのです。中村先生と話していると、和食の考えが深まります。
中村
いつも庭のお掃除をしながら思うのです。落葉が消え、庭が綺麗になると達成感があります。でも外からいらした方にそのことはわからない訳です。花を植えれば「あら綺麗ね」と言っていただけるけれどお掃除は形には残らない。でも自分にとってはとても意味があることなのです。お料理にもそういうところがあります。見えないところに込めた気持ちというのでしょうか。「その喜びこそ本当の喜びだよ」と皆が思える文化が理想ですね。
土井
真善美という言葉があります。偽りのない真実であること。悪意なく善良であること。そして混じり気のない澄み切った美しさ。人間がもっとも好む三つの要素です。日本語の「きれい」という言葉の中には真善美のすべてが詰まっていると思います。「きれい」を道しるべにお料理すれば美味しいものができますよ。
6.綺麗は秩序をつくるもの
土井
流れる水は腐らないと言いますが、水が豊かだからこそ日本の食文化はあるのだと思います。おひつに残ったご飯を手で掬って食べた時、水と一つになったご飯粒は何とも美味しいものです。和食は水をどう扱うかで美味しさが決まります。
中村
以前、イギリスのあるご家庭に一週間ほどお世話になった折、お台所のお手伝いと思って水を流しながらお皿を洗ったら「水を無駄にするな!」と怒られてしまった。向うでは、盥の中の水で洗ってそれでお終いなんです。水で洗い流さないと綺麗になったとは思えませんから私は馴染めませんでした。私たちは幸せですね。日本はほんとうに水が豊かですから。

土井
綺麗ということの起源はおそらく日本の気候風土がつくる豊かな水にあるのでしょうね。汚れた手を綺麗な水で洗えば気持ちよく、それは禊やけじめになります。日本ではどこにでも綺麗な水があるので、それを当たり前と思ってしまいますが、世界を見れば必ずしもそうではありません。仕事を終えて湯槽に湧かした風呂に入ってスッキリするのは、生まれ変わるような気分ですが、水に恵まれているからこそ味わえる贅沢です。
中村
日本文化の基盤は水ですね。だから大事にしないと。
土井
日本は弥生時代の頃から稲作や漢字を始めいろいろな文化を大陸から取り入れて来ました。でも綺麗や清潔という価値感だけは独自のもののように思います。
中村
「きれい」という言葉の原点は清らかであるということですね。
土井
「きれい」とは自然を汚さないということ、自然が持っている秩序を映す鏡のような在り方を言うのではないでしょうか。複雑であってもそこに秩序があるということが、目に見える「きれい」という形で現れてくるように思います。日本は豊かな水を生かして稲作のために水田を作り、その水を制御する灌漑のしくみが更に洪水を防ぐように働くという自然との共存が見事ですね。
中村
現代社会では、水も資源として見てしまいます。確かにそのような面はありますが、実は水があったからこそ生きものが生まれたのであって、私たちが先にあって水があるのではありません。ですから恵みとして受け止め、大切に生かすことで本当の豊かさが生まれるのですね。
土井
日本人にとっての自然観は豊かな恵みを与えてくれるものですけれど、例えば砂漠で暮らす人々にとっての自然観はもっと過酷なものでしょう。私たちは同じ自然という言葉も全く違う意味で使われるということを、砂漠の民や西洋の考え方を理解して、想像しなくてはいけませんね。
中村
日本のように穏やかな文明ばかりではありませんからね。でも今、世界が直面している地球環境の問題を考えると、この局面を救えるのは穏やかさであり、自ずから生ることであり、更にはあらゆるものを上手に取り入れ、美しく、美味しくする「和える力」なのではないかと、かなり真剣に考えているのですけれど。

土井
多様な価値を尊重してうまく調和させるということですね。
中村
嫌だとは言わず、いろいろ取り入れて新たな味わいを創出する。漢語を入れ平仮名を編み出し更に英語まで取り込む。漢字仮名混じり文って情報量が多いのに表情豊かでパッと読めて大変便利な発明だったと思うのです。一つの価値観に凝り固まって一直線の進歩を求める時代は終わり、調和を尊ぶ生き方の時代になるように思います。
土井
進化ではなく、深化することですね。中村先生の著書で、「科学って正しい必要はありません。アインシュタインだって間違えるんです。科学はきちんと見て、きちんと考えて私はこう思います。と言えばよいのです。」という言葉を見つけた時とても嬉しかった。わからないことでも自由に想像して自分なりに考えて行けばよいのだと、背中を押してもらった気がしたんです。
それで料理について色々と考えを巡らせました。洋食は、食材がどうあれ常に料理人が決めたその味を作り出す安定した世界です。一方で和食は、味が常に揺らいでいます。いつも変化しているという感じがするのです。すべての食べものは、海や川、山や畑で採られてからもずっと変化し続けています。そのうちのある瞬間を私たちはいただくわけです。和食というのは、常に揺らいでいる時間の中にある命、「生きている」ことを扱う独特な仕事です。それゆえに生命誌というものの中にヒントがあるように思えるのです。中村先生の生命誌というお考えを知り、ゲノムというものが自分の体の中にあると意識できるようになると、食べものの美味しさを感じる時、外なる自然と内なる自然が結んで、体の細胞の一つ一つが喜んでいることがわかるような気がしてきます。腸内細菌も含めての調和が穏やかな気持ち、食後の心地よさにもつながるのではないでしょうか。
中村
なんと嬉しいお言葉でしょう。私もそう思うのですが土井さんに言っていただいたら百倍もの重味がつきます。お料理と生命誌は面白いくらい重なりますね。ほんとうにたくさん教えていただきました。美味しいお料理をいただいて素敵な時間をありがとうございました。美味しいものをいただくと幸せになることを実感しました。
写真:大西成明
対談を終えて
中村 桂子
心のこもった一汁一菜に豚の角煮や白なすなどのおいしいおかずをいただきながらの対談は至福の時でした。奥様のお手料理です。そこで、世界遺産になった和食は家庭料理なのですとおっしゃられたのがとても印象的でした。私たち一人一人が生きることに向き合うことが世界に誇る日本社会をつくっていると実感しました。清らか、きれい、などという日本語が土井さんの言葉として語られると美しく、内容のあるものとして胸に響きます。食は生きる基本です。
土井 善晴
そもそもラジオから聞こえてきた、明晰なお話しぶりに、ひきこまれたのが始まり。御本を読んで、ぜひお会いしたいと手紙を書いて大阪の館を訪ねて、今日で2回目。科学は、自然と人間の関係を調節して、気持ちよく生きるためにある。未知なるものへのつつましさ、「私は偉いぞ」とおごる気持ちをいましめる。そして、暮らしが大切。いつの間にか安心に包まれて、やさしき母親と話すような気持ちになるのです。そして、それは健康の秘密、を、証明するように、しっかり我が家の料理をめしあがってくださって、ほんと、うれしかったのです。

土井 善晴(どい・よしはる)
1957年、大阪生まれ。スイス、フランスでフランス料理を学び、帰国後、大阪「味吉兆」で日本料理を修業。土井勝料理学校講師を経て1992年に「おいしいもの研究所」を設立。変化する食文化と周辺を考察し、持続可能な日本らしい食を提案する。著書に『おいしいもののまわり』『一汁一菜でよいという提案』ほか多数。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)














.png)