顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。
バックナンバー
言語誕生のマイスタージンガーモデル(前編)
2018年1月9日
これまで言語誕生について、断片的に書き留めてきたことの中間まとめを2回に分けてお届けする。脈絡なく書き留めてきた文章になんらかの筋を汲み取ってもらえればありがたい。一種の書き下ろし原稿になっているので、この文章だけで十分理解してもらえると思う。またこの原稿を通して、言語を考える時に参考になる本を紹介する。
言語誕生を促す2つの契機

互盛央さんの「言語起源論の系譜」(図1)を読むと、人間は言語を話す自分に気がついてからすぐ、自分の使っている言語はどのように生まれたのか考え続けてきたようで、この問題は少なくとも2500年の歴史がある。しかし、人間の脳との関わりで議論が始まったのはやはり20世紀で、中でも私たちの言語能力は決して学習するものではなく、生まれつき備わっているものだとしたチョムスキーのUniversal Grammar仮説は影響力が大きく、言語の起源をめぐる議論の中心になった。
図1互盛央さんの『言語起源論の系譜』(講談社)
言語起源論の歴史を知るには面白い本で、深い知識に裏付けられている。
チョムスキーは、言語発生がコミュニケーションの延長線上にないことをことさら強調することで、universal grammarを前面に出して言語の発生が統語能力の発生であるとする論陣を張った。これに対し、言語発生には、人類特有の新しい社会関係を支えるコミュニケーション能力が必要だとする陣営は黙ってはいなかった。現状はというと、(個人的印象だが)言語誕生の背景に人類特有のコミュニケーション能力の進化があると考える人の方が今では多くなっているように思う。
この論争についてここで詳しく解説する余裕もないし、またどちらを支持するのかという議論をするつもりはない。代わりにこの原稿では、普遍文法もコミュニケーションの能力も、言語誕生に必須の独立したモデュールとして考える。すなわち、チョムスキーの普遍文法が提起した統語の問題を、行動についての表象能力の問題、ボキャブラリーの問題を作業記憶過程での連合の問題、そして言語の誕生に関わるコミュニケーションの問題を、自分を含む社会のゴールの表象の問題として捉え、これらが交わるところに言語が発生したという観点から考えてみたい。
比較進化学として言語誕生を考える
言語は人間特有の能力で、地球史におけるそのインパクトは、地球上にこれほど多様な生物をもたらせた進化を可能にした生命最初の情報DNAにも匹敵する。言語を持つ人類ののみが文明を発展させ、他の生物を圧倒する繁栄を遂げた。その結果は地球の環境も変化させる力がある。例えば、もともと地球上にO2と表現される自由酸素はほとんどなかった。しかし、生物が誕生し、その後光合成を行う生物が進化すると(おおよそ35億年)地球上でも酸素が作られるようになり、生物の繁栄とともに10億年前から急速に濃度が上昇した。この変化は全て、進化を可能にしたDNA情報の誕生の結果だ。
同じように、現在地球温暖化の元凶と言われる2酸化炭素の蓄積をもたらしている工業化の問題は、元をたどると言語という全く新しい情報媒体誕生まで遡ることができるだろう。言語誕生を5万年から10万年と考えると、これほど短い期間に人類を繁栄させ、地球の生物相や大気成分までを大きく変化させる力を言語は持っていたことになる。事実、千年前は人間、家畜、ペットの哺乳動物に占める割合は1%に満たないと推定されているが、現在は何と98%に及んでいる。これは決して人間の筋力が他の動物に比べて強いからではなく、人間だけが言語を獲得した結果に他ならない。
このように人類だけが地球上で言葉を使い、文明を発達させ、地球の大気すら変化させた。では言語はどのように現れたのか?この過程を「創発」という言葉で終わらせるのは思考の停止だ。実際には見ることができない過去に起こった言語誕生を理解するために、現存の人間特有の能力と、他の動物、特に我々に最も近い霊長類の能力を比べ、それぞれの違いを理解した上で、各能力と言語の関わりを探る研究が続けられている。
言語誕生に関わる変化のうち一番わかりやすいのが、喉頭の解剖学的構造だ。口腔から離れた下の方に喉頭がある人間と比べると、霊長類の喉頭は口腔・鼻腔直下にあるため、声帯で発生させた音を口腔内で操作することができない。結果、私たちのように多様な母音や子音を発生することはサルには不可能だ。サルが発生するほとんどの音は鼻で増幅する鼻音として発声される。このため言語に必要な複雑な音を発生することは霊長類ではできない。
ただ、発声に必要な解剖学的特徴は言語に必要なモデュールのほんの一部でしかない。もっと重要なのは、記憶とコミュニケーション能力に起こった変化で、この条件が揃わないと、オオムと同じことになる。手短に、人間特有のコミュニケーションと記憶能力について見ておこう。
目的と意図を共有する新しいコミュニケーション様式の誕生
映画「猿の惑星」でサルも進化すれば人間と同じ能力が獲得できると描かれているように、私たちの興味はともすると「サルはがどこまで人間に近づけるか」、すなわち「サルでもできる」ことに向きがちだ。例えば、膨大な努力を払って、チンパンジーやボノボに言葉を教える研究がその例だ。これまでサルが100語以上の単語を正確に区別でき、覚えた単語を使って意思表示も可能であることなど示されている。しかし、言語誕生の条件を考える上で本当に重要なのは、間違いなく人間にはできてサルにはできないことを明らかにすることだ。実際には、できないことを証明するのは難しく、また一つの仮説の検証に、時間をかけてサルを訓練する必要があり、手間のかかる大変な実験だが、この努力のおかげで「サルにはできない」幾つかの人間特有の能力が特定されてきた。中でも、ライプツィヒのマックス・プランク進化人類学研究所(Max-Planck Institute of Evolutional Anthropology)のマイケル・トマセロ(Michael Tomasello)は、同じ課題をチンパンジーなどの類人猿と、様々な年齢の人間の児童に行わせて、人間特有の能力とは何か、またそれがいつの段階で獲得されるのかを丹念に調べている。彼が2014年に出版した『Natural History of Human Thinking』はこの分野に興味のある方には是非読んでいただきたい著書だ。

図2:Tomaselloが2014年に出版した人間の思考についての著作『Natural History of Human Thinking』(Harvard University Press)。多くの実験事実の裏付けられており、アカデミックな読み物。
Tomaselloをはじめ、この分野の多くの研究者が一致しているのは、人間特有のコミュニケーション様式を生み出した社会性が「一種の利他性」だという点だ。しかし、利他性なら母親が子供の面倒をみるcaringや、オスとメスがつがいを作って(pair bonding)暮らしている動物にも存在するはずだ?
たしかに、人間の持つ利他性の究極の起源にはcaringと同じ情動の仕組みがある。たとえば一見利益の反する行為も促すことができる「ご褒美回路」として知られている仕組みは、人間の利他性にも働いていることはまちがいない。しかしサルと人間を比べると、人間の協力関係だけに、「他の個体とゴールと意図を共有する」という特徴が見られ、これが動物の利他的行動には欠落していることがわかる。
Tomaselloの実験の一つを紹介しよう。お菓子を手に入れるのに協力が必要だが、得られるお菓子は一回に一人分しか出てこない機械を挟んで座った2人の子供、あるいは2匹のチンパンジーの行動を観察し、お菓子を順番に手にするために、相手が先にお菓子を手にするのを我慢できるか調べた実験を行うと、人間の子供は(3.5歳齢以上)協力して「今は僕、次は君」というように順番にお菓子を分けるのに、チンパンジーでは偶然に協力関係が成立することはあっても、自分が我慢を強いられる順番があることを受け入れられず持続的な協力が成立しないことを示している(Melis et al, Psychological Science, vol 27, issue 7, 987-996, 2016)。
集団行動という点で見れば、チンパンジーなどの霊長類も肉を求めて複数の個体が協力して小さなサルの狩りを行うことはよく知られている。しかし、一見協力して行われている狩もよく観察すると、各個体は自分が獲物にありつくという目的だけを考えており、獲物を得て分け合うという共通の目的を共有することはできない。
共通のゴールを共有する協力関係には、個体同士で指示をし合うコミュニケーション、すなわち相手の意図が理解でき、自分の意図を相手に理解させることが必要になる。このような指示関係が最初は自然発生的に成立しても、同じことを繰り返すためには、上記の論文のタイトルにあるように「今度は君、次は僕」といった取り決めを両方が確認する必要がある。先に述べたTomaselloの論文でも、協力し合う3.5歳児は、指差し(ポインティング)を用いてコミュニケーションを図っていることが記載されている。このように「君と僕」といった2人の間の比較的簡単に見えるコミュニケーションでも、人間だけにしか、しかも3.5歳児になるまで観察することができない。もっと多くの個体同士がゴールを共有して協力するとなると、さらに高次のコミュニケーションが必要になることだろう。
ではこのような意図の共有はどのように発生してきたのだろう?もちろん正解があるわけではないが、多くの研究者は共同生活するグループの人数が増え、社会構成が複雑になったことが大きな原因だとかと考えている。この根拠として最もよく引用される研究がロビン・ダンバー(Robin Ian MacDonald Dunbar)らが1992年に発表した論文だ(Dunbar RIM, Neocortex size as a constraint on group size in primates, Journal of Human Evolution 20, 469-493, 1992)。
この論文の要点は、霊長類から現代人までの新皮質のサイズと共同生活での集団のサイズをプロットすると両者が正比例することだ。すなわち、集団構造の複雑性と、脳のサイズが正比例することを示している。アフリカでの最初の人類誕生はおおよそ400万年前だが、脳の新皮質の急速な増大がみとめられるのは200万年後、Homo.Ergasserが誕生してからで、彼らのグループの人数も、それまでの50人以下から、100人近くに倍増していると考えられており、Dunbarの仮説を支持している(図3にDunbarの最近の著書1冊を紹介しておく)。
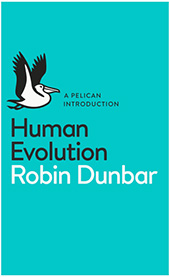
図3 Dunbarが2014年に出版した『Human Evolution』(Pelican)。何が我々人間の進化を後押ししたのか、言語誕生に至るまでわかりやすく書かれている。
最初の原人がアフリカに誕生したあと200万年間、人類のハンティングは、死体や食べ残しの骨をかすめるハイエナのような狩りだったと考えられているが、H. Ergasserになると人間より大きな獲物を求める狩りが始まった。石器の進歩は10万年前まではゆっくりだが、それでもH.Ergasserの石器には動物を殺すための進歩が見られる。いずれにせよ、100人程度の共同生活が可能になるためには、野生のチンパンジーの狩りとは違って、獲物を分け合う集団生活が行われていたと考えられ、ゴールや意図を共有して協力する社会が形成されていた。
重要なことは、この複雑化した協力関係や利他性の背景には、必ず新しい表象と統合システムが脳内で形成されているという点だ。このシステムの要件として、
- 1)自分の身体や内的自己を他人から区別し自分のものとして認識する能力、
- 2)他人の行動の目的について表象する能力、
- 3)他人も自分と同じように考えていることについての理解(Theory of Mindと呼ばれている)
- 4)自分が相手と同じであると相手が認識していることを理解する能力
など、自己と社会との関係についてハッキリと表象が形成される必要がある。実際、類人猿から人類まで、この能力拡大に伴って新皮質が急速に発達した。加えて後に説明するように、こうして生まれた表象が成立するためには、経験が記憶されるだけではなく、抽象的な意味記憶、すなわちカテゴリーや意味の記憶を基準として、感覚を通して体験するエピソードを選択し、表象し、記憶することが必要になる。脳が大きくなったというだけでなく、新しく発達した領域と既存の領域間のネットワークが形成され、より複雑な表象の形成が可能になった。
だからと言って、H.Ergasserやその後の原人(Hominin)のコミュニケーションが言語を使っていたと考えてはならない。実際言語はH.Ergasserどころか、ネアンデルタール人も使えず、Homo Sapiensが現れて初めて使われるようになったと考える研究者が多い。
実際には、コミュニケーションの手段自体より、新しいレベルのコミュニケーションが可能になったことがまず重要で、H.Ergasserが約200万年前に現れたとすると、その後190万年以上の間、5万年から10万年前に言語が誕生するまでの原人のコミュニケーションは、ジェスチャーや、スティーヴン・ミズン(Steven Mithen)がHmmmmm(Holistic manipulative multi-modal musical and mimetic)と呼ぶ、自分の意思を伝えるための分節されてない音楽的な発声(赤ちゃんの発声の意図を周りが受け取って要望を満たすといったシーンを考えればいい)で、実用的には間に合っていたと思える(図4にMithenの著書を紹介しておく)。
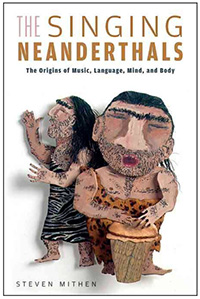
図4 Mithenが2005年に出版した歌うネアンデルタール『The Singing Neanderthals』(Harvard University Press)。言語誕生に音楽が果たした役割を示す面白い考え。
しかし、意図を共有したコミュニケーションを可能にする脳構造のおかげで、集団的な狩りの成功率は上昇し、その結果タンパク質の豊富な肉の消費量は上昇し、脳の拡大は更に加速したことだろう。このように、5−10万年前まで、集団で獲物を追いかけるHunter Gathererが目的を共有し分業により獲物をしとめる暮らしには、私たちが考えるような複雑な言語がなくても、ジェスチャーやHmmmmmで十分済ますことができたと思われるが、おそらく脳自体は大きくなり、より言語の誕生を支える可能性が高まったと思われる。
コミュニケーションを求める力動は言語発生の必須条件
では、ゴールを共有する社会性を持つことが言語発達にどのような影響を持つのだろう?進化の過程でこれを検証することは、現在はまだ難しい。しかし、人間の言語発達過程にこの社会性が重要な役割を持つことは、自己と社会との表象が変化する自閉症スペクトラム (ASD)やウイリアムズ症候群(WS)の解析を通して認められているので、短く紹介しておく。
ASDは、社会性の低下、言語発達障害、そして反復行動を主要な症状として示す発達障害を指し、症状は同じでもその原因は極めて多様であると考えられており、そのため自閉症という病名ではなく、自閉症スペクトラムと称す流ことになっている。原因はともかく、知能の発達が正常でも、社会性の低下と、言語の発達遅延が必ず合併していることから、他人とのコミュニケーションを求める力動が言語発達に必要な条件であることを示す例として考えられてきた。事実、ASDは乳児期から能動的に体験を求め外界へ働きかける行動が見られないことがわかっている。正常児では生後3−4か月までに相手の顔をじっと見つめ、動くものを目で追いかけ、音がする方向に顔を向ける動作が見られる。ところがこのような反応がASDではしばしば欠けている。このため米国疾病予防管理センターは、「もしあなたの子供が、音に反応せず、動くものを目で追いかけず、笑わず、指をしゃぶらない」なら、すぐに専門医に相談するよう勧告している。おそらく胎児発生の過程で形成される脳の回路が普通とは違っていたため、外に経験を求める力動が低下して、コミュニケーションを求める欲求が減ったため、結果としてコミュニケーションの媒体である言語発達を求めないのだろうと考えられる。
このような解釈は、都合の良い現象を集めただけの、思弁的な想像だと思われても仕方ないが、もう一つの例ウイリアムズ症候群について知ると、まんざら間違っていないように思えてくる。
ウイリアムズ症候群は1961年外科医により「大動脈弁上部狭窄症と特徴的精神症状を示す」一群の患者の存在として記載された。その後の研究で、7番染色体上の大きな欠損によりその領域にある20種類の遺伝子が片方の染色体ごっそり抜け落ちてしまっていることがわかった遺伝疾患だ。もちろん病気の詳しい解説をするつもりはない。重要なのは、この患者さんたちが自閉症とは逆に「相手の目をじっと見つめる、愛すべき人懐っこさを持つチャーミングな性格」を持つことと、知能の発達が障害されIQは60程度であるにもかかわらず、言葉を話す高い能力を持っている点だ。実際には、知能発達の遅れのため言葉を話し始める時期は遅れるのだが、一旦言葉を話し始めると多弁で同年齢の通常児を凌駕する。すなわち、社会性と言語能力の関係という観点から見た時、ウイリアムズ症候群の患者さんには自閉症とまるで反対の症状が併存している。このことは、「愛すべき人懐っこさと称される高い社会性」が、知能発達遅延による言語発達への影響を克服できるだけの力があることを物語っている。
これらの例は、個体の発達から見ても、コミュニケーションを求める力動、すなわち社会性が言語発達の条件になっていることを示している。この意味で、言語のコミュニケーション機能を無視する考えには賛成できない。
※「言語誕生のマイスタージンガーモデル(後編)」は2018年2月1日に公開します。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)