GREETING 20周年のごあいさつ
科学であり芸術である
作品づくりを求める源流と展開
小さな生きものたちが語る物語りを読みとり、それをさまざまな形で表現しながら、生きているとはどういうことだろうと考え続けているうちに早や20年がたちました。思い起こすと頭がはちきれそうになるほどたくさんのしかも多様な方々や事柄が浮かんできます。興味深いことに、そのどれもがお互いにつながり、生きているというところに集まっていきます。それが「生命誌」を創り、「研究館」を豊かな場にしてくれました。色とりどりの糸で編まれたハンモックの中にいるような感じです。一方、どう生きるかを考えると自然も社会も厳しさを増しています。その中で私たちにできることは、誰もが生きものであることを実感できる社会になることを願って生きものの物語りを発信し続けることだと思います。「生命誌研究館」という言葉の実態を創りあげることがこの20年間の私たちの活動でした。容れ物は小柄ですが、おかげさまでその中味は充実してきていると思います。
それができたのは、出発点で岡田節人館長から漂ってくる香りが、「生命誌研究館」そのものであったことが大きいと思います。まず専門の発生生物学への姿勢です。イモリの細胞を類希なる美しい存在として愛づることがすべてであり、出張の帰りがどんなに遅くなっても細胞の御機嫌を伺わずには一日が終わらなかったという話に若い研究者たちは生きものの物語りに耳を傾けるとはどういうことかを学びました。
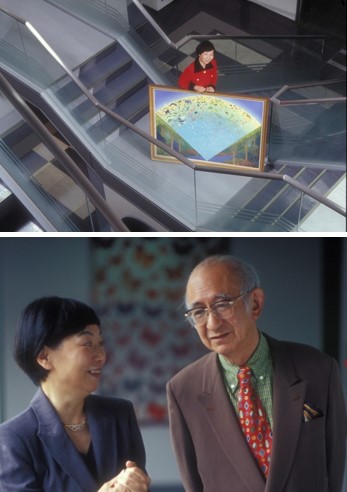
上:生命誌絵巻と中村桂子
生きものが語る"生きものの物語り"である生命誌版「ピーターと狼」を作成したころ(季刊「生命誌」8号より)。
下:生命誌研究館4階Ω食草園の前にて(季刊「生命誌」38号対談での一コマ)
中村桂子(左)と岡田節人(右)。
細胞が美しい時にはよい成果を見せてくれると言われるとなるほどと思います。そして細胞間の関係をゲーテの「親和力」、更には仏教の「縁」という言葉で語るお話はまさに生命誌です。再生という現象が見せる"しなやかさ"と"したたかさ"を生きものの本質と見て、私たち人間は大きな脳を手にするのと引き換えにその能力を失なったのかもしれないとも言われました。
季刊「生命誌」に20回近く連載された「音楽放談」は、毎回生きものの研究をしようとする者は、このようなセンスがあってこそなのだと思わされる話ばかりです。ハイドンの「天地創造」の序曲に太古の生物の海中の暮らしを聴き、植物光合成の出現、カンブリアの大爆発などをハイドンは喜ばしい音楽としたという語りに、周囲にいる私たちがどれだけ豊かな気持を育てることができたかしれません。
最初に始めたオサムシ研究、岡田節人、大澤省三という昆虫少年と最先端での研究者とが融合しているお二人のいかにも楽しげな様子こそ生命誌研究館の原点です。幸いその雰囲気は今も研究館を包んでいます。訪れる方が、ここには独特のゆったりした空気が流れていますねとおっしゃいます。この20年間になぜかギスギスしてきてしまった外の世界にもこの空気が流れていきますように。これからの生命誌研究館の仕事です。

生きているってどういうことを皆で考え、生命を大切にする社会作りに向けて発信していきます。これからもぜひこの活動にご参加ください。

上:1999年11月20日開催のサロンコンサート「縁-生物学者と音楽の-」の一コマ
生物学に詳しい音楽家とまで言われる岡田節人前館長(左)と法然院貫主の梶田真章さん(右)。
中央:アマチュア昆虫家や地質学者との協力で、大陸移動と生物進化の重なりから自然を見る研究の先鞭をつけたオサムシ研究
研究と表現が融合したオサムシ展示は、15年経った現在も生命誌研究館の重要な柱です。
下:宮沢賢治『土神と狐』の仮面劇を生命誌研究館にて上演(遠藤琢郎演出、2006)
生命や自然、科学を含めての人間の知を基本から考える必要を感じたとき、宮沢賢治に向き合うと何かがみえてきます。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)
.jpg)











