SYMPOSIUM
対談
科学を私たちの言葉で
壽一総合地球環境学研究所所長

1.空を飛べなかったサル
永田
今日はまず山極さんに、霊長類の進化も含めて人間が言語を獲得し、どのように文化が築かれたかとスケールの大きなご講演をいただきました。お尋ねしたいことも多々ありますが、まず小川洋子さんのご感想からお伺いします。
小川
人間だけがなぜ言葉を話し、書き言葉として文字を持つようになったのか。科学的な証明は難しいと思いますが、その起源に音楽を持ってこられたところに実感として共感します。例えば、バレエを見ると、自分が言葉で書く小説って、一体、何なんだろうと、身体や音楽による表現に打ちのめされる気がします。山極先生は、どういうところから音楽と言葉を結び付けられたのですか。

山極
ドラミングと言って、ゴリラは両手で胸を叩く。パーカッションですね。チンパンジーは胸を叩く代わりに足を踏み鳴らしたり木の幹を叩いたりします。音楽は自己主張から始まったと思うのです。これは二足で立たないとできません。もう一つ、パントフートと言ってチンパンジーは合唱します。「フーホフーホフーホッホホ」って、俺、チンパンジーじゃないからうまくないけど(笑)。ゴリラは「ウウウーウウウー」ってハミングする。これもメロディーです。ゴリラの鼻歌は1頭でやる場合が多く、物静かな雰囲気で皆が満足してる時、それが伝染して行きます。チンパンジーは興奮。人間に合唱も鼻歌もありますね。音楽は仲間と一緒に感情を共有する。しかも身体性を伴います。音楽のほうが起源は古く、言葉はずっと後だろうと思います。
小川
山極さんは、シジュウカラの研究をされている鈴木俊貴さんと『動物たちは何をしゃべっているのか?』という共著を出されましたが、鳥の囀りも音楽ですね。
山極
実はサルって、元々、鳥になりたかった動物だと思うんです。最初の霊長類は、恐竜が滅び始めた6500万年前頃に現れ、夜の世界でひっそりと大型恐竜の子孫に食べられないよう地上に隠れ住んでいました。昼の世界は鳥が占有していた。その後、だんだんと体を大きくして霊長類も鳥に勝てるようになり昼の世界に進出した。でもサルは飛べません。だからその子孫の我々は今も飛ぶことに憧れている(笑)。空に進出した鳥は、3次元の世界を自由に飛び回り、声を自在に操って、遠方ともコミュニケーションしていました。我々は地面から離れられません。でも、遠くまで出掛けていった仲間が情報を持って帰ってくる。それを示すのに一番手っ取り早い手段が声でした。声で意味を伝え合うことを始めたのが言葉の始まり。言葉によって人間は、やっと鳥と同等のコミュニケーションを獲得したんだと思います。

小川
アウシュヴィッツに送り込まれた子供たちが、チェコの収容所にいた時にこっそり絵を描いていて、その展覧会を見たことあるんです。多くの子供が、なぜか蝶と鳥を描いてる。空を飛べるということは、塀の向こうに行く、自由の象徴ですね。
人間は飛べない代わりに、二足歩行して両手を使って踊り、叫び、いつの間にかそれが言葉になった。今やってるラグビーワールドカップで、サモアやニュージーランドの選手が試合前に独特な踊りをします。あれを見ると、自分の中にある古い記憶が揺さぶられるような感触に襲われて無性に感動してしまう。あれは、死を覚悟した歌と踊りだと思うのです。これから生きるか死ぬかの勝負に出るという気迫が感じられて、狩猟に出掛ける際の家族に別れを告げる歌が発祥ではないかと想像します。踊りやリズム、音楽は底が深く魅力的で、言葉ってなんて薄っぺらなんだろうという気持ちになってしまいます。
2.いまはむかし
永田
言葉の起源として声と身体が重要ということですが、音楽はアナログなもので共感につながる気がします。一方、言葉は共感と同時に疎外をもたらす。デジタル化してしまうのです。山極さんの話で、チンパンジーの歌は自己主張だと思います。ゴリラは共感という面も強かったけど、言葉って究極のデジタルだと僕は思うのです。デジタル化とは切り取ることで、自分はこう思う、こう見る、世界をこう認識するという自己主張でもある。言葉には共感をもたらす面と、逆に、自分を他から切り離し疎外をもたらす両面がある。これがどこでどういう風に分かれて来たかを知りたい。やはりアナログとデジタルに帰着しますかね。

山極
音楽は、時間の芸術と言われるように、音と音とがつながり合って流れをつくるのが本質。1音では成立しません。ジェスチャーも同じ。そもそも切り離せません。でも言葉はそれを切り離した。切り離したことで、違うものを同じように捉えられるようになった。類推、アナロジーですね。言い換えができるようになった。これは狩猟に役立った。自分がやっているように、他の動物もお腹が空いたらここへ果物を食べに来るだろうという重ね合わせができる。さらに同じ人間なのに、違う集団の人間を区別する。境界線を引くことができるようなった。言葉とは、世界に線を引くことではないか? 小川さんいかがでしょうか。
小川
言葉を用いるようになった代償として、国家、宗教、民族というあってなきが如くの、実体が説明できないものにも名前を与え存在させることができるようになった。
そのために他の動物はやらない戦争するということまで起きてしまったわけですね。
永田
言葉は、時間を獲得することにもつながったと思うのです。言葉がなければ、時間という概念は持てない。山極さんとゴリラとの面白い話がありましたね。26年ぶりに再会したゴリラの…。
山極
タイタスね。
永田
山極さんが、昔、アフリカで観察していた幼いゴリラで、26年ぶりに、もう大人になったそのゴリラに出会った。するとタイタスは、一日目には思い出さなかったんだけれど、二度目に会って、山極さんを思い出したとたん、腹を見せてひっくり返って喜んだ。つまり昔、山極さんと遊んだ幼い頃の自分に戻ってしまった。ゴリラは、今と昔という時間の区別を持たないので、昔を思い出すことはそのまま昔に戻ることになると、僕はそう解釈しているんですけど。
山極
時間は因果関係をつくります。チンパンジーもゴリラも、原因と結果の関係が目の前で起きている分には理解できますが、過去や未来の出来事は関係づけできません。人間は言葉を持ったことで、物事を順序立てて並べ因果関係をつけて、まさに物語にできる。物語をつくったことが言葉の最大の功績ではないでしょうか。
永田
人間は、時間の整合性を離れると不安になる。小川さんの『博士の愛した数式』に描かれたテーマでもありますね。主人公は、80分以上前のことが全く記憶できない。何度読んでも最後やっぱり泣いちゃうとても素晴らしい小説ですけど。

小川
パントマイムは、時間を表現できないそうです。昨日や明日を表現できない。表現できるのは今やっていること。人間は言葉によって、時間の流れを物語としたり読んで味わったりできるようになった。物語によって、自分がまだ生まれていなかった時間も体験できるし、死後の世界を想像することもできる。自分を客観視できることは物語の重要な役割の一つだと思います。自分が世界の中心にいて、自分を中心に時間が巡っているという意識に囚われると息苦しくなるので、自分がいない時間にも世界はちゃんとあるとわかったほうがいい。むしろ自分をどんどん小さくしていったほうが気持ちは楽になる。俯瞰して世界を見れば、自分はちっぽけな、取るに足らない存在だと、そう思ったほうが実は心穏やかに生きられる。小説はその手助けをしていると思います。
3.言葉以前の世界へ
山極
アナログとデジタルという話題に戻りますが、永田さんがご専門の生命科学という分野は、デジタルの考え方と技術にどんどん依存し始めましたね。デジタルは安定で、何度でもくり返すことができるからです。アナログはつながっているので、どこかが変動するとそれが他にも影響して変わりやすく不安定。人間の身体はアナログですが、遺伝子は4種類の塩基の組み合わせですからデジタルと捉えることもできます。この両面性をどう考えたらよいのか。
これまで自然科学は、さまざまな生命現象を、その現象がもつ流れを止めることで解明しようとしてきました。顕微鏡で観察するのは、対象から切り出した切片だし、細胞内の機能を調べるにも、その動きをいったん止めて見なければならない。しかし、生命はアナログで常に動いている。
気候変動シミュレーションもデジタル。ここから予想できても、地球はアナログなので、予想に反して何が起こるかわからない不確実さがつき纏うのです。今日、小川さんに伺いたいのは、永田さんが仰るように言葉はデジタルだけれども、その間に潜むアナログ的な言葉の間にあるものを紡ぎ出し、人々をあっと言わせるのが作家だと思うのですが、一体どうやって考えていらっしゃるのでしょうか。
小川
本を読んで感動するのは、意味を理解したからではありませんね。むしろ意味のレベルを超えて「何なんだこれは!」というところまで連れて行かれた時に感動する。芥川賞の選考会などでも、この小説がいい、私はこれを推したいという説明はとても難しい。「すごい」としか言いようがありません。
作家は、理屈を超える限界点みたいなところを常に目指しています。人間が言葉を獲得する前の世界に読者を導く。宮沢賢治はそれをやろうとした人です。これは文化人類学者の今福龍太さんがお書きになっているのですが、『なめとこ山の熊』で、熊撃ちの名人が、彼はいつも熊に申し訳ないと思いながら熊を撃っていた。ある時、不意打ちで熊に殺されちゃう。すると熊のほうがその主人公小十郎のお弔いをするんですね。狩人の小十郎の弔いをする。その死体の周りを熊たちがぐるぐる回る。それは踊り、音楽です。その時、ここが宮沢賢治のすごいところで、熊という表現を使っていないのです。黒い大きなものっていう表現をしてるんですよ。宮沢賢治が書いているのは、人間が熊という言葉を使う前の世界です。
山極
言葉は、実はほんのわずかな言葉だけで奥深い世界を言い表すことができる。それは言葉の恐ろしさでもある。
永田
言葉はデジタルだから隙間がある。その隙間に秘められているものを探り当てるのが作家であり、歌人ですね。短歌を始めた初心者が、自分の思っていることがなかなか表わせませんと言いますが、詠う前に、詠いたいことはわからない。人間の心を書こうと思っても無理なんだと小川さんも書いておられますね。その人の周りを描写していくところから心の中にあるものを読み取ってもらう。短歌は五七五七七のわずか31文字しかありません。作者が何を言いたいかを読者が読み取ろうと努力してくれないことにはまったく伝わらない形式なんです。読者が読み取ってくれるだろうという信頼の下につくるのが短歌で、小説もそうだと思うのです。

小川
文学作品は、作家の手を離れたら読者とその本、歌集との1対1の関係で、そこに作り手は介入できません。ですから読者の数だけ読み方、感じ方がある。許容量の広い作品ほど残っていくのかなと思います。作家がこう読まれたい、私の気持ちはこうですと書いたら、読み手は自由度がなく、窮屈だと思います。ですから、例えばピントの外れた書評が載ったりしても、ああ、こういう読み方もあるのかとむしろ嬉しくなってしまう。
永田
その通りですね。
4.定住と所有、死者と土地
山極
今、科学が伝わりにくくなっています。それは科学に物語がないから。科学者はなるべく物語にすることを避けます。科学で大事なのは原因と結果で、それを膨らませてしてしまうと、真実とは違うと却下されてしまう。
永田
生命誌研究館は、生命誌の誌は歴史の史でなく、ごんべんに志すなんですね。岡田節人先生、中村桂子先生が館長の時代から、語るということをとても重視しているのです。生命の辿った時間の累積を物語るナラティブを大事にしています。
しかし、山極さんも仰るように一般的な科学、とくに分子生物学、細胞生物学にはデータ以上のことは語らないという不文律があって、もうちょっと言いたいところをグッと我慢して、データから言えるのはここまでというマナーを尊守している。とても大事なマナーなんだけれど、一方でそこに、一般にサイエンスが面白いと思ってもらえない壁があるように思います。今日の山極さんの講演のように、大胆な飛躍がいっぱいで、突っ込みたいところも多々あるけれど、こう考えることができるんだと大きな可能性を示す。そこに科学の存在意義もありますね。

山極
科学は、なぜという問いに対しては答えられない。現象を語るのが科学の説明の仕方です。でもなぜという疑問に対する答えが見えてこないと人々は納得しません。宇宙はなぜできたのか。これには答えられません。科学者は、宇宙はどのようにできてきたかという現象の説明はできる。でも、なぜできたかには答えられない。それが科学の限界です。
永田
科学者は実験して確かめられない現象は対象として扱わない。これは健全な科学の姿です。生命はどのように進化してきたかについて、検証や実験ができるデータに基づきながらどこまで語ることができるか。
小川
科学者は仮説を立てますね。素人から見ると、その仮説が物語的で面白い。なぜ人間は戦争してしまうのか。野生動物はどんなに対立したって相手を全滅させることはしないのに。仮説は立てようと思えばいくらでも立てられる。その仮説には物語る力が必要だと思いますね。
山極
チンパンジーやゴリラの研究を通して人間の過去を見つめてみると、闘争状態は我々の本性ではありませんね。考古学的にも、戦争の証拠は1万3000年ぐらい前までしか遡れないこともわかっています。ではなぜ戦争が始まったのでしょうか。ここからが仮説です。歴史的な過程を調べると、やはり定住と所有ということに結びつきます。人間は狩猟のために武器をつくりました。でも狩猟採集民は、狩猟の武器を人間には向けません。狩猟は経済行為です。相手を殺害するためにやるわけではないと狩猟採集民たちは言います。これは戦争の起源ではありませんね。今、ここを真剣に考えなくてはいけない時代だと思うのです。
永田
山極さんはご著書の中で、戦争の起源に、死者と土地を据えておられますね。自分たちのルーツを持つ。そして農耕時代になって定住する。死者と土地を共通の財産として持つ集団の発生が戦争の起源だと仰って。動物は死者を持たないが、我々は、言葉を獲得したことで死者を持つようになったと考えられませんか?

山極
狩猟採集民たちは死者の名前を保存しません。埋葬もせず、森の奥に捨て置いたり、鳥葬したり。なぜかというと移動して行くから。だから、言葉として記憶が残る範囲は4世代ほどです。墓というものは、その土地に祖先が足を踏み入れてから延々と続いた伝統を示すもの。その土地に住み着いている人々は、祖先たちが眠っている共通の墓地を持っていて、祖先を礼賛する儀礼もありますね。
小川
死者という、もう目の前にいなくなった人について冗舌に語れることも言葉を持つ人間の特徴ですね。私たちは、うわさ話が好きですね。その場にいない人の話をすることがなぜか楽しい。目の前にいない、去っていった人、死んでしまった人について、あたかも今ここにいるかのように語る。それが物語の力で、それがどこかで捻れると、この墓を守らなくてはならないと、隣の土地の人を敵対関係で捉えてしまうのでしょう。
永田
自分たちの祖先や死者は、既にこの世界にはいないけれど、物語として思い描くことができるのは、言葉の持つ大きな力ですね。
小川
子供の頃、お盆にナスとキュウリに割り箸を刺して馬と牛をつくったことを強烈に覚えています。今日は、本当に死者がやって来る日なんだと言って火を焚いて、来る時には馬に乗って早く来て欲しい、帰る時には牛に乗ってゆっくり帰って欲しいとお迎えした。この世は、生きてる人だけで成り立ってるわけではないと知った原点です。そのような死者との関係が、現代では失われつつあるのかもしれません。
5.曖昧さを抱えらる科学を
永田
科学は厳密を求め曖昧を排除します。しかし、日常的には曖昧さが人と人との間を取り持っていることは明らかで、この曖昧さとは何かを説明することはとても難しい。曖昧さや間は、小説を書かれる時にも大事なところかと思います。
小川
言葉は、所詮、人間の都合でつくられたもので、人間とは何かというような根本的な問題を説明できるような道具ではありません。しかし、その言葉で敢えて物語をつくろうとしているのは、時に、残酷で耐え難くもある現実の中で、本を開くと、もう一つの世界にひととき避難することができる。人類が途切れることなく物語をつくり続けてきたのは、そのような心の寛容さを育ててくれる言葉が持つ曖昧さのゆえかと思います。
今日の鼎談の前に生命誌研究館を見学して、クモの研究をされてる方のお話を伺ったら、なぜこれを研究対象に選んだか自分でもわからないのですって仰ったんですね。何か美しいものがそこにあったんですという風に。とても科学者と思えない発言をされて(笑)。そんな風に、自分でも訳がわからないままつき動かされているという感じに共感しました。

永田
短歌もそうですが、曖昧さを認識できないと文学にならないだろうと思います。その真逆が、今、話題の生成AIで、これは確率で言葉を選んで並べます。
小川
最初に私の担当になった編集者が「男はトレンチコートの裾を翻して去っていった」というような文章は絶対に書いてはいけないと言っていたのを覚えています。こう書けば大勢の人と共有できるという楽な道へ行くと袋小路に入ってしまう。だから使い古された言葉には敏感になります。辞書に載ってない言葉の意味の奥底まで、熊という言葉のない、黒い大きなものであった時代まで下りていかないと、本当の表現は見出せない。書くのに時間がかかるわけです。ストーリーやキャラクターを考えるということではなく、描写に時間が掛かるのです。
山極
屋久島に山尾三省という2001年に亡くなった詩人がいて『アニミズムという希望』という本を1999年に書かれてるんですよ。古くからの知人で、彼によれば、現代のアニミズムとは、自分が好きなもの、敬意を払えるもの、それらはすべてカミだと。漢字の神じゃなくて片仮名のカミ。それを見つめていると自分の誠が見えてくる。恐らく、クモの研究者もご自分の誠をそこに見ている。私もゴリラを見つめていると自分の誠が見えてくる。僕は、生成AIという人工の言葉のエキスパートと会話をするよりも、人間とは異なる存在をつくってきた自然と向かい合うことが大事だと思います。言葉を使い始めた人間は、自然と会話することを忘れてしまった。自然界はすべてアナログでできています。自然と向かい合い自分の誠を見る。それは生きる力を与えてくれるはずです。
小川
人間には自然からしか学べないことがあると山極さんは仰っていますね。
山極
自然は未知の事柄でいっぱいです。科学は曖昧さを許さない。自然は許してくれます。曖昧なうちにわかる、間を含めてわかる必要があるんです。自然とのつき合い方は、曖昧さを前提にわかり合うか、機先を制するかというコミュニケーションです。最近では、地面の下で、異種の植物の根同士がバクテリアの循環でお互い栄養を分け合ってることがわかっていますが、これまでは異種の植物同士は競合していると考えられていた。でも助け合ってる面があることがだんだんわかってきた。ある時は競争しながら、ある時は分かち合いながら。お互いを根絶やしにしないのが自然の姿で、そこに、厳密さを要求する科学では切り取れない部分があると思いますね。
6.生命を奥底から紡ぎ出すもの
永田
早いもので、そろそろお開きの時間となってしまいましたが、最初の山極さんの講演で、小川さんと私に投げかけられた質問に、まだお答えできていません。小川さんいかがでしょうか。「物語はいのちをどう変えたか?」難しい質問ですね。
小川
少しでも死ぬのが怖くないように人間は物語をつくっているのかな。死んだら優しい天使のようなものが空へ運んでいってくれるというような物語をつくることで、少しでも死の恐怖を和らげようとしている。限りあるいのちが、死んだ時に途切れるのでなく、死後の世界にも、自分が生まれる前の世界にもつながってるんだというように、いのちの尺を伸ばしてくれる、そういう役割を物語は果たしていると思います。また「物語は私たちをどこへ導こうとしているのか」という質問については、逆に、物語なしに人間は生きられない。真実の世界だけでは息苦しくなってしまう。曖昧で、時に嘘も混じった、理屈の通らない。そんな曖昧さの中に身を置くことを、物語は許してくれると思います。

永田
ただ、物語を書いてる時、そのように意識していませんよね。
小川
書いてる時はその世界に入り込んで、登場人物たちを観察して、追いかけていくので精いっぱい。でも彼らを操っているわけではなく、自分は物陰から彼らの様子をじっと伺っているという感じ。書くというより、イメージの中の世界を見ている時間のほうが長い気がします。
永田
短歌というのは五七五七七と定型があるので必ず終点がある。でも小説はどこで終わるかという決まりはありませんね。
小川
これは、物語のほうが終わるんです。あ、このお話はここで終わろうとしてい るということを、向こうから私に合図を送ってくれます。
永田
やはり以前、詩人に聞いた時もそう言ってました。次は、山極さんから私への質問で「言葉の基調は音楽ではないか?」。実感としてその通りだと思います。皆さんもいろいろな短歌を記憶しておられると思いますが、リズムも型もない、何の音韻も踏まない書き言葉は覚えられないでしょう。我々歌人は、少なくとも何千首かの短歌は出てきます。自然に言葉が出てくる。これは言葉にリズムと抑揚と音韻があるからで、五七五七七という定型がリズムを生み出してる。単に1つ1つの語が並んでいるのではない。言葉の本質はそういうところにあると思います。もう1つの質問は「生命の本質はリズムか?」。我々、地球上の生命体は、1日の時間を自ら刻む概日時計というしくみを体内に備えています。細胞レベルで1日の周期を制御しています。太陽の光を手掛かりに生体のリズムが1日24時間でうまく回るように調節しているのです。例えば実験でマウスを暗闇の中へ長らく置いておくと、周期がズレてうつになったりします。
山極
一生という時間は生きものによって違いますね。そもそも時間はリズムの積算ですからパターンはそれぞれ違っても、リズムを基調としながら多様な現象を自ら紡ぎ出している存在が生命なのではないかと思います。
永田
リズムが多様な生命の時間の基底にある。生命にとってリズムが大事であることは間違いありませんね。最後に小川さん、今日はいかがでしたでしょうか。
小川
お二人の著名な科学者に挟まれて、私がどれほど緊張していたかおわかりいただけたかと思いますが、どうにかお二人に助けていただき自由にしゃべることができました。ありがとうございました。

写真:川本聖哉

やまぎわ・じゅいち
1952年東京都生まれ。京都大学理学部卒。理学博士。京都大学大学院理学研究科助教授、同教授、同研究科長・理学部長を経て、第26代京都大学総長。人類進化論専攻。日本霊長類学会会長、国際霊長類学会会長、日本学術会議会長歴任。南方熊楠賞、アカデミア賞受賞。『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』など著書多数。

おがわ・ようこ
1962年岡山市生まれ 早稲田大学第一文学部文芸科卒。1988年「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞してデビュー。主な著書『妊娠カレンダー』、『博士の愛した数式』、『密やかな結晶』、『ことり』、『掌に眠る舞台』など。最新刊はエッセイ集『からだの美』(文藝春秋社刊)。
創立30周年記念

SYMPOSIUM
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

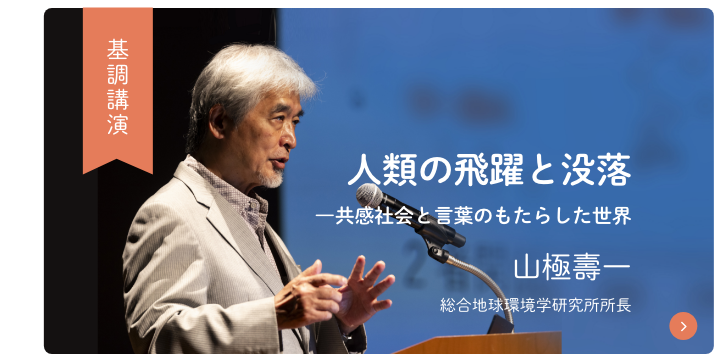















.png)